 |
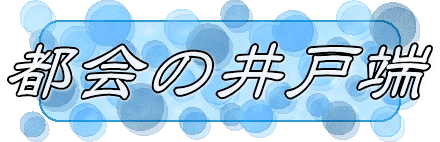 |
| 小璃間けいと歩く |
| 柴又帝釈天 | 隅田川両岸 | 早稲田界隈 | 玉川台公園と周辺 |
| 上野・早朝観蓮会 |
| 早朝観蓮会
7月も終わりの頃、「観蓮会」に出席するため、早朝不忍池に出かけた。 背丈の伸びた蓮の葉が弁天堂を取り囲んでいる。 梅雨明け後の東京は蒸し暑く、蝉の声が一段と高かった。
雲間から朝日がすーっと差す。 江戸文化文政期から続く「象鼻杯」が披露される。
すっきりとした味わい。 |
柴又帝釈天に初詣 年もあらたまり、卯の年となった。 年々「らしさ」が失われつつある日本。 お正月のお飾りは簡略化され、晴れ着姿もめっきり減った。 町の情景も普段とあまり変わらないが、 初詣には老若男女が神社仏閣に繰り出す。
足の便が良く、駅前が参道入口の「柴又帝釈天」に向かった。 京成金町線柴又駅前で先ず出迎えてくれるのは、 帽子にカバンを持った、あのお馴染みの「寅さん」!の像。 人懐っこい笑顔が、改札口の正面に立つ。 帝釈天まで続く参道は200メートル余り。 初春らしいお飾りのなか、両側には団子や手焼き煎餅、 川魚料理や縁起物の店が軒を連ね、 昔ながらの雰囲気を色濃く残している。 活気づく縁日の「庚申の日」とはまた別の、 新年の華やいだ空気がみなぎっていた。
帝釈天は題経寺といい、 江戸時代の寛永6年開創の日蓮宗の寺院。 彫刻の寺としても知られている。 寅さんが産湯をつかった「御神水」や回廊式庭園、 法華経の説話を表現した彫刻ギャラリーもあり、見所は多い。 帝釈天の裏手を行くと、「山本亭」へ。 地元のカメラ部品製造、山本工場の創立者・山本栄之助の 自宅だった建物と庭園を一般公開しており、 大正末期から四代の暮らしぶりがうかがえる。 品格のあるどっしりとした長屋門、 そこから奥へ石畳をたどると土蔵が残る。 母屋の庭に面した長い廊下に沿っては書院造りの和室が並び、 対照的に昭和初期の洋間はモダン。 いずれも往時の生活がしのばれた。 お茶をいただくことにする。 坪庭をはさみ、ガラス戸越しに見える和室や廊下の様子が、 子供のころ住んでいた家に似て懐かしかった。 都心の喧騒からはずれ、 久し振りに本来の「家」の良さをお茶とともに味わった。 長屋門の正面に見えるのが、「寅さん記念館」。 言わずと知れた‘車寅次郎’の世界が繰り広げられる。 昭和の下町にタイムスリップ!! 記念館から江戸川の土手にでる。 ビルに切り取られる景色もなく、のびやかだ。 水面をわたる真冬の風は冷たかったが、 川の流れと土手がどこまでも見るかぎり続き、 気持ちよかった。 向こう岸は千葉県の松戸市。 そこと柴又を結ぶのが「矢切に渡し」だ。 この日もゆっくりと小舟が行き交い、 伊藤左千夫の小説『野菊の墓』の冒頭が思い出された。 再び参道を通り、柴又駅へ戻る途中で考えた。
ただし営業日は、金、土、日のみ。 |
初冬の隅田川両岸を歩く
冴えわたる冬空の下、川の表情はじつに豊かだ。 吾妻橋の浅草側のたもとに立つと、 向こう岸のレトロなアサヒビール・ビアホールが、 大川端で夕涼みをした江戸庶民がタイムスリップしてきたら・・・ ここは水戸徳川家下屋敷跡で、潮入回遊式庭園の一部が残る。 公園北側は「牛嶋神社」。 水戸街道に出ると、東京スカイツリー撮影ポイントの言問橋東交差点。 右側には凧の「唐変木庵」や「富士かりんとう」、 その先にあるのが向嶋墨堤組合見番で、 さらに進むと長命寺。徳川家三代将軍家光が 寺の裏が「長命寺桜もち」で、向かいが「言問団子」。 土手に上がり桜橋を歩くと、上流には白髭橋、 桜橋の先に広がる浅草は、暮れも新年も一際賑やか。 |
早稲田界隈
暑く長かった2010年の夏が遠のき、待ちわびた秋の到来だ! そんなわけではないが、山手線内一の高さを誇る その一角にあるのが穴八幡宮。 高田馬場といえば思い出されるのが、 馬場は寛永13年(1636)に造られ、将軍家の厄除けや若君誕生の際、 交差点から早稲田大学文学部の前を過ぎ、箱根山通りへ。 野鳥のさえずりを耳に、しばし園路をたどると、 一帯は、江戸寛文年間、尾張藩主徳川光友が 下山し、戸山ハイツを左に見て歩くと、明治通りに出る。 園内は緑あふれ、芝生やアスレチックなど 公園の最北、高田馬場口から通りに出ると、 深まりゆく秋の早稲田の杜、野球部のハンカチ王子に、 |
||
多摩川台公園とその周辺
降り立った東急東横線多摩川駅ホームを吹き抜ける風は、木々の緑の匂い。 ここは大田区田園調布。 多摩川浅間神社は800年ほど前の創建で、 多摩川台公園は多摩川に沿った広大な丘陵地で、 眼下に多摩川を臨む見晴台やあずま屋も点在し、 南端のアジサイ園では7種、3000株のアジサイの花が咲き、 園内には亀甲山(かめのこやま)古墳と宝莱山古墳、 その宝莱山古墳へ続くのが山野草のみち。 多摩川台公園を後に坂を下ると、宝来公園が見えてくる。 整えられた瀟洒な町並みを抜け駅のロータリーに近づくと、 |