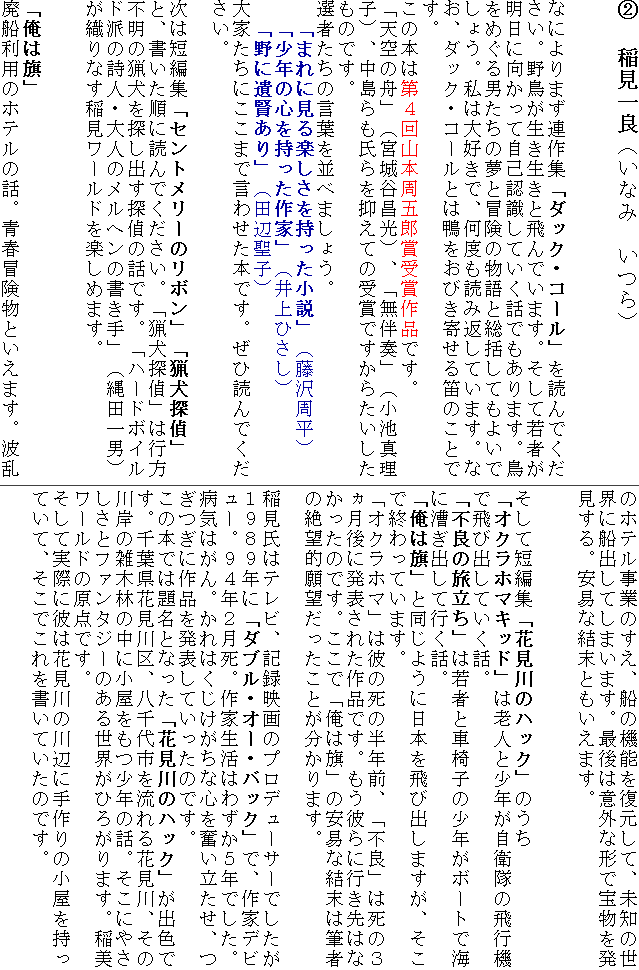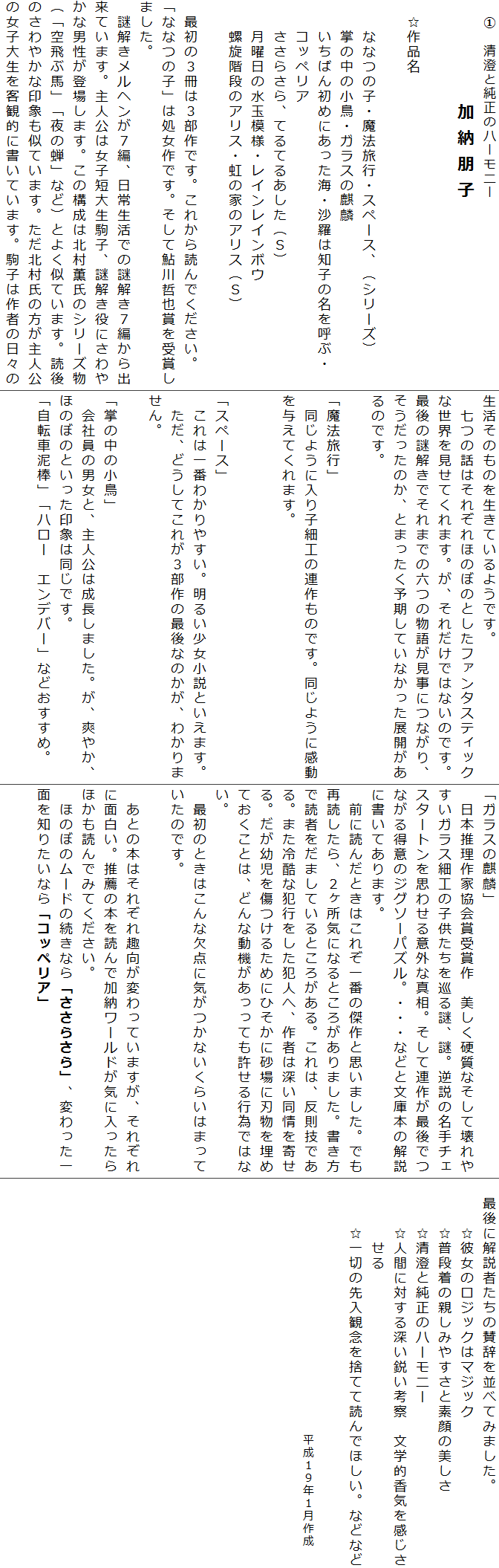数学エンターテイメントの伝道師
桜井進の「雪月花の数学」
メタメタ面白い本を友人に教えてもらいました。それも数学の本です。
私は数学が苦手で、その類の本は全く読んでいません。
それが読みだしたら止まりません。一気に読んでしまいました。
今回はこの本だけを紹介したいと思います。
●自然の美、西洋の美は数列にあった。
1202年フィボナッチは数列:F(n+2)=F(n+1)+Fを発見しました。
彼の名をとってフィボナッチ数列と呼ばれます。
この数列は「ある数は前の二つの数を足したもの」を意味します。
1、0+1=1 1+1=2 2+1=3・・・・・
ですからこの数列は
1,1、2,3,5,8、13,21,34・・・・・
となり、どこまでも続きます。
●さて実はこの数列から螺旋が生まれるのです。
① 辺の長さが1の正方形を二つ並べて描く。
② つぎに長さ2の正方形を①の上の書く。
③ ②の正方形の横に3の正方形を描く。
④ ③の正方形の下に5の正方形を描く
⑤ …以下どこまでも・・・
ここでそれぞれの正方形の辺を半径として4分ノ1の円を書き順につなげていく。
すると螺旋が誕生します。
螺旋は自然界に溢れています。見慣れています。
巻き貝、朝顔の蔓、台風の渦・・・自然界に溢れている螺旋が数学の理論的定式から
作られているなんて、考えもしませんでした。
「黄金比」という言葉をご存知ですか?
西洋では美と調和を感じる最も美しい比率とされてきました。
神の比率ともいわれます。
ピラミッド、パルテノン神殿の縦横、ミロのヴィーナスなどに取り入れられている。
カード、国旗の縦横比も黄金比になっている。
その比率は 1:1,6181・・・
フィボナッチ数列の隣り合った数字どうしで割ってみます。
例(8÷5=1,6)(13÷8=1,625)
どんどん大きな数字で計算するとく答えは1,6181・・・と続く無理数になります。
なんと黄金比はフィボナッチ数列から導き出されるのです。
●日本の美は白銀比
また筆者は日本の美は白銀比にあるといいます。それは1:√2です。
日本の建築・華道に白銀比が現れる。(説明は省略)
A版、B版など、用紙の寸法も1:√2です。
この比率の紙は半分に折っても同じ形になります。
どこまで折っても相似形になっています。
そのほかにも『目から鱗』の話がたくさんありました。
ひまわりの花の種の並び方は黄金比になっている。
生け花が大切にする奇数、俳句はなぜ5,7,5なのか
世界一の数学大国だった日本
万葉集の時代から九九はあった。
「二八十一」と書いて「ニクク」と読ましてます。
二九九と書いても読めるのにお遊びでこう書いているのです。などなど・・・
ぜひ一度読んでください。
難しい数式も出てきますが、分からなくても楽しさはかわりません。
●エピソード
面白くて、妻にフィボナッチ数列を説明しました。
その3日あと妻は小原流の生け花の雑誌を捨てるつもりで整理していました。
妻はそのなかの1冊に数列から作る螺旋の図をみつけました。
そのほか同じ話、図、写真がいっぱいありました。
黄金比・白銀比は生け花の前提という趣旨の記事でした。
妻に説明していなかったら、妻は何も考えず捨てていたはずです。
この偶然には驚きました。
著者は三井秀樹という人です。
玉川大学教授で、「かたちの日本美」「美のジャポニズム」ほか数冊書いていると
筆者紹介にあります。
まったく同じことを同じ例で説明しています。
私にはどちらかが剽窃したとしか思えません。師弟関係なのでしょうか。
これが謎になってしまいました。
平成23年12月
 ページトップへ ページトップへ   (@を英半角@にして送信して下さい) (@を英半角@にして送信して下さい)
|

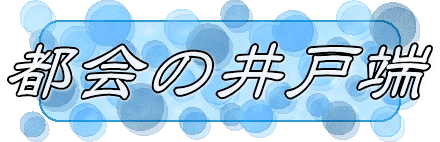
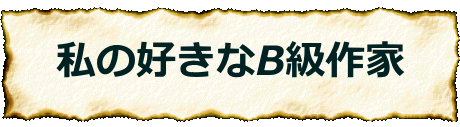

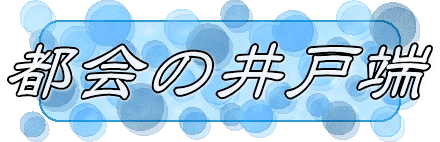
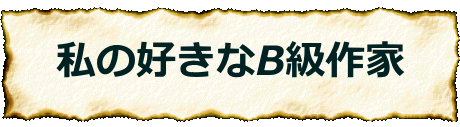
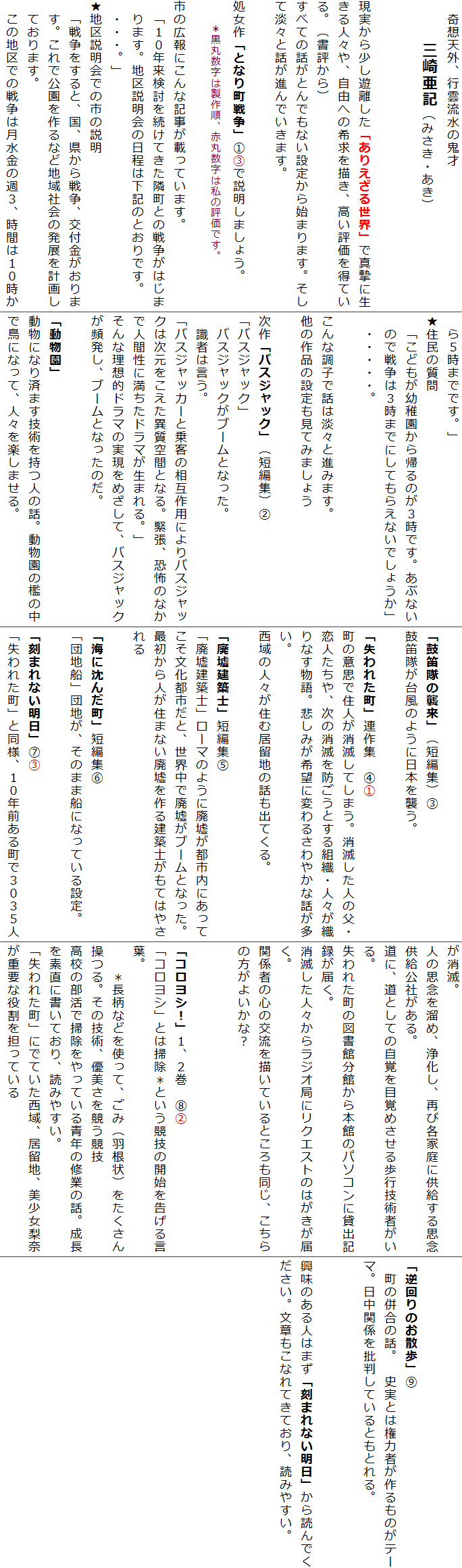
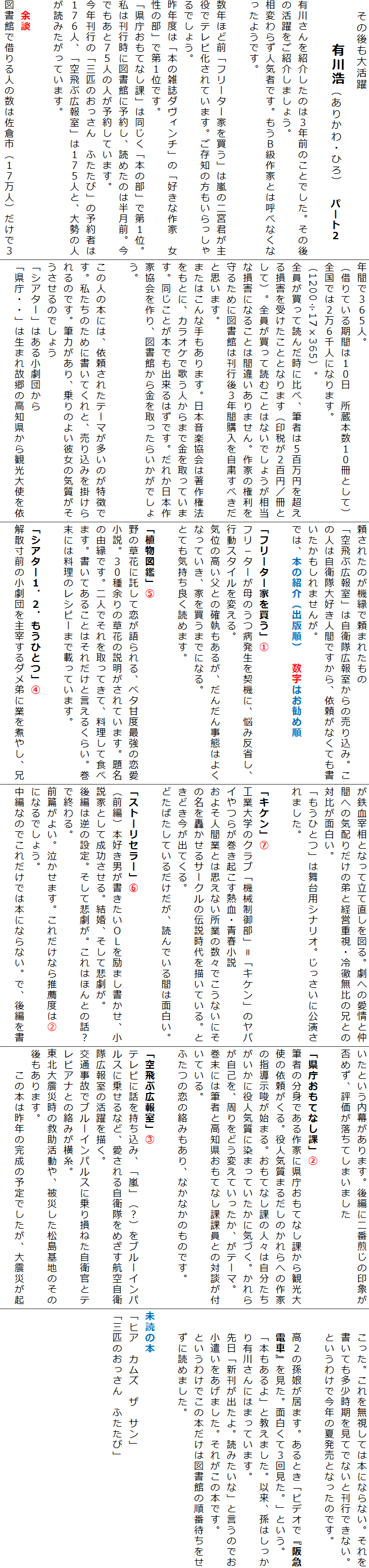
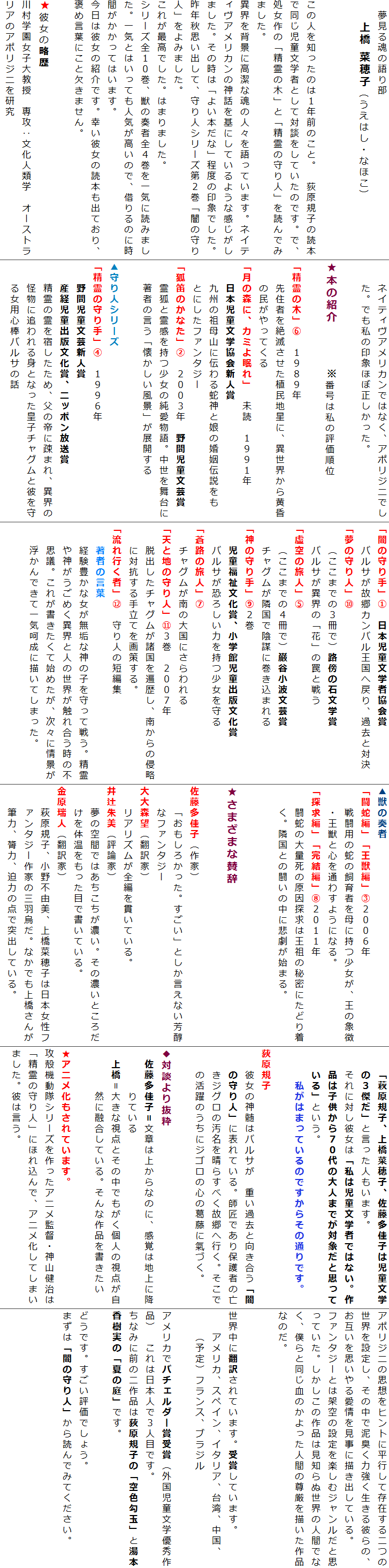
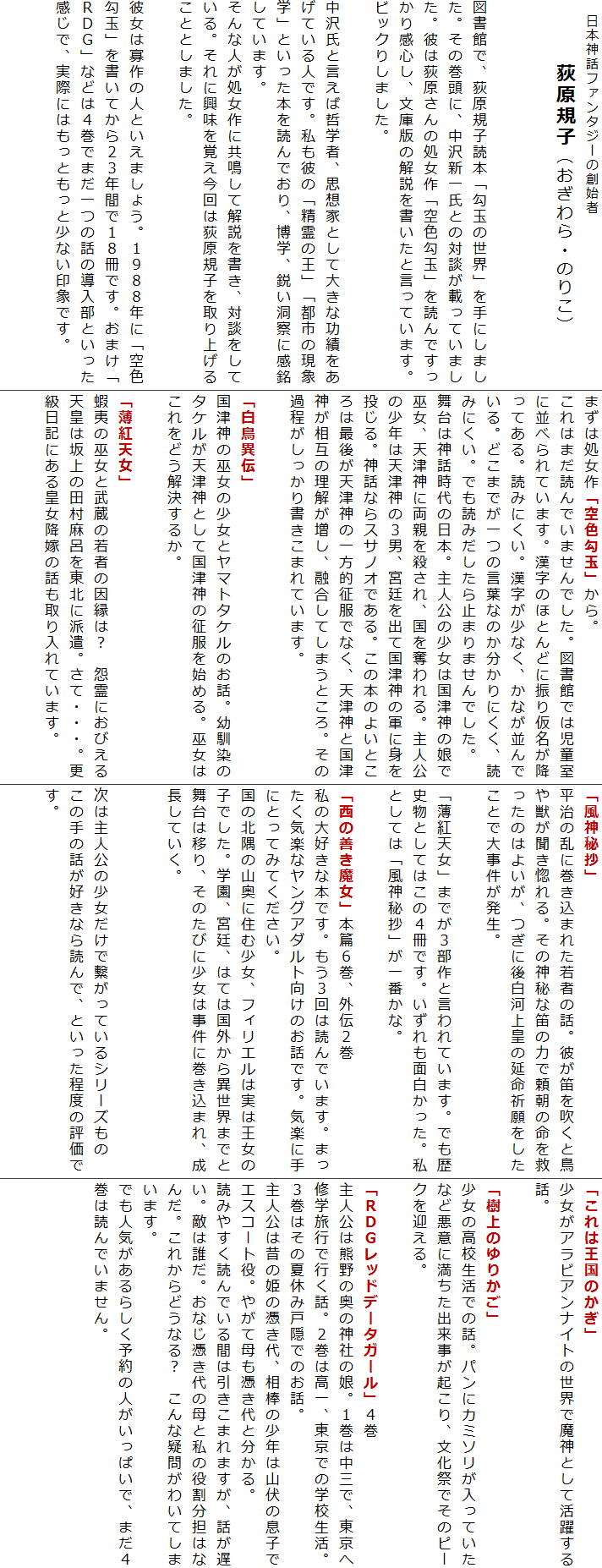
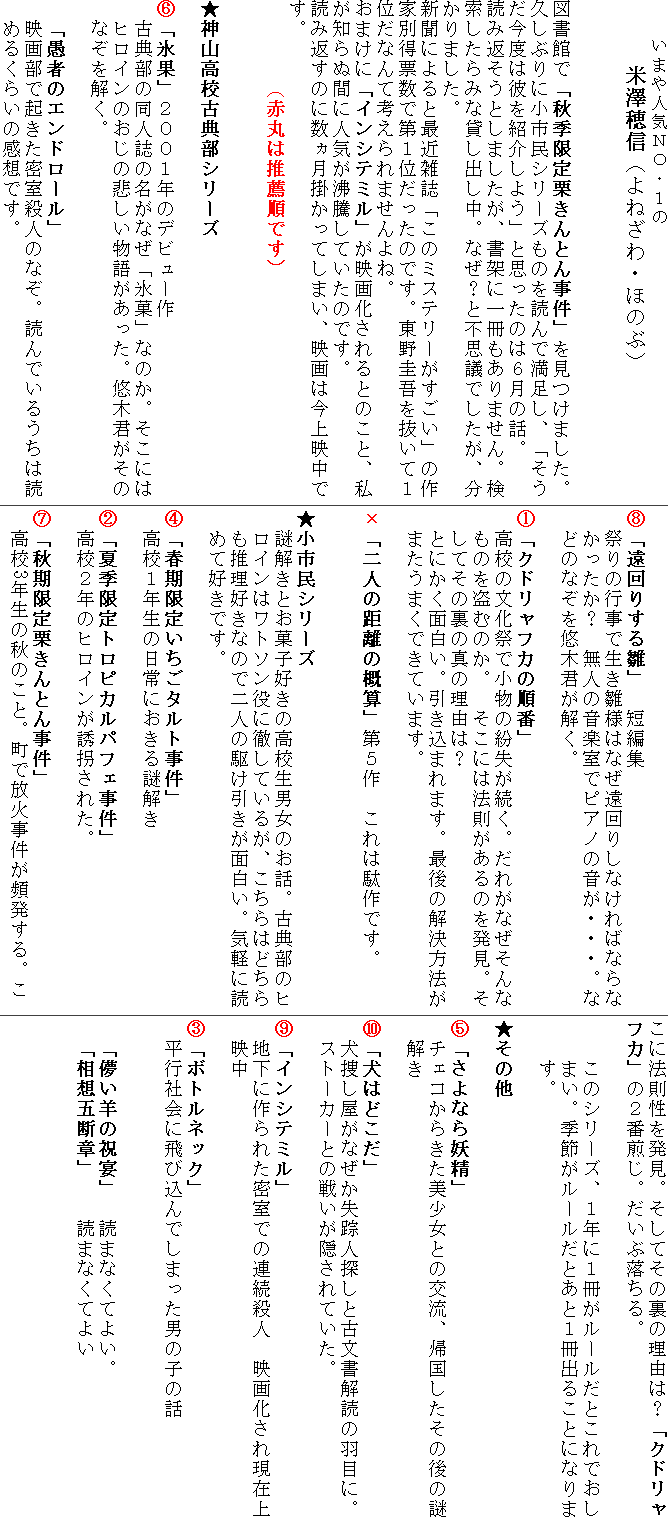
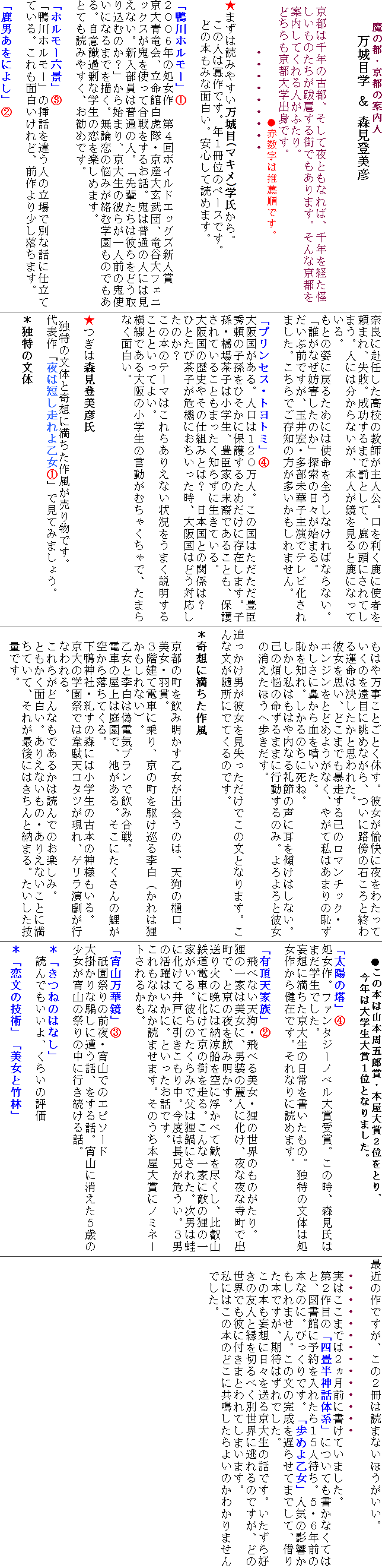
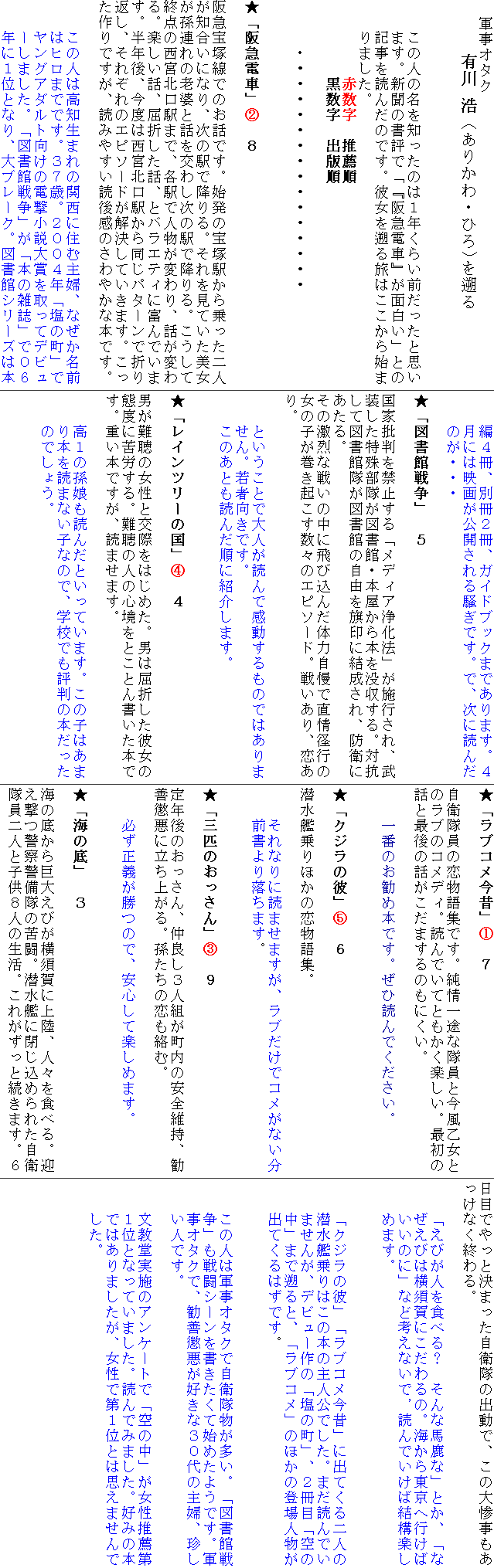
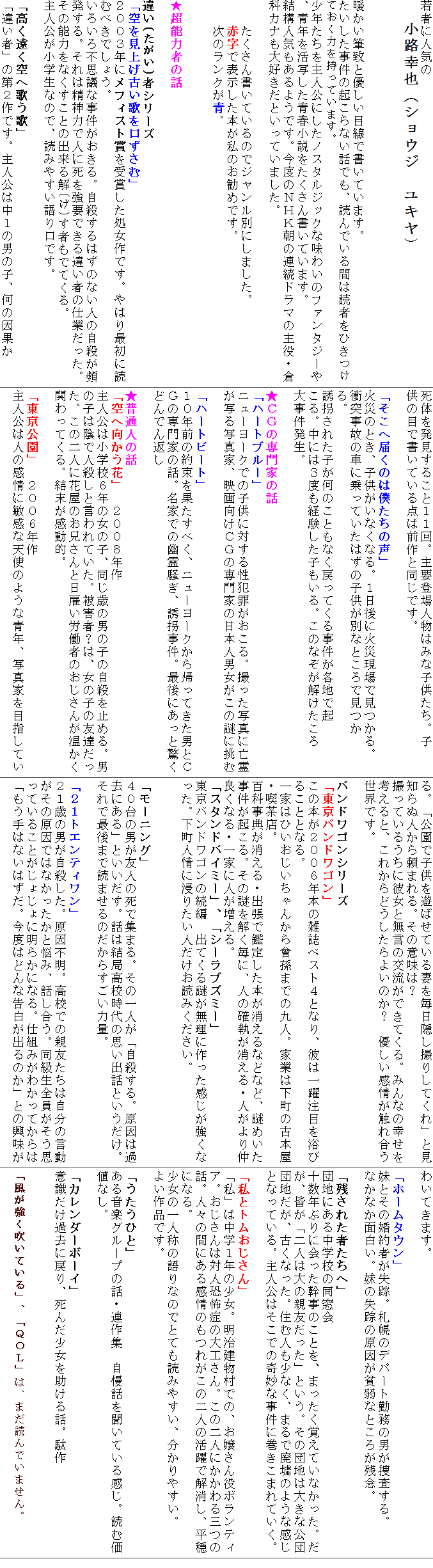
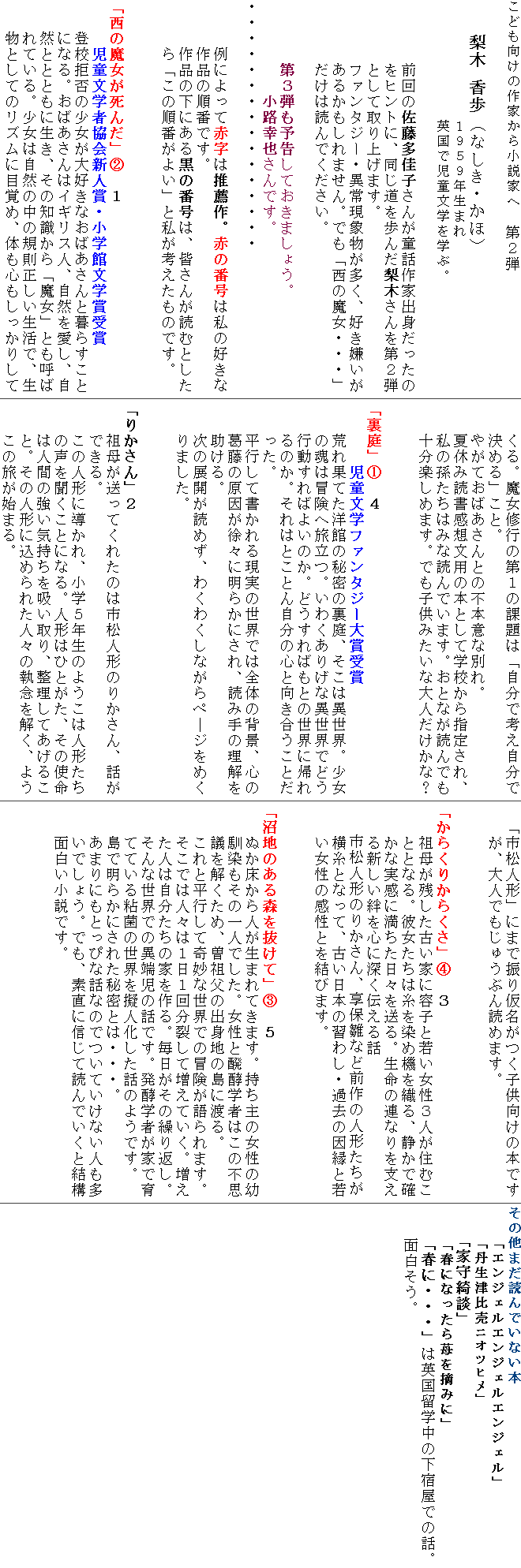
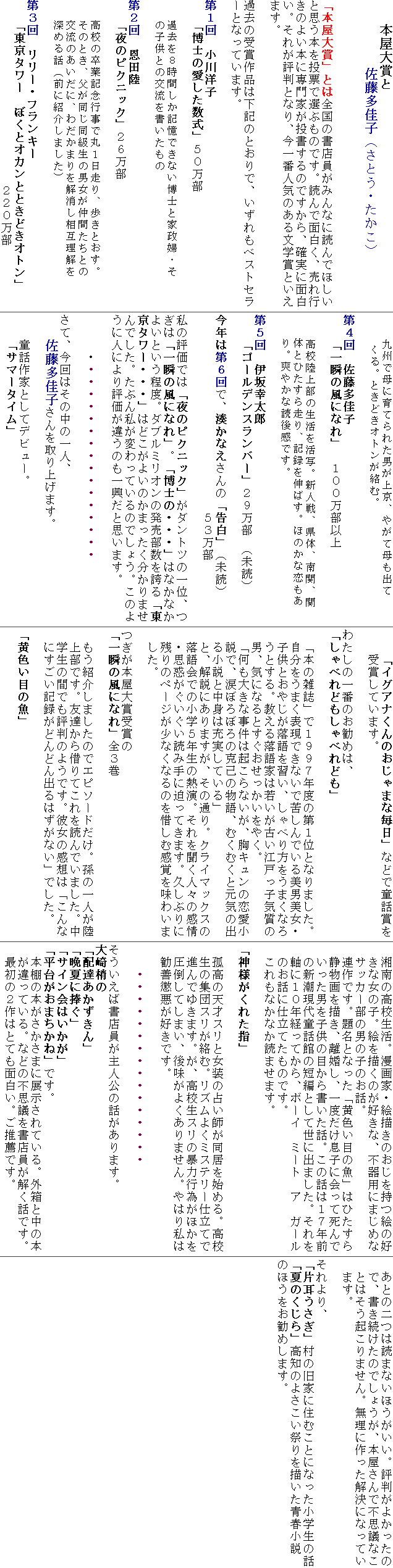
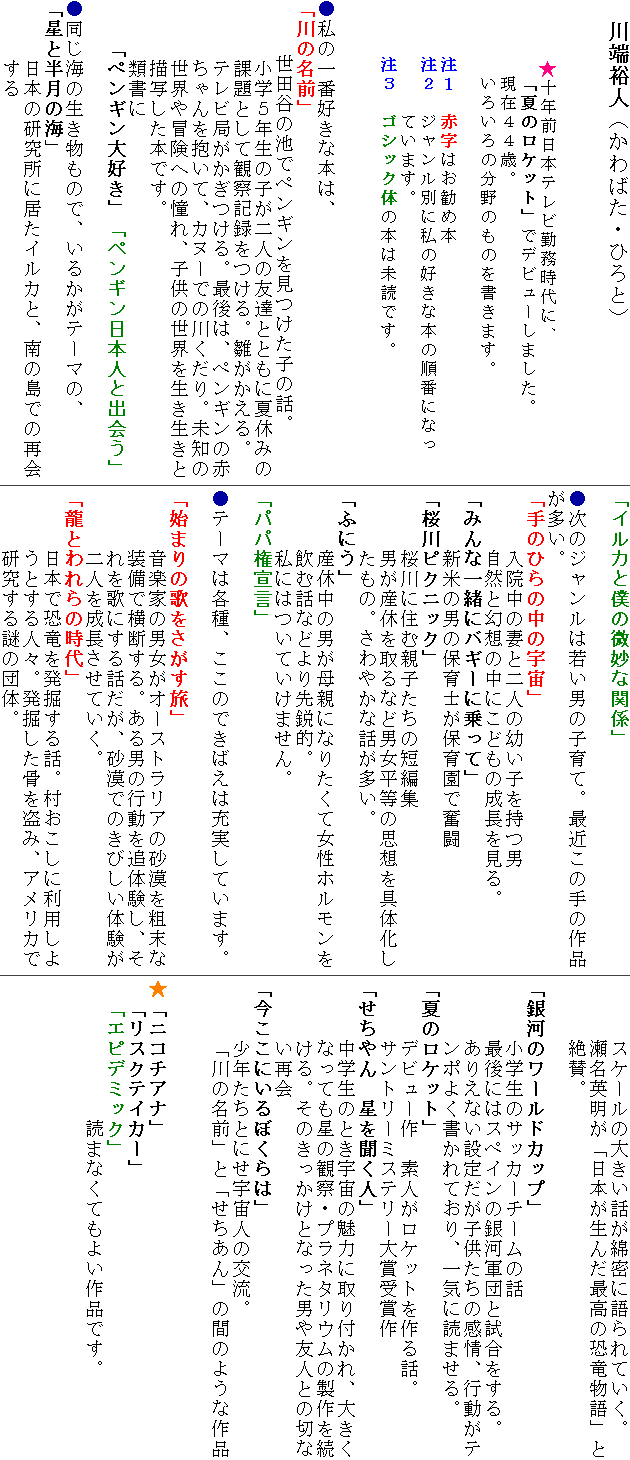
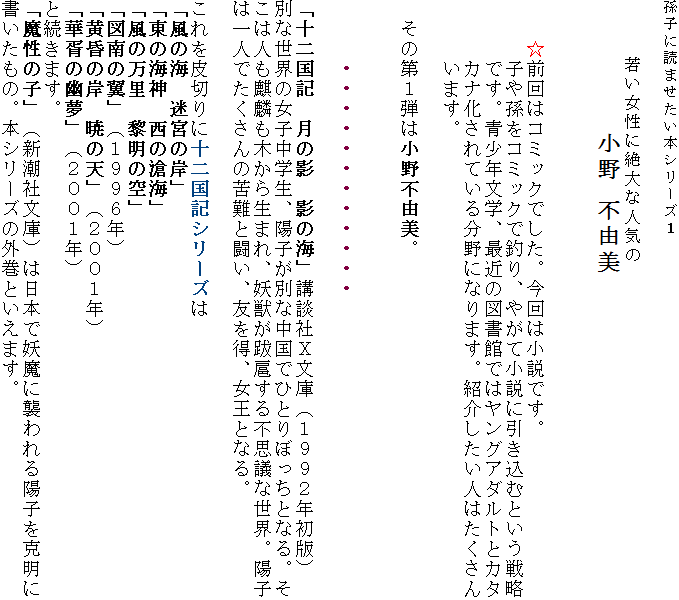
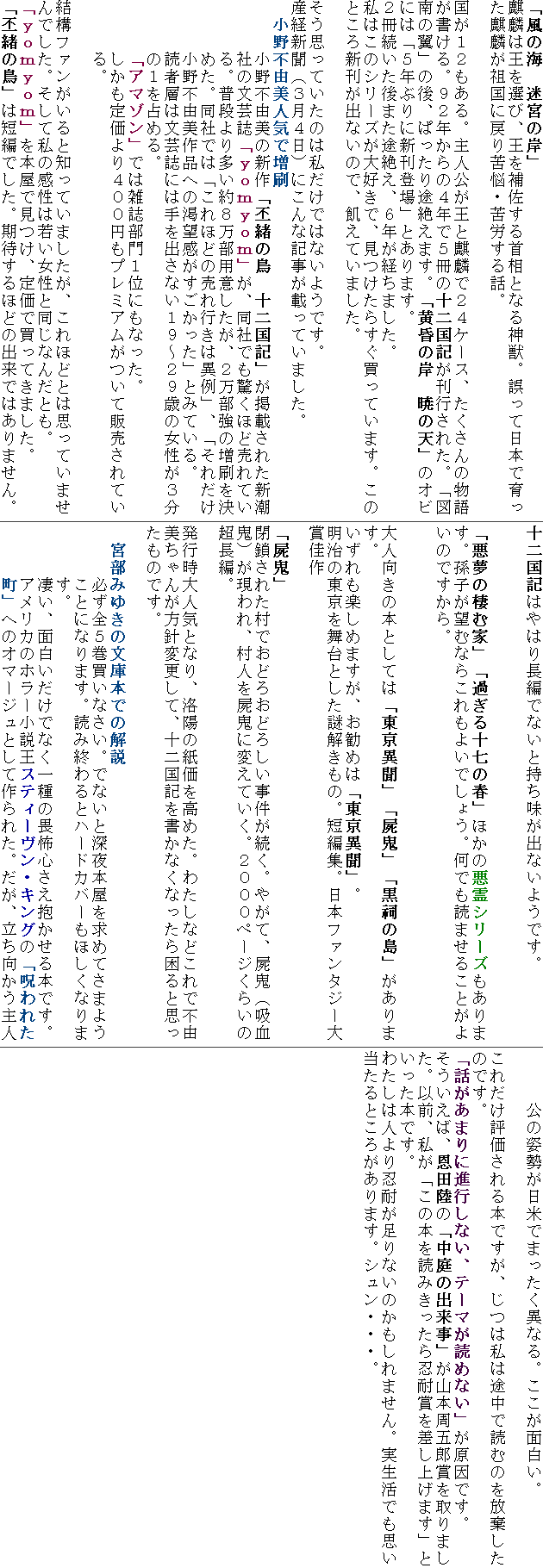
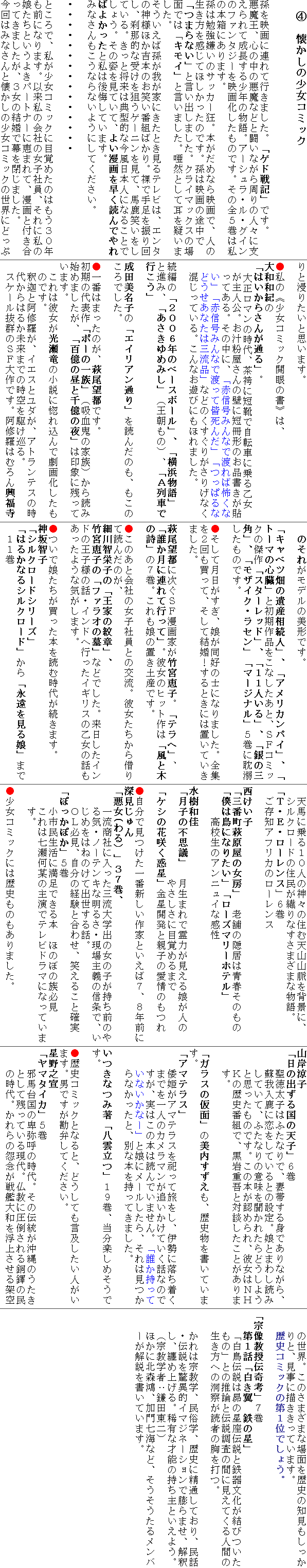
![③卓越した技巧と多彩な物語メーカー
恩田 陸(おんだ・りく)
恩田陸、64年生まれの女性。多作家です。これを書くにあたり、図書館でチェックして、驚きました。私は30冊読んでいる。でもまだ読んでいない本が11冊もあった。十数年で40冊以上書いているのだ。
そして「木洩れ日に泳ぐ魚」などは予約が23人も入っている。もうすっかり人気者で、B級作家とはいえなくなってしまった。「夜のピクニック」で吉川英治新人賞・本屋大賞を受賞し、ブレイクしたせいです。
今回はそれまではマイナーだったとして、紹介させてください。
読んだ本を分類してみました。でも学園ものに分類されていても推理、青春、異次元ものとあり、単なる目安に過ぎません。
作品一覧(既読)
まず読んでもらいたい本に★印をつけます。
タイトルが赤字ゴシック体のものは、恩田色の強い本です。
読みやすさとジャンルを意識して選択しました。
[学園もの]
★六番目の小夜子、
★夜のピクニック、
ネバーランド、
球形の季節、
図書館の海(短編集)、
[架空の隔離された世界]・・・・・・・・・・・・
ロメオとロメオは永遠に、
麦の海に沈む果実
夏の名残の薔薇、
[異次元・タイムトラベル]・・・・・・・・・・・
★月の裏側、
ねじの回転、
ネクロポリス、
ライオンハート、メイズ、
[超能力]
劫尽童女、
光の帝国常野物語、
★蒲公英草紙 常野物語、
禁じられた楽園、
[短編集(推理)]
木曜組曲、
象と耳鳴り、
[推理]
三月は深き紅の淵を、
黄昏の百合の骨、
不安な童話
[抱腹絶倒・冒険]
★ドミノ、
上と外と、
[心理・感情]
ユージニア、
黒と茶の幻想、
まひるの月を追いかけて、
クレオパトラの夢、
蛇行する川のほとり、
Q&A、 (以上30冊)
初めての方は★印の作品を読んだあとに、好きなジャンルの本を読んでください。どれも期待を裏切らないと思います。ただし「中庭の出来事」だけは読まないでください。私は途中でやめました。読みきった人には忍耐賞を差し上げます。ほかにも一冊、ひどい本がありましたが、名前を忘れました。
(私の未読作品は・・・)
木洩れ日に泳ぐ魚、青にささげる悪夢、
朝日のようにさわやかに、エンドゲーム常野物語、 七つの黒い夢、血と12幻想、パズル、
チョコレートコスモス、殺人木の放課後、絶海、
中庭の出来事(11冊)
では、★印の作品について少し紹介しておきましょう。
★六番目の小夜子
処女作、日本ファンタジー大賞最終候補作。綾辻行 人・小野不由美絶賛
伝統高校の奇妙な伝統。誰かがひそかに小夜子に指 名される。みな小夜子がいることは知っているが、 誰がそうかは知らない。六番目の小夜子を巡り、奇 妙な出来事が続発する。
やはりこれから読んでください。原点ですから。
★夜のピクニック
池上冬樹はいう、「新作にしてすでに名作。ずっと 愛される青春小説、ノスタルジックでリリカルで、 多幸感に満ちたすばらしい小説」
高校の行事、80キロを歩く鍛錬歩行祭の一日を書 いています。
一昨年、本屋大賞・吉川英治大賞新人賞を取りまし た。
これから読んではいけません。これでファンになっ てほかの本を読むと違和感が出てしまいますから。 彼女の本には超能力・異次元などのスパイスがつき 物。まずそちらを読んでから、これを読んでくださ い。恩田ワールドが好きになった人も嫌いになった 人もこの本には満足します。
★月の裏側
異次元生物侵略ものです。こんな言葉に拒否反応を 起こす人も、まあ読んでください。
ある町に無個性の人が増えてくる。ふと気がついて 調べ始めると・・・。じんわりと始まる恐怖がだん だんと大きくなって・・・。
★蒲公英草紙 常野物語
隠れて暮らす優しい超能力者の一族の話、常野物語 第2弾。
常野はいうまでもなく遠野物語を意識しています。
昔はよい人たちがいたんだなーと感じさせる物語で す。素直なストーリーで読みやすい。これを2番目 に読んでください。
★ドミノ
登場人物は、保険会社の部長・OG、過激派、暴走 族、元刑事、少女タレント志望、別れ話の3人、推 理マニアの大学生たちと盛り沢山。この無関係な 人々が東京駅周辺で、爆弾をめぐり大騒動。ドミノ 倒しそのままのスピードで話は展開し、大団円とな る。楽しい本。
ここまで読んできても、恩田ワールドになじめない人は★印以外の黒文字タイトルの本だけを読んでください。それなりに楽しめます。好きになった人は手当たりしだい読んでください。
最後に私が選んだベスト3をお知らせしましょう。ただし恩田ワールドが好きになった人向きです。細かい紹介はわざと省きます。ご自分でご賞味ください。
●ねじの回転 2・26事件を扱ったタイムトラ ベルもの 詳細な調査、的確な人 物描写、重厚な筆致
●ネクロポリス あの世と繋がる孤島で起こる殺人 事件
恩田らしさを存分に発揮
●ユージニア 集団幻想を描ききった鮮やかな傑
作 山田正紀絶賛
追 記
「エンドゲーム常野物語」を読みました。失敗作です。「中庭の出来事」を含め、最近の本は多作の悪影響が出ているのかもしれません。](vimgtext53.gif)