 |
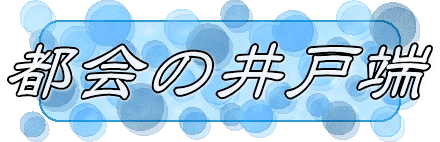 |
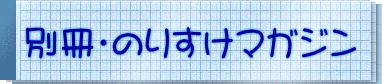 |
|
|
 |
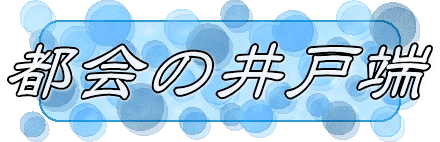 |
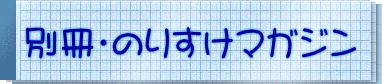 |
|
|
| のりすけ 自己紹介へ 「のりすけのショートショート」へ |
|||
| 栃木市 | 小和田 | 常陸太田 | 波佐見 |
| 崎 津 | 伊予大洲 | プリンスエドワード島 | 柳 川 |
| 遠州森 | 姨捨 | 備中高梁 | 郡上八幡 |
| 神 埼 | リオデジャネイロ | リオデジャネイロ② | 八 女 |
| 尾 道 | 鞍 馬 | 萩 | 津和野 |
| 関 門 | new! 温泉津 | ||
温泉の港(津)と書いて「ゆのつ」と読む。難読地名のヒトツかもしれない。
町並みといい、温泉といい、ひたすらゆっくりしてアクセクした日常を忘れるに限る。
単に移動時間のみを比較すると、仁摩町から県道31号線を通るルートの方が近いのだが、
|
||||||||||||||||||||||
関門とは地名ではない。下関(山口県下関市)と門司(福岡県北九州市門司区)を併せた呼称である。
下関と門司の間に関門海峡が横たわっているが、どちらかにクルマを駐車すれば、
江戸時代には、宮本武蔵と佐々木小次郎が巌流島(下関市)で決闘している。
関門海峡を渡る風に吹かれながら、歴史を紡いできた関門の史跡を歩いているうちに、
|
||||||||||||||||||||
萩と津和野は、観光コース的にセットで語られることが多いが、
津和野のもう一つのアイコンが、堀に大量にいる錦鯉である。
元々、山がちな場所だけに、津和野の観光資源はコンパクトにまとまっている。
|
||||||||||||||||
萩は長州藩毛利家の本拠地である。
同じような城下町が「町並み保存条例」などで白壁の町並みを保存使用しているのに対して、
「おもしろき こともなき世を おもしろく」
|
||||||||||||||||
のりすけ紀行には、あまりメジャーでない観光地が並んでいる。 「鞍馬天狗のおいちゃんもこの空気の中で暮らしていたんだろうな」などと、
どう見ても“イヌ”には見えない。しかも肩凝りしそうな姿勢で座っている。
ただ、足下は、木の根っこが地表に露出した状態になっており、極めて歩きにくい。
貴船神社は、本来、水の神様であったはずなのだが、なにやら縁結びの神様になっているのだそうで、
|
||||||||||||||||||||
坂が見えた。坂が見える。五年振りに見る尾道の坂はなつかしい。
新幹線を利用して新尾道から入る手段もあるが、ここは放浪記のとおり、
林芙美子の他にも志賀直哉などの尾道にまつわる作家は多く、旧家などもあるが、
ところで、肝心の尾道の海であるが、
|
||||||||||||||||||||
矢部川が流れる八女盆地は、農耕に適した土地として縄文の昔から集落ができ、
岩戸山古墳から八女丘陵のお茶畑の中を15分ほどドライブすると、
今度は、八女市街を抜け国道442号線を矢部川の上流に向かうと、
|
||||||||||||||||
前回の「リオデジャネイロ」はすこぶる評判が悪かった。
基本的に車社会であることも共通しているようで、地下鉄もあることはあるのだが、
このボン・ジ・アスカールは、2016年リオ五輪の公式エンブレムにもなっているから、
|
||||||||||||||||||||||
のりすけ紀行2回目の海外編である。
クタクタではあるが、せっかく遠いところまで来たのだから、ブラジルらしい場所に行こうと考え、
|
||||||||||||||||||
神埼市は佐賀平野東部にあって、北側の背振(せぶり)山地から久留米市に接する南側まで、
ただし、九年庵と仁比山神社に関係性はない。 城原川沿いのキャンプ場にクルマを駐めて、まずは立派な仁王像が左右に立つ山門をくぐって山の方に進む。 もし一般公開の時期に行くのなら、朝早く行くことをお奨めする。
|
||||||||||||||||||
あくまでも個人的な見解だが、
郡上八幡駅から街の中心部、旧庁舎記念館あたりまでは少し歩く。
|
|||||||||||||||||||
倉敷で伯備線に乗り換えて、高梁川沿いに中国山地の中に分け入ると、30分少々で備中高梁に至る。
実は記憶が鮮明なのは、ストーリーの方ではなく、
|
||||||||||||||||||
姨捨は日本三大車窓の一つに数えられている。
|
||||||||||||||
海道一の大親分、清水の次郎長一家の有名人と言えば「森の石松」が挙がる。
|
||||||||||||||
水郷・柳川にはJRの駅がないので、西鉄大牟田線を利用する。
一般的には、川下り舟に乗船して観光スポットを回るのだが、
|
||||||||||||||
長らくサラリーマンをやっていると思いがけない場所に出張することがある。
せっかくなので、とりあえず感動している風をがんばって装ってはみたが、
|
||||||||||||||
愛媛県大洲市に行ってきた。
その先の臥竜山荘は趣味のイイ造りだ。
|
||||||||||||||
崎津集落は、現在の行政区分では熊本県天草市河浦町に属している。
|
||||||||||
長崎県波佐見は、佐賀県有田と隣接している。
|
||||||||||
茨城県常陸太田市は、JR水郡線で上菅谷まで行き、
|
||||||||||
「小和田」は駅の名前というだけであって、正確な地名であるかすら不明である。 道路ははるか山の上を通っているので、車で行くとしたら国道沿いに車を路駐した上で、 道のない山の中を歩き続けることになるそうだ。 地元の人たちに捜索活動の迷惑を掛けた上に、翌日の地元新聞に載りたくなければ、 大人しくJRで行くことをお奨めする。 駅のホームの両側、少し離れた場所にトンネルがあり、 トンネルで切り取られた山間の空間に駅舎とホームが存在しているのみである。 駅から小径を少し下に降りてみる。 皇太子殿下御成婚時に造られたのであろうベンチと休憩所があるが、 特に記念写真を撮るようなものでもないし、 これを見るためにここまで来るような観光客もいないだろう。 特別な文化的な価値があるようでもなく、 あと十数年もすれば自然に朽ち果てていくのを待っているような風情である。 雑木林と雑草の合間から天竜川の流れを眺めることができるが、 少し遠いこともあって、清流の風情などを感じることもできない。 これ以上は何もない。 つまり、「小和田」には観光地に必要な要素、 すなわち見るべき物が何も無いのである。 地方の郊外に行くと「日本の原風景が……」みたいな感想を言うことが多いが、 「小和田」に日本の原風景は見あたらない。 少なくとも筆者の目にはそう映った。 目に入るのは、酔狂な秘境駅マニアという、 あまり一般的ではない日本人くらいである。
「小和田」には、見るべき物はないが、感じるべきものは多くあった。 過去、日本人は、このような山の中を開拓して生活圏を拡大していったのだ。 「小和田」の開拓が、この国の発展にどんな役割を果たしたのかは分からないが、 先人達の逞しいフロンティアスピリットと環境対応能力を感じる。 今現在、廃村となっているこの場所に、毎日列車が停車して、 マニアと言う名の少しずれた連中を運んで来ている、 そんな日本社会の懐の深さも感じることもできた。
|
||||||||||||
栃木県栃木市。実にマイナーである。
|
||||||||||