 |
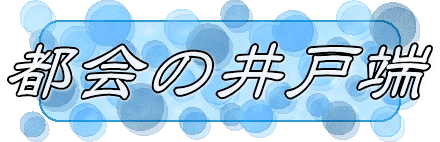 |
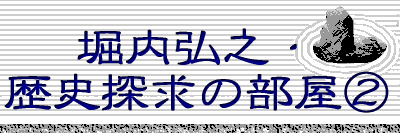 独自の視点で「始まり」を探求します。 歴史探究の部屋①では「歴史の謎」を考察します。 作者の堀内弘之は故人となりました。 掲載分のみですが、お楽しみください。 |
 |
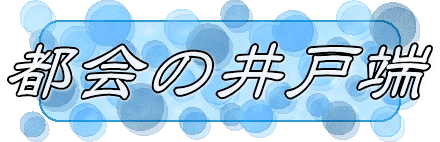 |
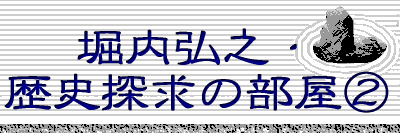 独自の視点で「始まり」を探求します。 歴史探究の部屋①では「歴史の謎」を考察します。 作者の堀内弘之は故人となりました。 掲載分のみですが、お楽しみください。 |
| ものの始まりに興味があります。 はるか昔のこと、資料も少ない。色々推測、推理するのがおもしろい。 このところ画期的名学説が出ています。しかも皆そのことをあまり知らない。 たとえば古代文明の始まりは四大文明とならいました。エジプト・メソポタミア・インダス・黄河でしたね。 でも、安田氏によればその前に文明があったのです。 漢字はどうしてできたのか。白川静氏は昭和45年人に「漢字」という本で新解釈を発表しました。 これにより昔からの解釈は一変に粉砕されてしまいました。 それやこれやの「始まり」をしばらく書いてみたいと思います。 しらすよみひと(堀内弘之ペンネーム)私の好きなB級作家 |
| 縄文人はどこから来たか | 縄文時代の日本 | 漢字の始まり 第1部 |
| 中国文明の始まり | 漢字を大事にしよう | 書くことは良いこと |
| 弥生人はどこからきたか(前) | 弥生人はどこからきたか(後) | |
| 弥生の歴史 大和の誕生1・日読みの世界 | 大和の誕生2銅鐸国家の興亡 | |
| 大和の誕生3 オオクニヌシ縄文人説 |
 ※纏向遺跡 http://inoues.net/club/makimuku.html |
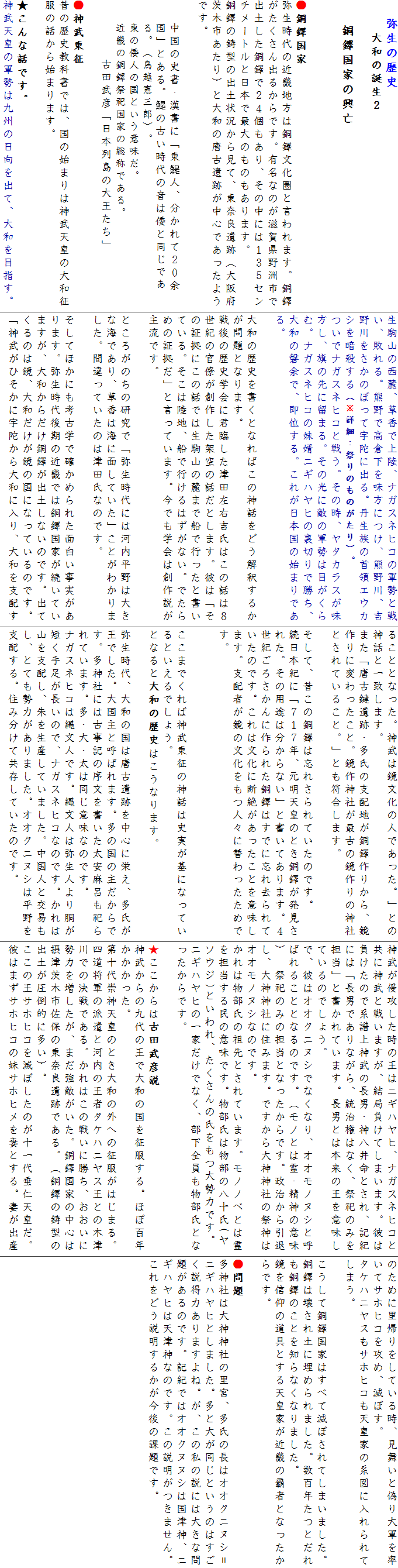
|
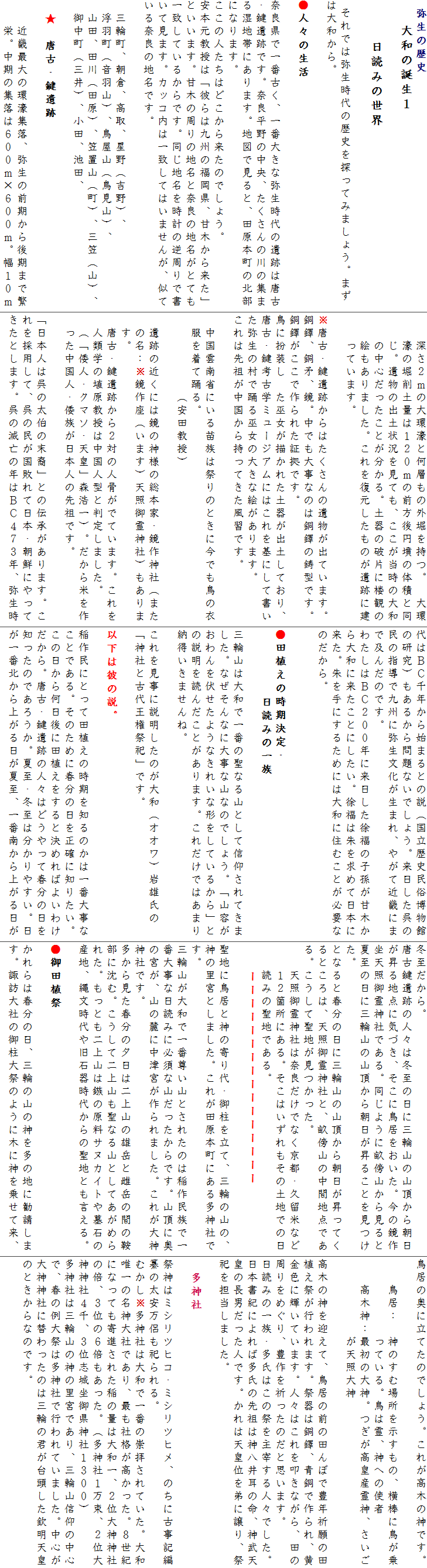 唐古・鍵遺跡 http://inoues.net/club/karakokagi_new.html 多神社 http://www.d3.dion.ne.jp/~stan/txt0/n1oo01.htm 鏡作座天照御霊神社http://www.norichan.jp/jinja/shigoto/kagamitsukuriniimasuamaterumitama.htm |
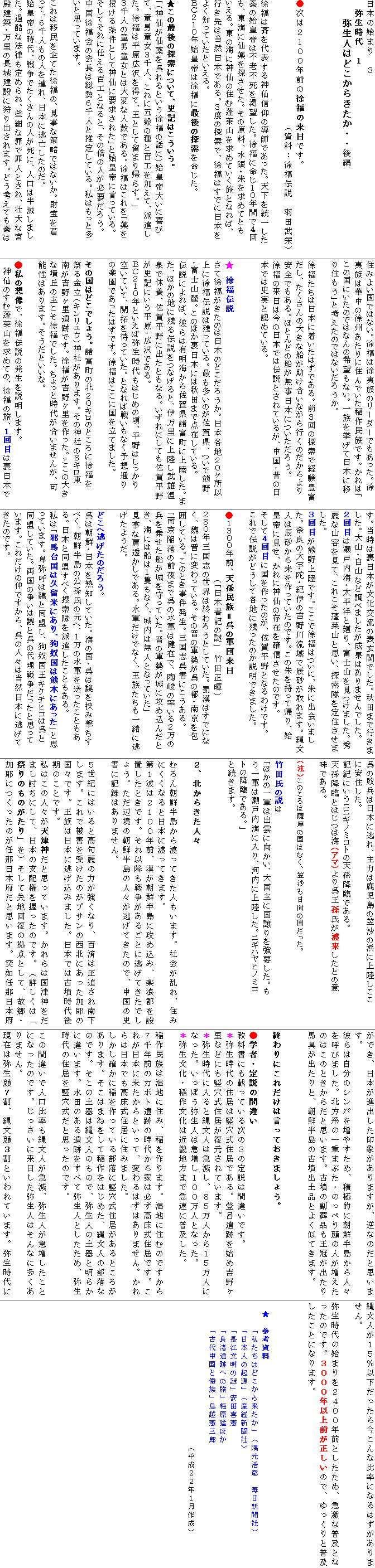 と と |
![日本の始まり 3
弥生時代1
弥生人はどこからきたか・・(前編)
1、稲の民はいつどこから来たのだろう
★稲作の起源(おさらい)
稲は1万7千年前から、中国の長江中流で栽培され始め
た。長江下流の淅江省河姆渡遺跡は高床式住居が立ち並
ぶ大変大きな遺跡である。ここでは7千年前から熱帯性
ジャポニカが作られていた。5千年前から温帯性ジャポ
ニカが作られはじめ、収穫量は飛躍的に大きくなった。
発掘した倉庫には稲籾が120トンも残っていた。
ひょうたんとはと麦を栽培。最古の漆椀も出土。金属は
ない。
5300~4200年前 杭州の西北で稲作文化が繁栄
を誇った。良渚遺跡という。そこにある小山は じつは
東西670m・南北450m・高さ8mという人工の基
壇であった。その上に神殿・王の家などがあったのだ。
そんなことができるほど栄えていたのです。玉宗・玉壁
・玉鉞など玉文化が特徴で、玉石を求めて黄河のほとり
に交易所を作った。それが夏の国となった。
★最初の渡来
学界の定説ではこうなっています。
「九州での水田稲作は2400年前から。韓国では3000 年前から始まっている。残された土器・青銅器が同じ物なの で、稲作民は朝鮮半島から九州に来たといえる」
学校の教科書にもそう書いてあります。
わたしは「学者たちは間違っている」と、ずっと思っていま した。
「華北では稲はできない。稲作民がいたのははるか南の上海
あたり。南の民が何で北の朝鮮半島から来るの? おかしい
じゃない」と。
華北に稲がない以上、稲の民は黒潮に乗って直接来たと思っ
ています。
華南から黒潮に乗ってくれば、最初に九州にぶつかる。だか
ら「九州に上陸、暫くして朝鮮南部にも」が正しい。その差
は歴史的には同時といっていいくらいかもしれませんが。
ですから韓国の南部海岸にいた馬韓・弁韓の人々は倭人と同
じ、長江からきた人たちです。ちょうど川の両岸に住んだよ
うなものです。両方に住まない方がむしろおかしい。もっと
も半島内陸の人は北方系の人です。
この私の信念を裏付ける研究が近年続々と出てきました。
*「4200年前の寒冷化・旱魃で黄河文明は危機に直面し
南への大移動が始まった。金属を持たない長江文明は彼ら
に敗れた。稲作文明の担い手、倭族・苗族は南西山岳部や
日本朝鮮に逃れた。」安田教授
*「土器の年代判定で、菜畑遺跡は3000年から3400
年前と判明」暦史民俗博物館の教授たちの新説。
この研究により日本での稲作は韓国より古いか、ほぼ同時
に始まったとなりました。
●次は来かたです。
私は江南から直接来たと思っています。
上海と九州の間は漁船で1週間あれば着きます。NHKのテ
レビ「日本人遥かな旅」のなかで、上海の漁民が「日本へは
黒潮に巻き込まれて、7回も行った」といっています。
唐の時代には3日で、昭和19年3月には大潮に乗って20
時間で来たとの記録もあります。
だから、ひょうたんの水とかまどがあれば、安全に日本まで
来ることが出来るのです。
遣唐使の遭難記録や鑑真が6回目の渡海でやっと成功したな
どの話から、直接の渡海は大変難しいとの印象があるが、そ
んなことはありません。これらは時期・航路の選択を誤った
ためです。「朝鮮半島沿岸航路のほうが危険で、遭難率3割
華南直行航路は遭難率1割以下」との研究もあります。
北に稲作がもたらされ、それから日本にきたという証拠はま
ったくありません。学者たちは「中国文明は必ず朝鮮半島を
通ってやってくる」と盲信しています。ですから朝鮮半島と
日本に同じ土器があると、それだけで朝鮮から日本にきたと
結論付けてしまうのです。証拠もなしに言ってよいなら、
「同じ土器があるから、日本から朝鮮に行った」といっても
よいことになります。
●そしてとうとう決定的な証拠が発見されました。
*「温帯性ジャポニカのタイプはaからhまで8種類ある。
日本にあるのはaとb。比較的初期のタイプだけが来たこと
になる。朝鮮にはaだけで、bはない。だからbを持って日
本に来た人々は江南から直接来たのだ」佐藤教授
これで稲作朝鮮渡来説は完全に否定されました。
「稲の民は3千年前に江南から海を渡ってきた」が結論。
最初の弥生人は金属を持っていませんでした。これは良渚国
家の民と同じです。私としては「4200年前良渚国家が滅
亡したとき、その遺民が逃げてきたのが日本の稲作の始めで
ある」としたいのですが。(少し年代が合いません。研究が
進めばあうようになるでしょう)
★渡来の波
このように中国で稲作民の国家が滅びるとき、その遺民が日
本にやってきます。
●次の渡来はBC473年、呉が越に破れ滅びたときです。
約2500年前。このときの人々が弥生人の中心のよう
です。卑弥呼の使いが、魏の皇帝に「我々は呉の太伯の
子孫だ」といっています。
「呉越同舟」の呉です。呉も越も倭人の国ですが、
江南の覇を争い、とても仲が悪かった。
「臥薪嘗胆」 越の王様は呉に負けた屈辱を忘れな
いように、薪の上で眠り、苦い肝を食べた。
●次の波。BC334年に越滅亡、2300年前。
越は大いに栄え、どんどん北まで進出、山東半島に都を
置くまでになりました。が、楚に本拠地の江南を攻めら
れ、滅びました。山口県の土井が浜に弥生人の墓地があ
ります。今は博物館となり、一般公開されています。こ
こには数百体の遺骨が埋められています。その頭はみな
西北の山東半島の方を向いています。DNA判定で、山
東省臨施の墓の遺骨と同じ人々とわかりました。越が滅
びたとき、山東半島から逃げてきた人たちだったのです
土井が浜のまわりに住む人は呉の子孫たちです。迫害さ
れたのでしょう、かれらはまだ稲作民が住んでいなかっ
た北陸に移りました。これが越の国です。このころは
「コシノクニ」ではなく、[wo]ノクニと呼ばれて
いたはずです。むかし「越」は「wo」と発音し、
「倭」の古音と同じ発音です。いまでも「越智」さん
は「オチ」さんですね。
おなじ「wo」の民を越と書いたり、倭と書いたりして
いたのです。(3月号に続く) 平成22年1月作成](vimgtext153.gif) |
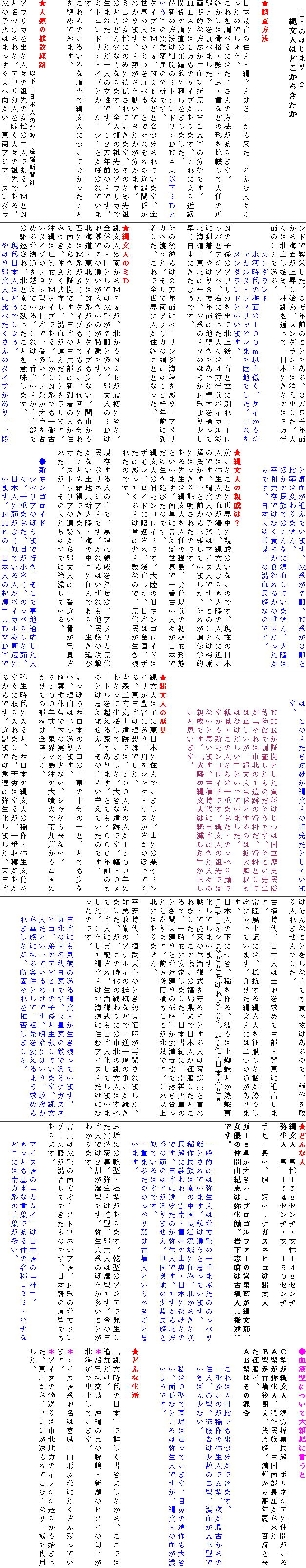 |
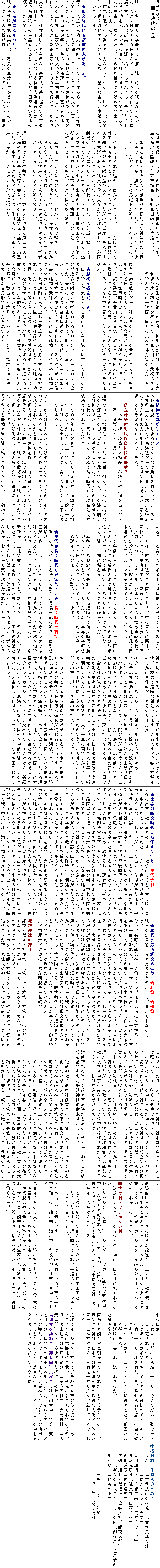 (注)「怨霊をたずねて 鎌倉編」 |
★ ものがたりの証明 ★ 謎の神サルタヒコ 第2回 |
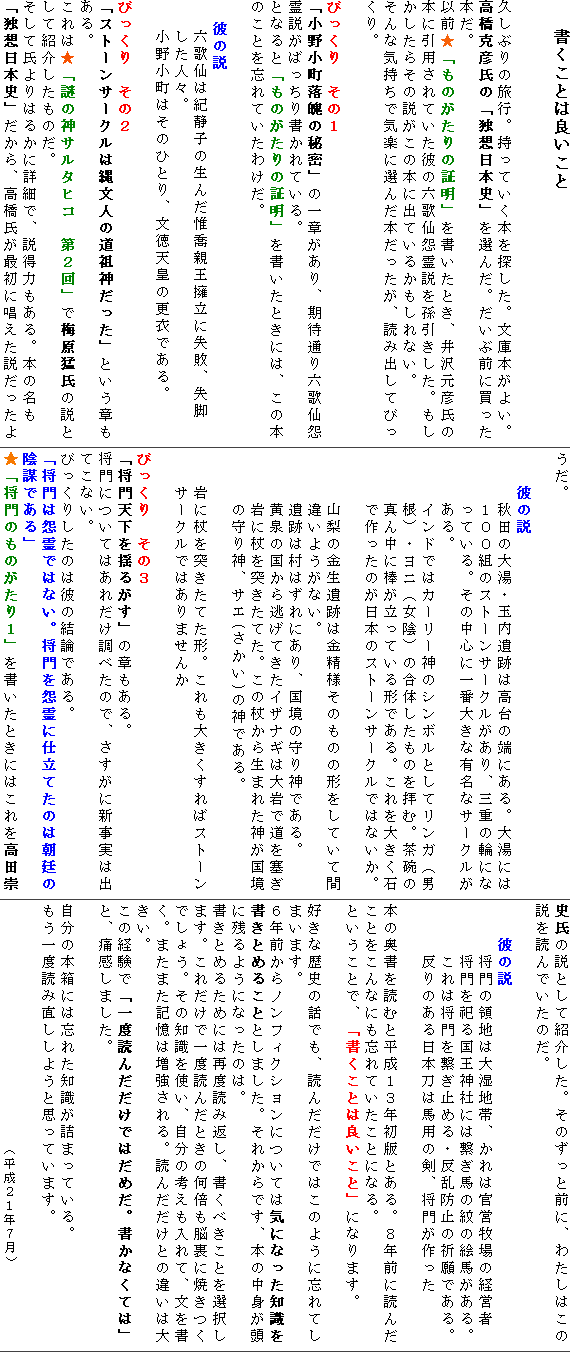 |
| ★ 将門のものがたり その1 |
|
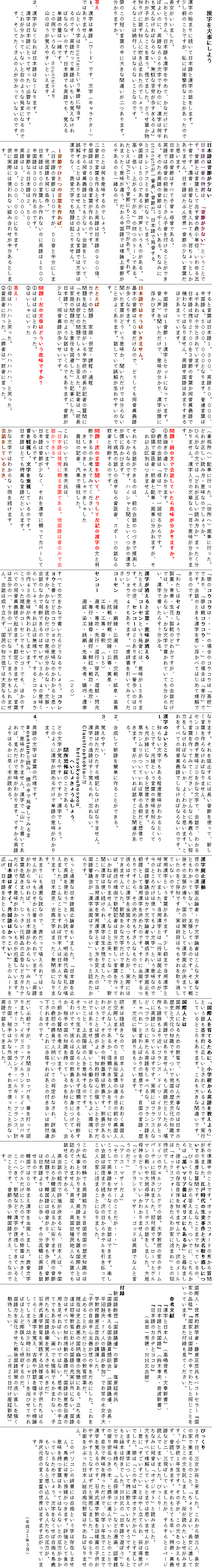 |
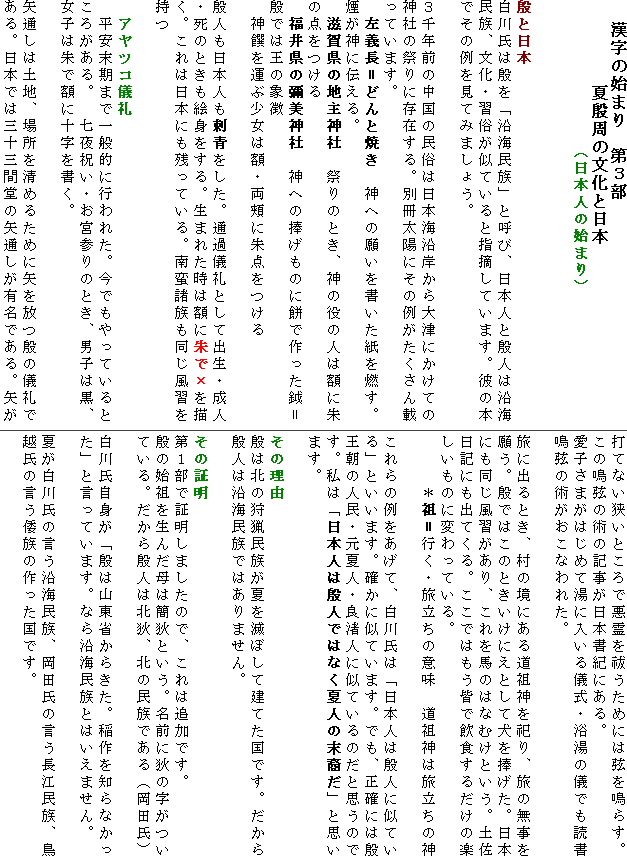 |
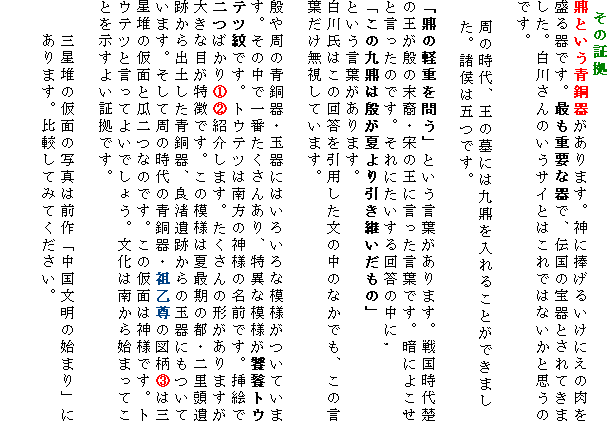 |
![殷人は。北からきた戦いに強いだけの野蛮人です。文化など持っていなかったのです。少数支配民族として君臨していただけで、人も文化も夏のすべてを引き継いでいるのです。だから文化的には夏と殷の区別がつかないのです。
区別がつかないなら、どちらでもいいではないかと思われるでしょうが、大いに違う。殷人により夏の文化は変質してしまったのです。
夏と殷の違い
私が注目したのは生贄のあり方です。
神にささげる生贄の風習は、夏・殷どちらにもありました。
殷では「今度の祭りで神は何人の生贄を欲しいか」を 占った甲骨がたくさんあります。十人、五十人、は当 たり前、一度に三百人を殺した例もあります。王の墓 からは三千人のいけにえの遺体が出てきました。首と 胴体は別々なところに埋めてあった。
生け贄としてたくさんの人を必要とするため、殷は人狩りを盛んに行いました。遊牧民のキョウ人が主な犠牲者です。
確かに夏でもいけにえとして、人を殺しています。
夏の遺跡はとても少ないので、稲作民族の遺跡から類 推するしかありません。
4500年前の宝敦遺跡、ここの神殿の基盤に人がいけにえとして埋められています。でも一人です。ほかのたくさんの遺跡からもいけにえは出土していますが、すべて一人です。
「伏」この字は建物を守るため、人と犬を犠牲として埋めたことを意味する(白川氏)
後漢のころ、雲南省填湖のほとりに填国がありました。倭族の国です。「填王乃印」という金印も出ています。ちょうど卑弥呼のころです。
そこから青銅製の貯貝器が出土しています。そのころ子安貝は宝物でした。この宝石箱の蓋を土台に、ある場面が作像されています。
女王が宮殿の前でかごに乗っている。人がいて、動物がいる。1本の柱が立っている。そこに若い女性が後ろ手でつながれている。
これは女王就任の儀式を記念したものだと思います。縛られた女性はいけにえとして神に捧げられます。女王の呪力を増すために殺されるのです。この人は女王の位を争うくらいの尊い人だと思います。そのくらいの人でなければいけにえとなる資格がないのです。
大事なものを神にささげる。これは西洋でも同じです。旧約聖書にアブラハムが息子イサクを神にささげる話があります。聖書では最後に神がその気持ちだけでよいといったので、息子は助かります。この話の原型では息子は本当にいけにえとなったはずです。
日本にも人柱を立てた話は残っています。やはり犠牲者は高位の人一人です。
王は神と話すことのできる人。災害が起きたときそれを直す責任があります。息子を、自分を犠牲にしてでも神の機嫌を直さなければなりません。一番大事なものを神にささげるのです。
実は殷にも同じような話があります。
ひでりのとき 殷の初代の王・湯王は髪を切り、爪を切って、薪の上に座り、神に祈りました。薪に火をつけようとしたとき、雨が降り出しました。
殷でも最初のころは夏のいけにえの意義を継承していたのです。でも我が身はかわいい。異族をいけにえにするようになりました。見知らぬ人なら何人殺しても気になりません。神に気に入られるようたくさんの人をいけにえにしました。質より量への転換です。夏と殷とでは生け贄の意義がまったく逆なのです。
これが、私が「倭人は殷でなく、夏の親戚」にこだわる理由なのです。
お酒の飲み方
神にお願いするとき、「いけにえの肉と酒」は欠かせません。
稲作民族は春の田植え祭り・秋の収穫祭・災害時の神への願いのときだけ神ともに酒を飲んだのだと思います。普段は酒などもってのほか、働くのみです。殷はここでも変質しました。支配階級は酒を飲めば神が喜ぶと、年中飲むようになりました。酒池肉林の世界です。殷の最後の王桀は傾国の美女をかたわらに、池に酒を入れ林の枝に肉を掛けて、裸の男女たちと遊びほうけたと書かれています。
西方から来た質実な周は、殷のこうした風習を嫌いました。そこにあった思想も嫌いました。ただ物質面の文化・技術を継承したのです。和魂洋才の世界です。青銅器にトウテツ紋は残っても、刺青は消えました。こうして中国文化から稲作民族の風習は消えたのです。中国の最初の史書でも南の野蛮人は刺青をするとさげすんでいます。中国文明の創始者・倭族はすでに蔑視の対象となっているのです。
日本人の祖先は長江の稲作民族だった
日本人の定義を日本にすむ稲作民族とすると、弥生人から始まります。
弥生人は長江から来ました。上海から九州まで、船で1週間前後でつきます。その辺の漁民には嵐などで日本に流された経験をもつ人がたくさんいるそうです。(NHKのVTR) 弥生人はそのようにして3000年以上前に江南から日本に来、住みついた人々です。その後も何度も来日の大きな波がありました。
定説では弥生時代の始まりは2400年前です。歴史 民俗博物館の学者は、それを千年も遡る説を出しまし た。朝鮮半島の稲作は、3000年前からとなってい ます。私は「前から長江から来る人々はまず九州に住 むはずだ。韓国より日本のほうが早いはずだ」と思っ ていました。
BC473年呉の国が越に滅ぼされました。滅亡のときたくさんの人が南に西に、そして日本に、逃げてきました。「金印をもらった奴国の使者も卑弥呼の使者も『われわれは呉の太伯の末裔』と名乗った」と晋書にあります。ずいぶんたくさんの人が来たのでしょう。
越はBC334年楚に滅ぼされました。越は最後のころ都を山東半島に移しています。
山口県の土井が浜に弥生人の墓があります。埋められた人はすべて西北、山東半島のほうを見ています。そこが故郷だったのです。越の人々だったのでしょう。越前・越後にも越の人が住み着いたのかもしれません。
秦の始皇帝は戦争や大土木工事でたくさんの人を殺しました。確か人口は4割以下となったはずです。徐族のリーダーで方士の徐福は一族の安全を図るため、始皇帝をだまして、たくさんの人を連れて日本にきました。2200年前のことです。中国徐福会の会長はその数6万人と推定している。話半分としても3万人もの人がきています。徐族は倭族で、徐州中心に住んでいました。佐賀・熊野・富士を中心に徐福伝説が残っています。 「徐福伝説」 羽田武栄ほか
次は三国志の時代、「280年晋に攻められ、呉は最後のときを迎えた。
海軍はまだ健在で2万の兵が海上にあった。呉の都・南京が開城したとき、城の中は無人であり、前夜までいた海軍の船は一隻残らず姿を消していた。どこへ行ったか誰も知らない。」 これは三国志呉史の記事です。
これを踏まえて、竹田昌暉氏は「日本書記の謎」でこう説きます。
天孫降臨とは海アマから呉王・孫氏が九州・日向に来たことを示す言葉である。そののち河内へ進出した。これが神武東遷である。三角縁神獣鏡は河内で彼らの工人が作ったものだ。
傍線部分は鏡に詳しい中国の学者が唱え、一番有力な説です。
径20センチを越える鏡は魏にはありません。呉にだけあります。
このように、長江の稲作民族はたくさん日本に来ています。南方に逃げた倭族との関連は残っているでしょうか
弥生人と南方民族
苗族は江漢平原・洞庭湖あたりで栄えていましたが、漢民族に破れ雲南・貴州に逃れました。かれらは黄帝の子孫に敗れた伝説を持っています。
炎帝・黄帝がシユウを滅ぼした。シユウは良渚国の王 様である。
梅原猛氏「南方神話と古代の日本」角川選書
苗ミャオ族は今でも祭りのとき鳥の衣服を着、冠をかぶって踊る。銀の冠には鳥と太陽が彫金されている。 (カボト遺跡の玉器と同じ図柄です)
填王国の青銅器の絵にも船をこぐ羽人が書かれている。
鳥取県淀江町の角田遺跡の土器には船をこぐ羽人が書かれている。
継体天皇のお墓・ 今城塚古墳の多くの埴輪に船の絵が書かれ、舳先に鳥がとまっている。
「長江文明の謎」安田喜憲 青春出版
「古代中国と倭族」 鳥越憲三郎 中公新書
奈良県田原本町には唐古・鍵遺跡博物館があります。そこにそのころの生活の想像画が飾られています。その中で鳥の羽で身を飾った巫女が踊っています。ここでも羽人が描かれた土器が出土しているのです。
「日本王権神話と中国南方神話」の中で諏訪春雄氏は弥生人と南方民族と似ている点を列挙しています
漁労・高床式建築・土器・文身・断髪・貫頭衣・絹織 物・蛇竜信仰・持衰・双系親族・ヒメヒコ制・歌垣・ 妻訪い婚・もがりの風習・稲・ひょうたん・えごま・ 大麦・そば
南方民族とは中国貴州から雲南の山々に住む少数民族 です。苗ミャオ族・トン族・ナシ族などがあります。
諏訪氏は日本の神話が南方民族の神話とよく似ていることを、たくさんの神話で説明しています。
イザナギ・イザナミの国生み神話は西遊記に出てくる三官伝説とほとんど同じである。トン族には兄妹神の結婚として半分くらい同じ話がある。
黄泉ヨミノ国神話・アマテラス・大国主(難題婿話)・サルタヒコ(道案内の神)神話などとよく似た話が南方民族の間に伝わっている。
殷の時代から続く儺の祭り(打鬼)が残っている。日本の節分と同じ。
すべての神話が南方系だと言っているわけではありません。わたしは古墳時代後半に加耶王の人々が来日し、支配者となったと思っています。ですから北方系の神話もあるのです。ただ少ない。
終わりに
漢字の話第3部のはずが、話の続きで日本人の起源にまで入ってしまいました。まあいいとしましょう。
★[堀内弘之・歴史探求の部屋Ⅰ]の
「祭りのものがたり」を補追しました。
ぜひお読みください。
以前「祭りのものがたり」で「神輿の祭りは神
様を脅すための祭りだ」と書きました。まった
くの推測で書いたのですが、よい事例が見つか
りました。
●私の推測は正しかったのです。
(平成20年12月1日)](vimgtext114.gif) 「祭りのものがたり」へ 「祭りのものがたり 追補」へ |
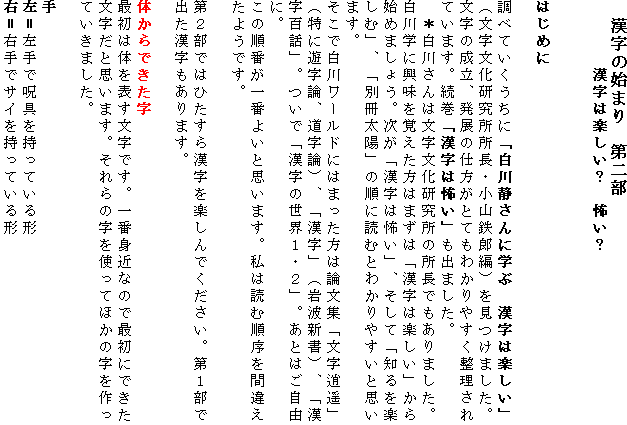 |
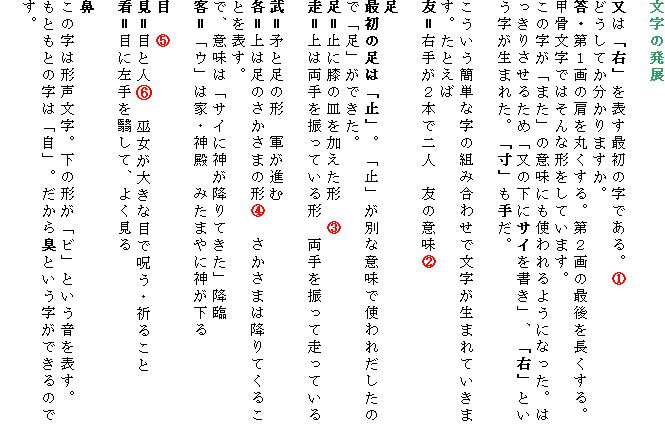 |
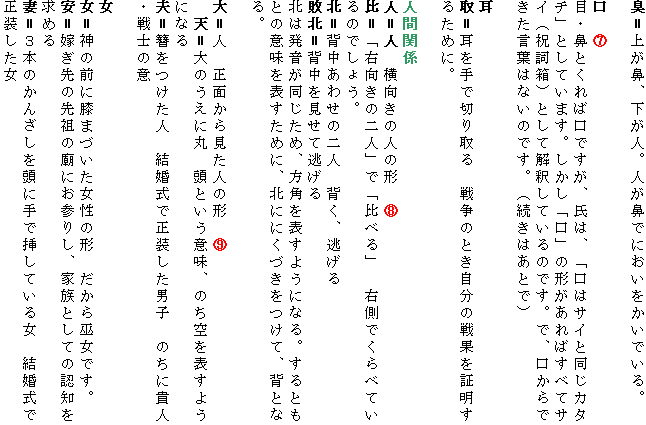 |
||||||||
 |
||||
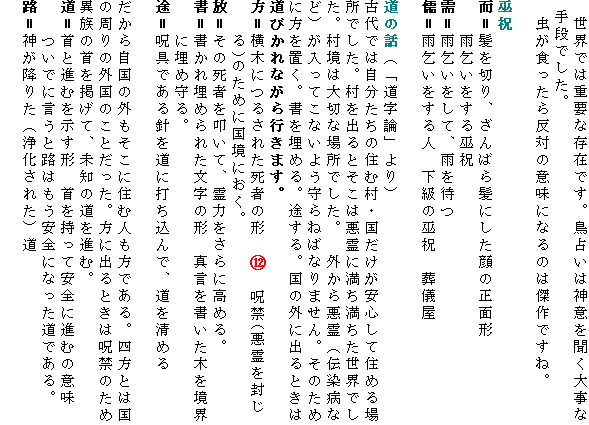 |
||||
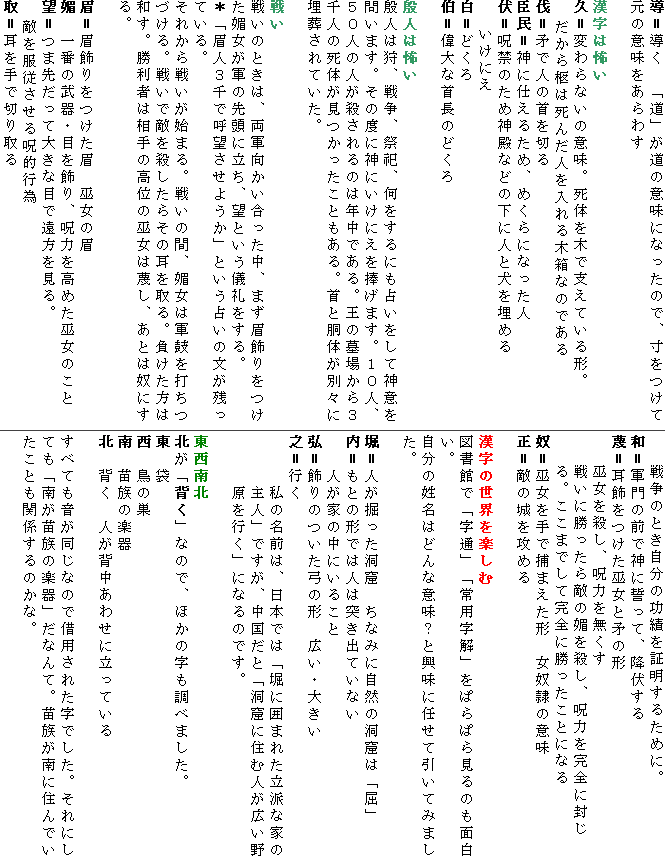 |
||||
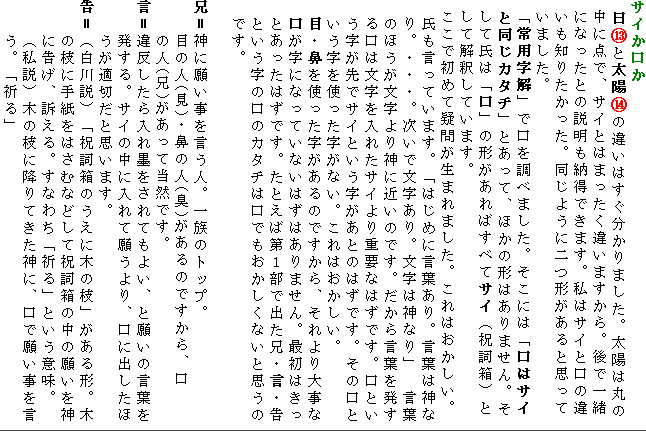 |
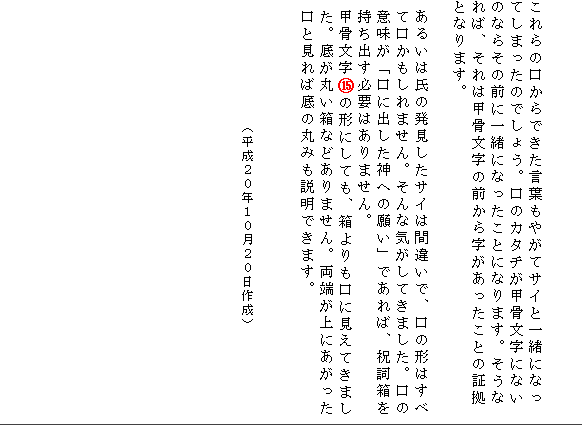 |
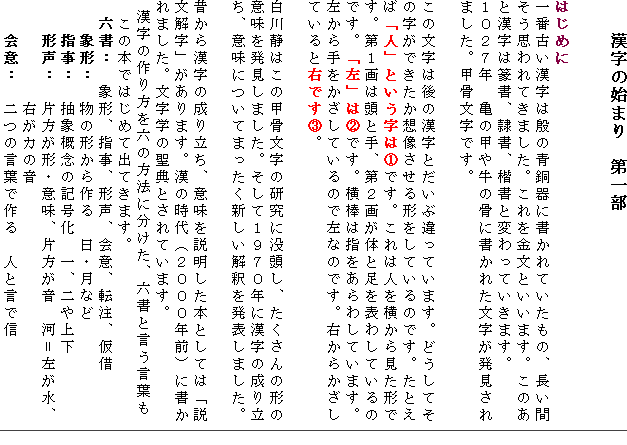 |
|||||||||||||
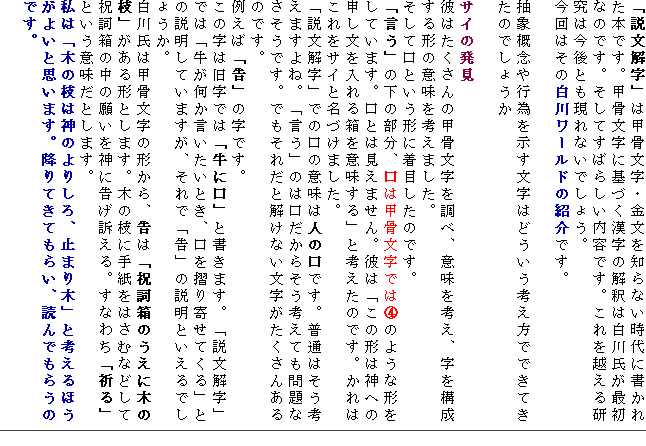 |
|||||||||||||
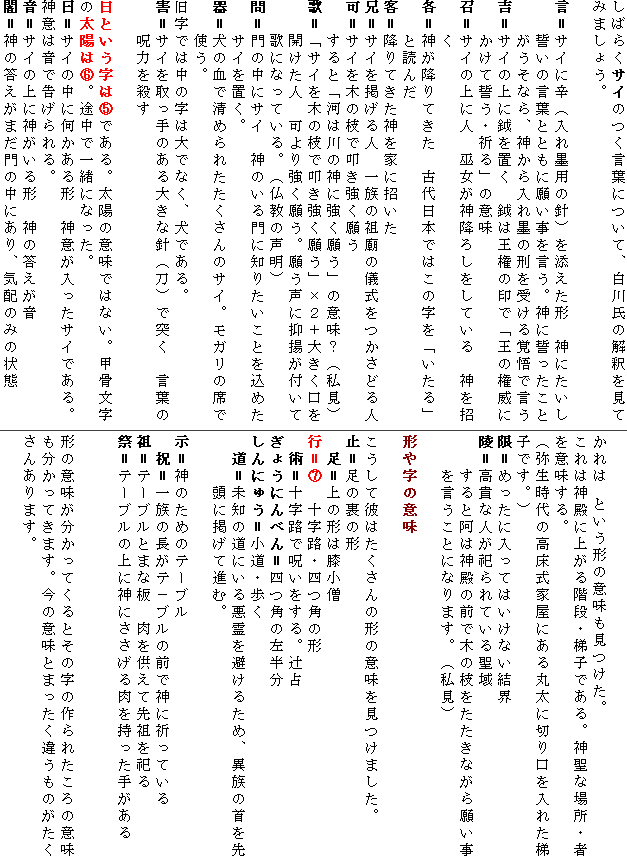 |
|||||||||||||
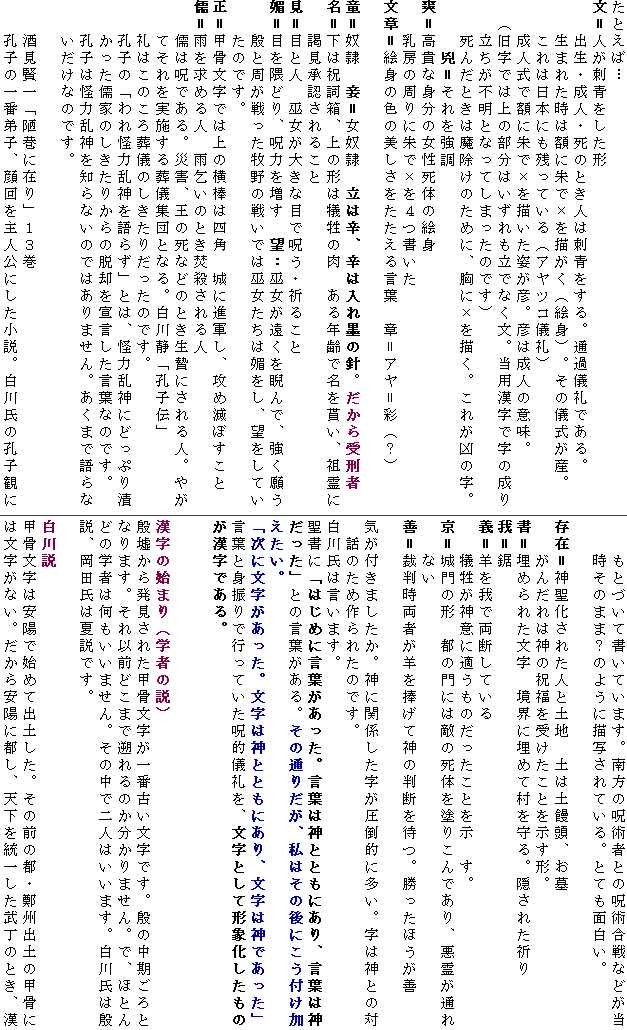 |
|||||||||||||
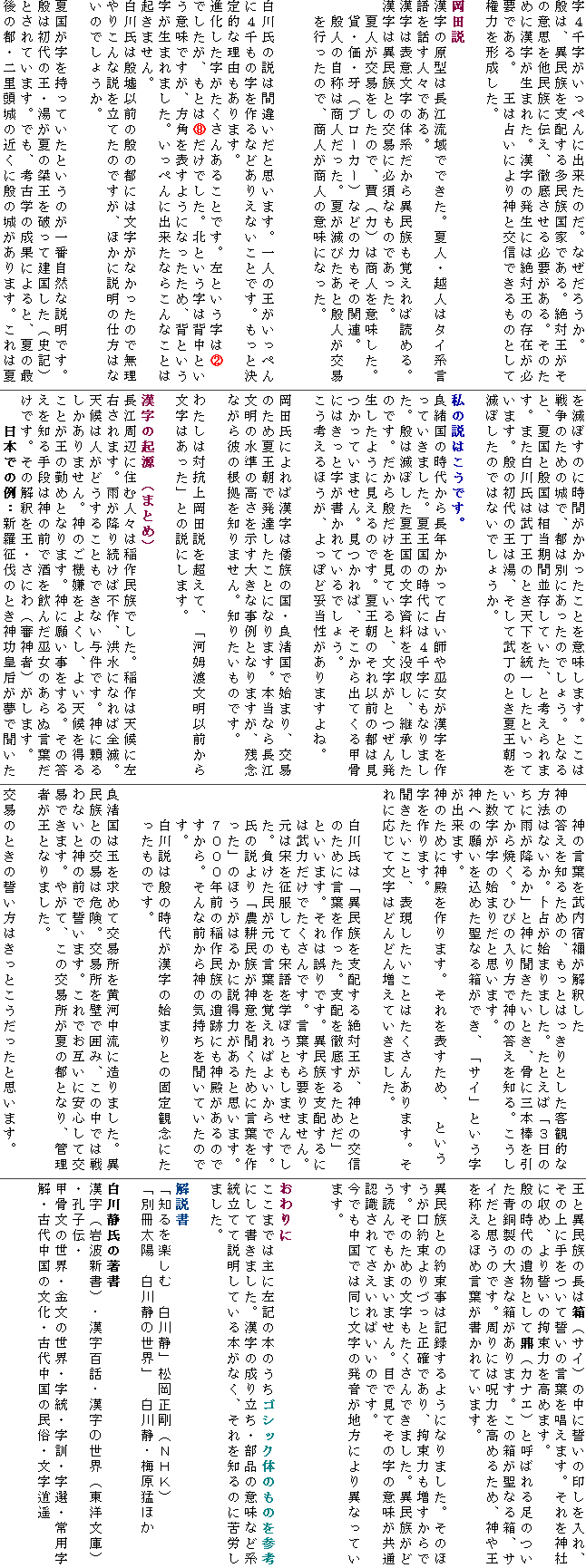 |
|||||||||||||
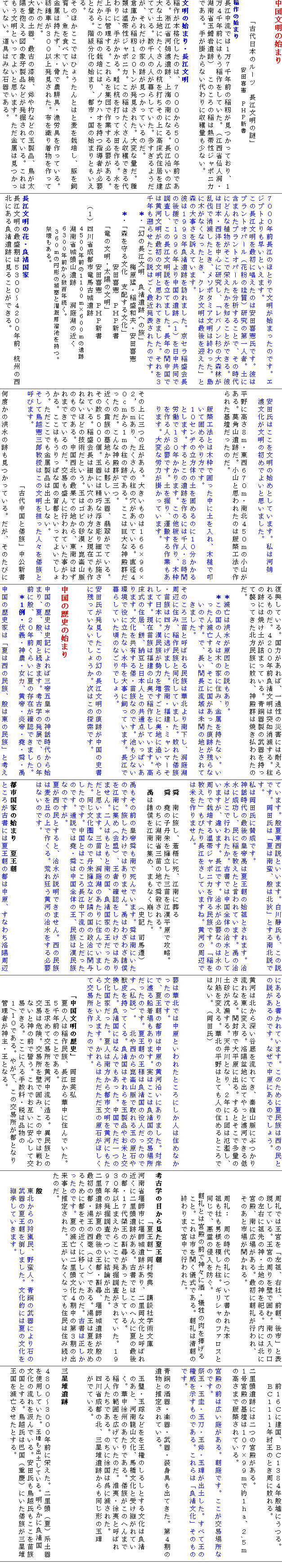 |
 中国歴史博物館名品展・三星推出土 凸目銅面具 (祖乙尊の図柄に戻る) |
 中国歴史博物館名品展 三星推出土・銅人頭 |
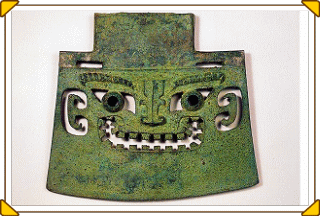 中国歴史博物館名品展・蘇阜屯出土 銅銊(どうえつ) |
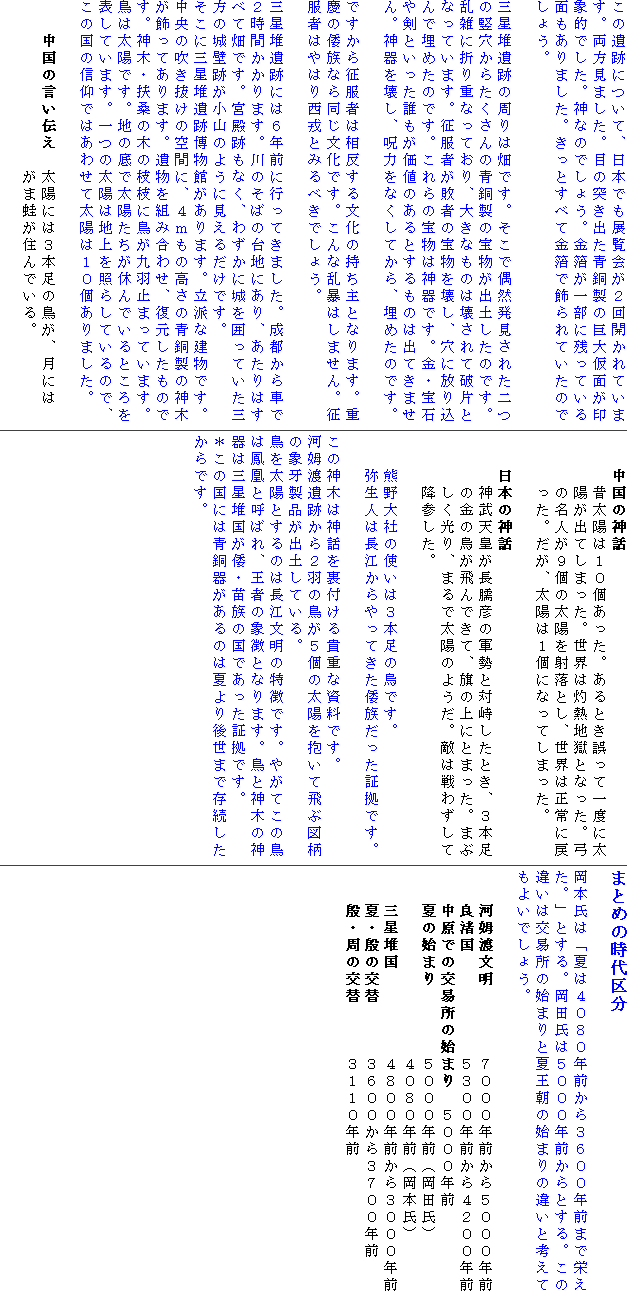 |