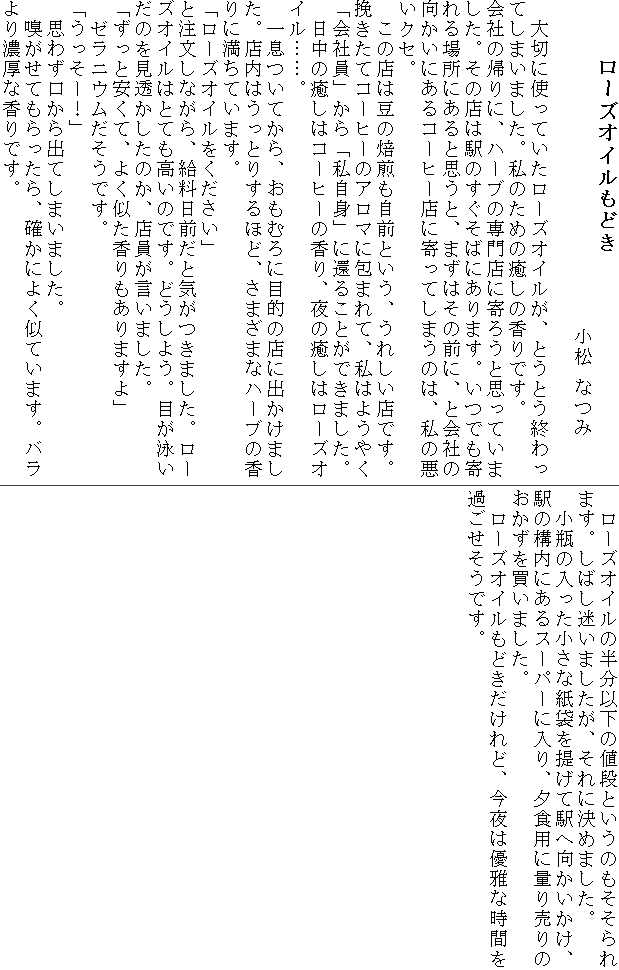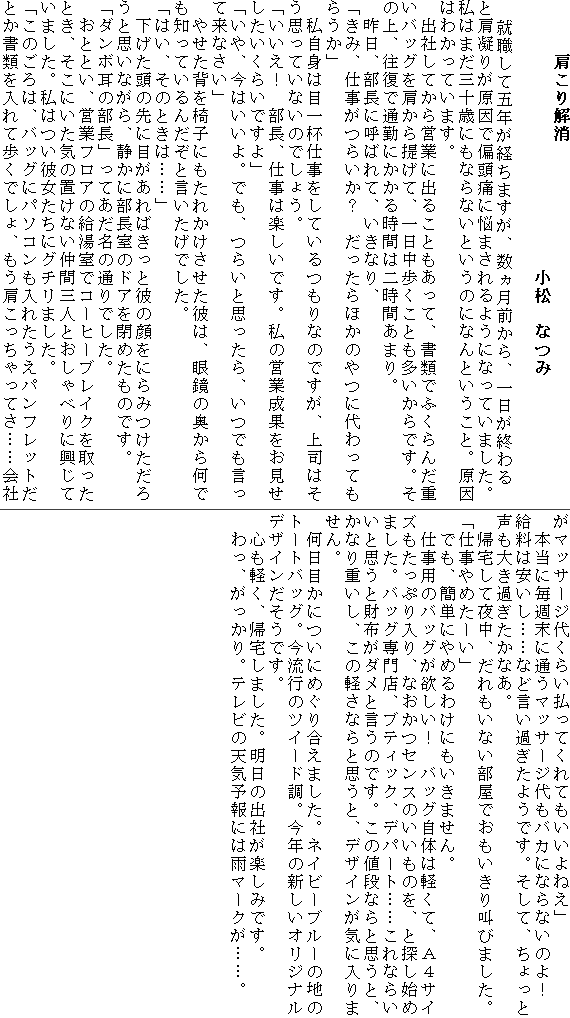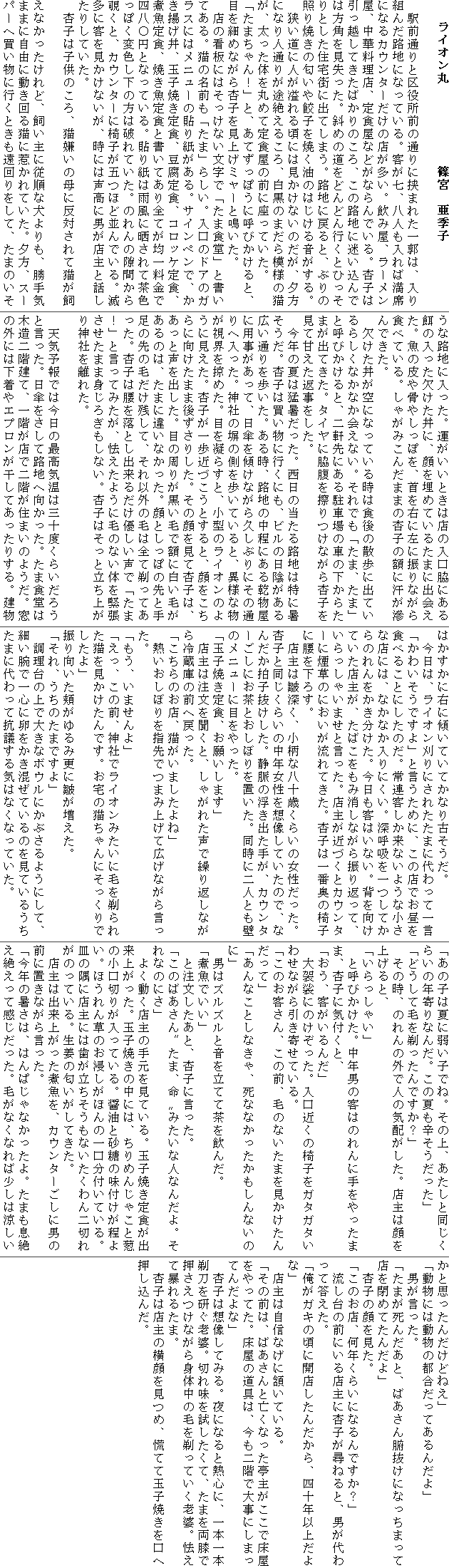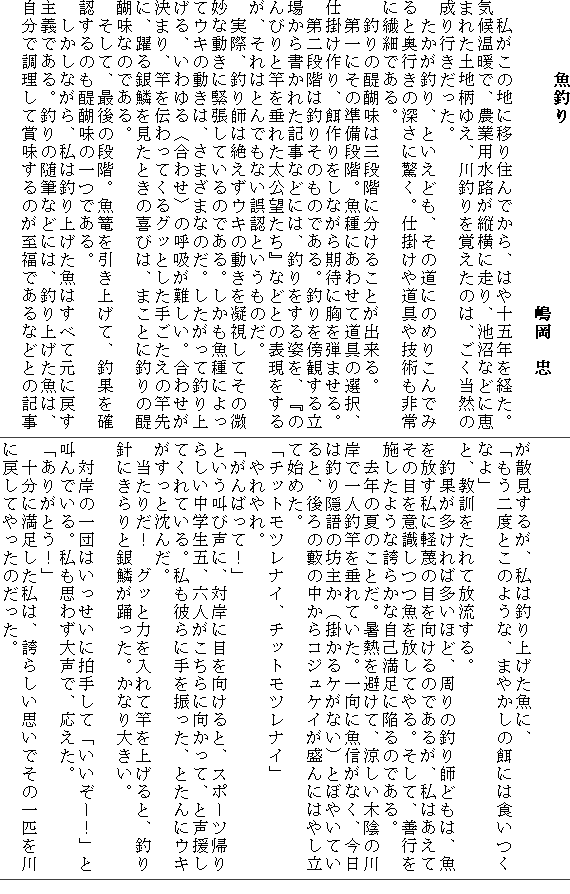|
�@�@�@�@�@�`�]�[���������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�x�� �O�V
�`�]�[����v�w����t�����q�s�ɂ���䂪�Ƃɔ��܂邱�ƂƂȂ����B
���͂P�P�N�O�A�R���������ă��[���b�p���͌��ł��ĉ�������Ƃ�����B
�x�������ł͔ނɂ����ւ��b�ɂȂ����B����ȗ��̕t�������ŁA���͔ނ̉ƂɂQ�܂�A�ނ�͎��̉ƂɂP�܂��Ă���B
�`�]�[����͂V�U�ŁA�h�C�c�͌��̏d���B���Ă̓��[���b�p�`�����s�I�����������Ƃ�����B
��N�x�������œ��{�̈͌閼�l�킪�s��ꂽ�Ƃ��A��o�Ƃ��ďo�Ȃ����{�ɂ܂ŕ��f����Ă���B�e���ƂŁA�Â��͊�{�A���염���l���͂��߂�������̓��{�l�𐢘b���Ă���B���̂����A�ނ͂��̐l�����𗊂��ē��{�����B���x�͂W�x�ځA�S�T�Ԃ̗��B���̂����R�T�Ԃ͒m�l��K�˂ĉ��B
���̒S���͂P�U������P�X���ƂȂ����B
�Ȃɘb���Ɓu�������ȁ[�v�B�Ȃ͂P�U���ɂ͐����Ԃ̋���������A�U���܂ł͕s�݁B�P�T������P�V���͌����ٍՂŁA��������N���u�̓W����ɋl�߂Ă��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�ǂ����悤�B
����ȂƂ��ׂ̔����s�ɏZ�ޒ�������d�b���������B�����m���������͎����̉ƂŖʓ|������Ƃ����Ă��ꂽ�B�����̕v�͒P�g���C���A�y���͗p���Ȃ��Ƃ����B
��������������������ɂ��A�����āA�v�抮���B�P�U����͊��}�f�B�i�[�B�@
�O���A���̖��Ǝ������܂�B
�v�T�l�����܂�̂�����z�c������Ȃ��B�x�x�͂ӂƂ���Ƃ��玝�����ނ��Ƃ���n�܂����B
�@
�T���`�]�[�v�w�����B
�`�]�[����Ǝ��͉p��ł̉�b�ƂȂ�B���ɂƂ��ĂQ�N�܂��x�������@�K��ȗ��̉p��ł���B���̉p��͊ԈႢ���炯�����A�C�ɂ��Ă�����b���Ȃ��B�ǂ�ǂ�b���B
���uHis husband�E�E�E�v
���������B�uNot his. Her�v
�`�]�[����uI understand it. His, her no problem�v
�l�̂̊ԈႢ�Ȃǂ���C�ɂ��Ȃ��ƌ����Ă����B�����łȂ���킽���Ƃ̉�b���������Ȃ��B
���͉p���b���Ƃ��A�l�́A�����A�O�u���͈�؋C�ɂ��Ȃ��B�C�ɂ��Ă���ƕ��͂��l���˂Ȃ炸���Ԃ�������B��b�ɂȂ�Ȃ��B����炪�Ԉ���Ă��Ă��A��b�̊Ԃ������Ă���Θb�͒ʂ���B
�Ȃ܂��O�u���Ȃǎg�킸�A�P�����ׂ��ق����A�킩���Ă��炦��B
���{�l�̉p��Ɋւ��Ă���Șb������ł͂Ȃ����B
�����h���֍s�����ƁA�ؕ������ŁuTo
London�v�Ƃ�������A�ؕ����Q���o�Ă����B�������A����������Ă�����[For
London]�Ƃ�������A�ؕ����S���o�Ă����ƁB����ȂƂ��́u�����h���v�ƌ����āA�w����{���Ă�悢�̂��B����͎������[���b�p��l���Ŋo�����m�E�n�E�ł���B�����������āA�uThis one, please�v�ŏ[���B
�����ق��ɂ��m�E�n�E������B
���͍������������Ȃ��A���{��ł��Ȃ��Ȃ��������Ȃ��̂ɉp�ꂪ�܂Ƃ��ɕ�����͂����Ȃ��B������Ȃ��Ă��ڂ����ď݂��ׂĕ����A�b�̌X�������ށB
�I������炷����������B������A�b������B
�uSure.�v
�uReally?
�v
�uUnbelievable!�v
���̕ӂ������Ă����A��b�͂Ȃ����Ă����B
�@
���炭�����Ă�����������Řb���ʂ���̂��˂Ɗ��S���Ă����B
���āA���̓��̗[�H�͂���Ԃ���ԁB
�W�x�ڂ̖K���Ƃ��Ȃ�A�`�]�[����v�w�͊�p�ɔ����g���B�@
�킽���͈�T�ԑO�ɓ]��ʼnE�蒆�w�̐�����܂����B�������ĂȂ��B
���uI use folk. You use chopstick. I am
Germany. You are Japanese�v
(��)
�@
������̓h�C�c�ꂾ���Ȃ̂ʼnᒠ�̊O�B���Ȃ�������ɂ���l���ʖ�B
�����ЂƂ���B�@
���[���b�p���s�����悭���������i���B
�@�H�����I���ƁA����l�̓h�C�c���b�W���J���āA������̂�����B
�����u�O�[�e���^�[�O�i�����́j�v�Ƃ��A�����u�A�E�t���B�[�_�[�Y�C�[���i���悤�Ȃ�j�v�B�@
�u���͂悤�̓O�[�e�������Q���v
�u����ɂ��͂́A�O�[�e���^�[�O�v�Ƃ��ƁA
�u�O�[�e���@�A�[�x���g�i���ӂ́j�v
�u�O�[�e�@�i�n�g�i���₷�݂Ȃ����j�v�ƕԂ��Ă���B
�����̂Ȃ��h�C�c��̗��K�����A��������ɂȂ��Ƃ��낪�����B���������A�悭�C�����B�@
�P�V���̌v��F
���A�Ɠ��Ǝ������\�h�K��A�s���ό��A��̓`�]�[����ʂȐl�Ɖ�H�B
�����Ƒ��͎l�l����Ă����B�����̒���(���Q)�͂�����ԂƂ̂��ƁB������������̒����i���R�j�́u�ꏏ�ɕ�����v�ƁA�����̉ƂɎ��]�Ԃōs���Ă��܂����B�@
�c�����l�X�͂������k�̂��ƍs���J�n�B
�����Ƒ��Ƒ��ǂ��S�l�̓A���f���Z���q��ցB
�Ɠ��͌����فA�`�]�[����Ǝ��͎O���̉^�]�ō������j���������قցB
���̔����ق͌�����D�A�l���̖͌^�������W������Ă���A�O���l�ɂ��������₷���ʔ��������悤�ŁA��������ʐ^���Ƃ��Ă����B
�A��ɉƓ��̂�������قɊ�����B�O�l�ƈꏏ�Ȃ̂ʼnƓ��̒��Ԃ͂т�����A���тŁA�W��������܂˂Ő������Ă��ꂽ�B
�P�W���̌v��F
�O�g���Ǝ��̖�����X�ƍ������āA���q�ό��B��͎O�g��ɔ��܂�B
�O�g���͂킽���̂P�O�N���̉�Ђ̌�y�B���������A��㐶�܂�̗V�ѐl�ŃO�����B�P�A�W�߂Ȃ���h�J�̐搶�B���Q��͗��s�E���������ƕ����ǂ��ւł��H�ׂɂ����B�����Ԏ��̂͂T�A�U��B�݂Ȏ����A����������߂͌y���B��Ԃ̓o�X�̌��ɃI�[�g�o�C���Ԃ����A�r��܂������Ƃ��ȁB�킽���͂ނ���ޏ��ƋC�������N�ɂR�A�S�܂�ɂ����B�O�g�Ƃɂ͖�����l�B�ޏ��������s���Ɓu��������A���A��Ȃ����v�Ƃ����B
�O�g�v�w�͂U�N�O�`�]�[����Ɖ���Ă���B
���͂Q�N�O���ƃh�C�c�𗷍s���A�`�]�[����v�w�Ɛe�����Ȃ��Ă���B
�O�g���Ɩ��Ɗ��q�ŗ��������B
������͂��Ȃ��B�����Ǝh�J�̎d���Ȃ̂��낤�B
���z�̋��t�̓X�u�r�c�ہv�Œ��H�B�����̂��炷�Â�����H�A�v���Ԃ�ŁA���܂������B�`�]�[��������߂ĂƂ̂��ƁB��낱��ł����B
�O�g���̎Ԃł�������B
�`�]�[����͂R�V�N�O�Ɍ����ێ��ɍs�������Ƃ����B�U�N�O�ē��������ɂ͌�����Ȃ������B���x�͑��v�A���@�@���@���ł���B�ێ��Ƃ����Ă��R�̎Ζʂ̐Βi�ɑۂ������Ă��邾���B�X�ƌÂт���������镗��́A��сA���тƂ����Ă����s�̑ێ��Ƃ͂����Ԋ������Ⴄ�B�u���̎��������������̂��v�Ƃ����`�]�[����̓��{�l�Ԃ�Ɋ��S�B���Ƃ͒��J���A�啧�A�K�ٓV�Ŋό��I���B
�˒˂̎O�g���̉ƂɌ������Ԃ̒��ŁA
���u������͂����A���Ă���́v
�O�g�u��t�ŃS���t�����Ă���v
���[�I�@�Ƃɂ����Ȃ��́B���ꎝ���ŊO�H�A�Ƃ��Ă���̂ŊԂɍ����悢�����̂��Ƃ����ǁB����ɂ��Ă��O���l�����҂��Ă����ăS���t�Ƃ͂ˁ[�B�t�Ɍ�������Ȏ��悭���҂������̂��B
�ƂɋA�����Ƃ���ʼn�����d�b�B
�u���܃A�N�A���C���ɏ��Ƃ���B���Ȃ��͂ǂ��H�v
�u�����Ƃ���B�����A���Ă�����
�u���ƂP���Ԕ�������v
�`�]�[����v�w�͏����Q�����Ƃ����B�n��ɑD�������B
�@
�U�����Ɂ@������A��B�u�H���͂����Łv�Ƃ̂��܂��B
�u�O����Ȃ��́H�v
�u�����I�v�ƁA�߂̈ꐺ�B
�S���t�ňꏏ���������F�B�����Ă���B�H���̎菕���v���炵���B
������p�ӂ��Ă����̂����݂̍��z���߁A�ϕ��Ȃǂ��o���A���C���͓S�Ă��ŁA���̂��Ƃ��D�ݏĂ��B���̂���Ԃ���Ԃ����������A�ڂ̑O�Œ���������̂��������b���ł��āA�p�[�e�B�ɂ͍D�s���̂悤���B
�O�g�Ƃ̖����A���Ă����B�ŁA�`�]�[����ɁA
���uI have three daughter in Chiba, and one
in Totsuka.�v
�`�]�[����̓L���g���A�Ӗ����킩��Ȃ��B
���uI have two
fathers�v�킽���ƎO�g���w���B
�������A�������̑��͂҂����肾�B
�P�X���B
���˂ɍs�����B�����ɂ͈͌�̌��l�A�ؒJ�����Z��ł����B���ˎs�͈͌�������̃e�[�}�Ƃ��A�ؒJ�L�O�ق����Ă���A��ʂ̌�Ղɕ��ׂāA���łs���������肵�Ă���B�`�]�[���͂��̋L�O�ق������������̂��B
�L�O�قɂ͂����������̂͂Ȃ��������A���͂�����Ɏʐ^���Ƃ����肵�Ė������ł������B
�v�ȂƂ͂����ł��ʂ�B�ނ�͕��˂��瓌�C�����œ��c�ցB�����͑���S���̌i�F���ӏ܂���̂��B
���͂��̂��Ɖ��{��c�Y�ɏZ�ޕ��\�h�K��̗\��B
�o�o�͂X�V�̈�l��炵�����A���̘b�ł͍����̓f�C�T�[�r�X�łS���܂ŊO�o�Ƃ̂��ƁB�ōĂсA���q�ό��ƂȂ�B�����͓�K�����ʂƂ���B���E���E���E�`���V�_�ЁB�[���Ȓ뉀�̏����悩�����B
����ŎO�g���Ƃ����ʂ�A���t����������J�l�ł����B
�S���ɓc�Y�Ńo�o�Ɉ����A���@���f�������āA�A��B
���������l���Ԃł����B�����B
|

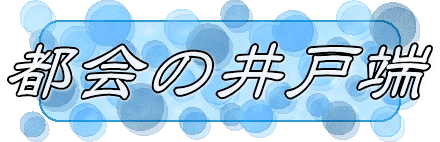
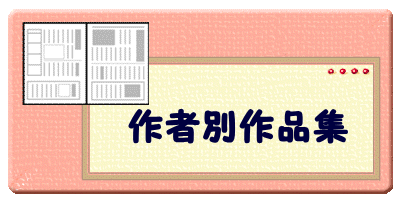

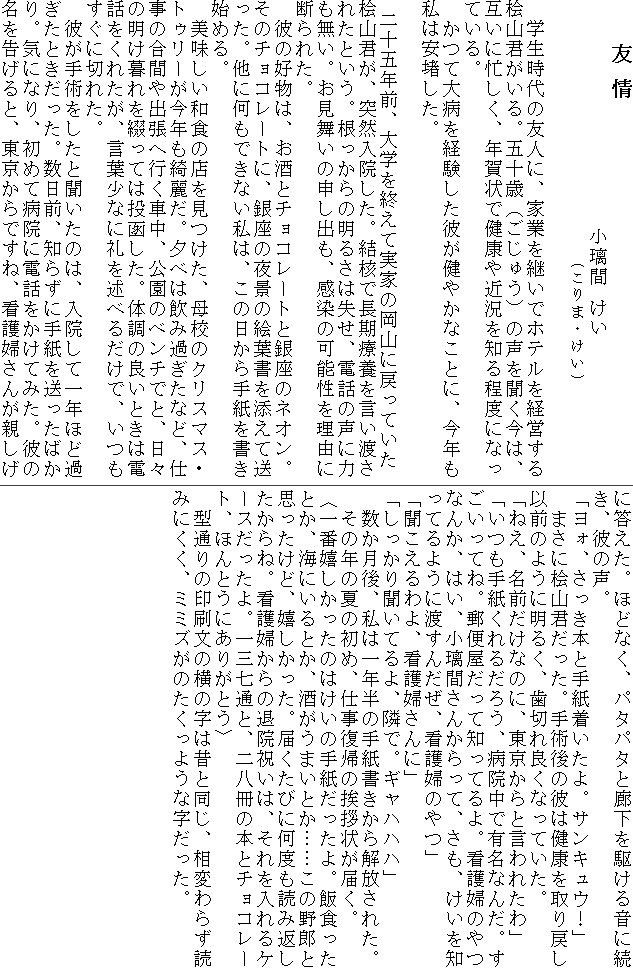
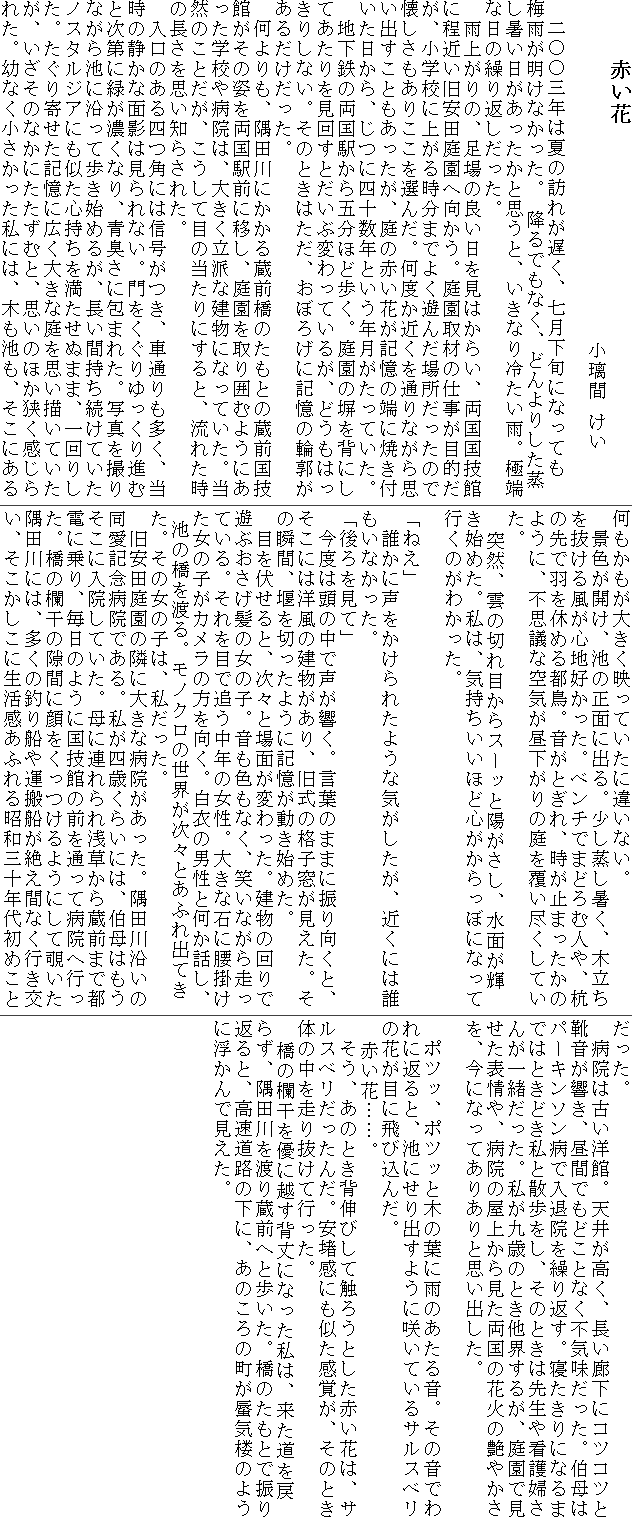
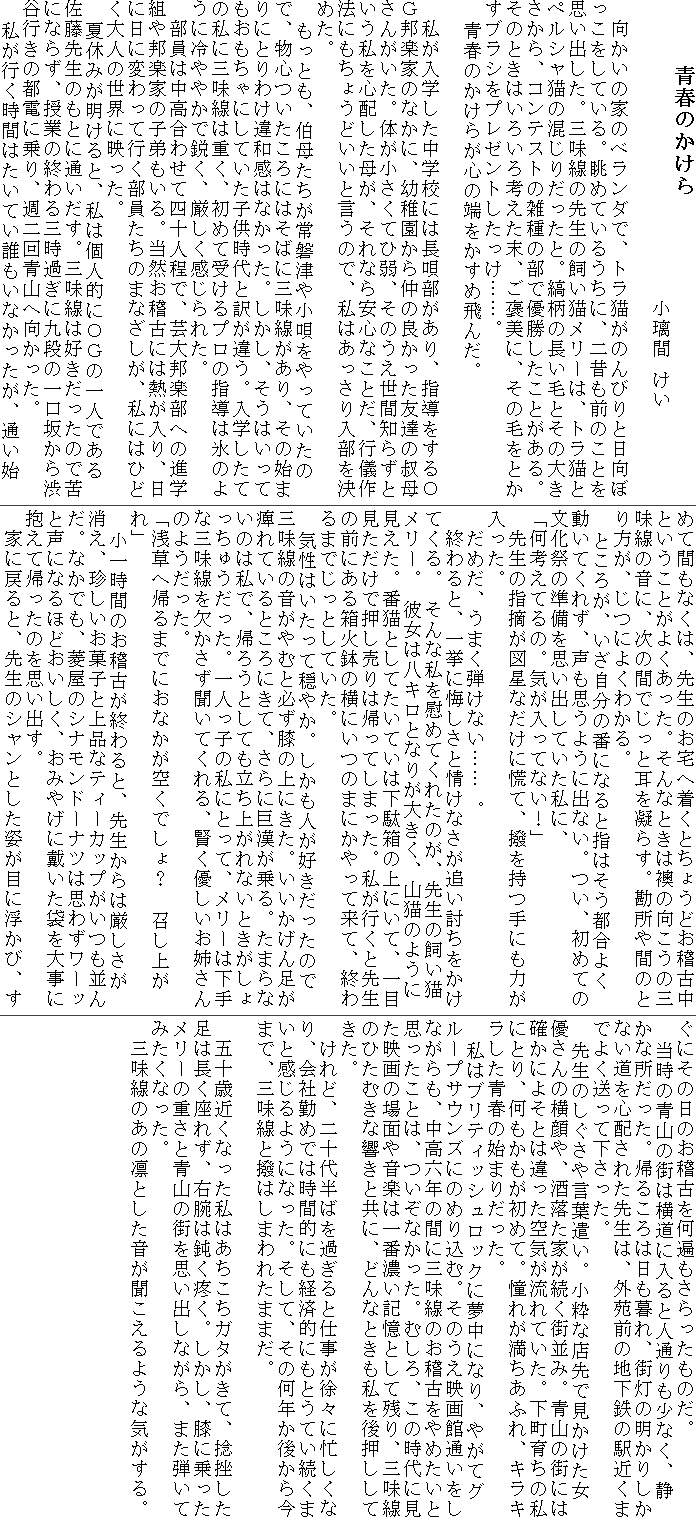
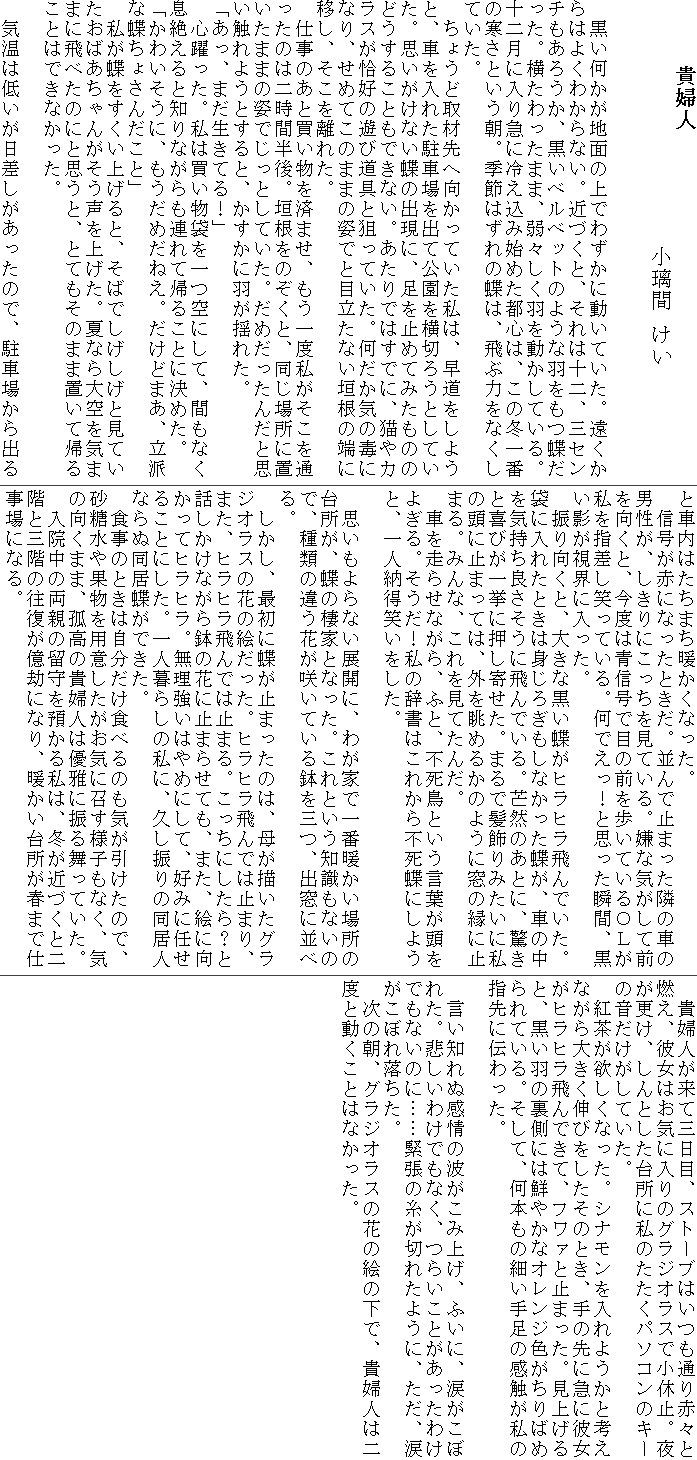

![�@
�@�@�@���̌܁E���E�� ���c�[�]
�@�Ԑ���[�ё剤������
�@�������ɂ��������v������
�@
�@�Ԃ̉����̓��͗��ʂƒm���
�@
�@���݂�炭��l�����������m�点
�@
�@�ނ����ы��̊X�p���݂Ƃ䂭
�@
�@���Ă̕v�w���q��{���H
�@
�@�ϑ卪�����݂鍠�m�b�N����
�@
�@
�@�N�̎�̔M���`��鏉���J
�@
�@�g�t����S�̂���铌����
�@
�@�܂Ԃ��Ƃ����Ԃ͂��̎��J��
�@
�@�O���Ŋ�肻�����ɉ��t�ӂ�
�@�����[����������������肵
�@
�@�T�~�����Ȃ��䂭������
�@���ǂ��ӂ̂�炬�݂߂��l����](vimgtext239.gif)
![�@�u���̓��v�����ł���@�@�@ ���c�@�[�]�@�@�@�@�@�@
�@�Îs�ɏZ��ł���F�l�����W�u���݂�v�̊��z���ƍ��킹�āA�O�d���Y�̍����Ƃ������̂�𑗂��Ă��ꂽ�B�������̂�́A���X�`�₤�ǂ�A���[�����Ȃǂɂ��̂܂ܓ���ĐH�ׂ�ƁA���e�ƌ��N�̗F�ł���B�����ƊC�̍��肪�ӂ�ɍL�������B
�@�ׂ̒��ɃX�[�p�[�̃`���V�̈ꕔ������t���Ă������B���Ƒ����ŏ����Ă���A�㌎�Z���́u���̓��v��C���킹�̂悤���B
�@���E�����E���|�ȂǍ����H�i�̓��ɐ��肳��Ă���B�Ȃ�قǏ����ł���B
�@�ǂ�����N�ɂ悭�A�ǂ��̉ƒ�ɂ�����H�i���B
�@�����@���ɑ��̐H�i�ƍ��킹�āA����������������邩�ł��낤�B�ӉZ�Ƃ����������|�ɍ��킹�āA�����ς肵�����₷�߂������Ă݂悤���Ǝv���B
�@���̓���m���āA���߂čl��������ꂽ�B
�@�@](vimgtext241.gif)
![�@ ���������w�L��@�@�@�@�@���c�@�[�]
�@�e���r�ԑg�́u�m�g�j�����R�������v�ŁA�������������̕��i���f�����B
�@���̎��A�ӂƎv���������B�V�h�w�����L��A���a��\��N����ɂ͂܂��A��������̉��䂪�������B��̂��������߂邾���ł͂Ȃ������ɁA�钆���璩�܂œ����Ă���l�����̒����т��H�ׂ��鉮����������B
�@�������тɉ����A���X�`�ɊC�ۂƗ��Ă��A�Е����̉ƒ�I�ȐH�����H�ׂ���̂��l�C�������悤���B
�@�铢�����삯������V���L�҂����ɂ����p�҂͑�������ƁA�m�l�̋L�҂ɘb�����������������́A�����������ĘA��Ă����Ă�������B
�@�\��̎��ɂ́A���������̂����߂������B�ׂ��H�n�����˂��āA��̉���ɂ����B�̈֎q���u���Ă���B���ʂȐH���ł͂Ȃ����A���C�̏o�Ă��锒�����сA���X�`�����������������̂��o���Ă���B
�@�K�v�Ȑl�̂��߂ɕ�e��Ȃɑ����āA�H������鏗���A�N��͂킩��Ȃ������ς������ɔ��𑩂˂Ă��邾�������A�������Ǝv�����B
�@�����̏o���邱�ƂŎd��������B����������������
�������̂͂��̎������߂ł������B
�@���̐V�h�w��������́A�z���ł��Ȃ����i�ł���B�����܂ŖY��Ă��������������ʂł��邪�A�H�n������Ă��鎞�̐H���̓�������������B](vimgtext240.gif)
![�@�@�@���z�̋��@�@�@�@�@�@�@���c �[�]
�@
�@���W�̃e�[�}�̈�Ɂu���v�����������B���Ȃ�ď������Ƃ����邩�Ȃ��Ǝv�����B
�@�����l���Ă���Ǝv���o�����B�k��B�ɁA�d���ŌܔN�قǏZ��ł������ɂ������Ă����B���̖k��B�s�̒��ɍD���ȋ�������B�������R(�������)���珬�q��̑O�ɔ����鏬�����ʂ肪����A���̏Z��ł����}���V���������̒ʂ�ɖʂ��Ă����B���₪����A���ׂ̗ɖ����V���Ђ�����B���炭�s���z�e���̑O���߂���ƁA���z�̋�������B
�@�^�C�����U�C�N���{�����Ђ܂�肪�������炭���ł���B���̂Ђ܂�肩�ƌ����ƁA�k��B�s�̉Ԃ��Ђ܂�肾����ł���B
�@���̋���n��ƁA���q��̓����ɏo��B�x���̎U��ɂ͂ƂĂ��悢�R�[�X�ŁA���������āA�܂��A�Ђ܂��̏��ʂ��ċA�����B�v���o�̋��ł���B
�@���{�ɂ́A�召�̂�������̋�������B�V���܋��̂悤�ȗL���Ȃ��̂���A���{���̂悤�ɗ��j������A�̂ɂȂ��Ă��鋴������B�_�Ɨp�ŁA�l����������������B�ŋ߂ł́A�C���~�l�[�V�����̔������Ⴂ�l�����ɐl�C�̂��郌�C���{�[�u���b�W�Ȃǂ��B
�@���͐l�����Ԃ��̂ł���A�����ɖ������Ă���B���̏ォ�牺�̗��������ƁB����Ƃ͈�������i�ɐS�Ȃ��ނ��Ƃ�����B
�@
�@�����ڐ���ς��ĖZ�������X����u�Y��܂��B](vimgtext238.gif)
![�@�@�O�@���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���c�@�[�]
�@�O�@���ɂ́A�~�l�����A�}�O�l�V�E�������ʐ��̔{�͂���ƌ����Ă���B
�@�O�@�Ƃ́A�O�@��t�i��C�j�̗��ł���B
�@�l�����H�̓r���ŁA���̐��̏o���˂ɏo��l�͑����B���ނƑ̂ɂ悢�������B
�@���܂��܃e���r�����Ă�����A�Ė}���A���g���������̍O�@���̈�˂̂��鎛�Ɋ�����f�����f�����B
�@�m�̘b�ɂ��ƁA�l���ɂ͋�\�����͂���C��ɂ�����ƌ����B�S���ł͐�ܕS����������Ƃ̂��ƁB
�@���̉摜�����Ă��Ďv���o�����B��t���َ̊R�ɂ��鉖��˂̂��Ƃ��B���w��̎j�ՂɂȂ��Ă���B���̈�˂́A��̗���̒��ɍO�@��t������������������ɁA��(�ʂ�)���������o�Ă���B��ʂ��ꂷ��Ȃ̂ɂ��������̌�������ƕ����B���ۂɎ�������˂ɍs�������Ƃ�����A�������Ɖ��������B
�@�\�N�ȏ�O�̂��Ƃ����A�����ŋߗׂ̐l�͐�������Ő���Ɏg���ƁA���Ȃ��Ă����ꂪ������ƕ������B���̌㌧�w��ɂȂ����̂ŁA�͂����ł��ď���Ȃ��Ƃ͏o���Ȃ��Ȃ��Ă���B
�@�������ォ��A��ː��͟���邱�ƂȂ��l���ł́A�O�@���ō�����u���ǂ�v��X�����邻�����B
�@��x�H�ׂĂ݂����B�����Ɣ��������ɂ������Ȃ��B](vimgtext2343.gif)
![�@�@�@���݂�Ǝ��@�@�@�@�@�@�@���c�@�[�]
�@�\����\������݂���̋�s���������B����������w�ׂ̗ɂ���t�����[�K�[�f���E�A���W�F�ŁA�H�K�N�𒆐S�ɏ\������{���E�R���ԁE�e�E�T�t�����Ȃǂ̂�������̉ԂƁA��Ȃ�̃J�����E����ꖂ�ꂽ�����S�Ȃǂ����Ȃ���U���B
�@�n���E�B���̊��ԂŁA�����ɂ͋����Z�������u����Ă���B�d�ʓ��ăN�C�Y�Ȃǂ��y���B
�@���H��A�����ڂ��ċ�s���č���������l�R��Âo���ċ����s�����B
�@�������X�Ƃ킭�y������ƂȂ����B���͊��������Ă���̂ŁA���T����\��Ȃǂ����Ă���W�ŁA��l�̃����o�[���߂Â��Ă���
�u���݂ꂿ���A���낢��L��������܂��v�ƁA�����ĉ�߂����ꂽ�B���̂r����͉������������݂ꂿ���ƌĂԂ̂ł���B���̂Ƃ��A���Q���̂s���A
�u���݂ꂿ���Ȃ́H�@�䂪�Ƃł́A���݂�v�l�ƌ����ƉƑ��ɒʂ���̂�v
�@����ȏ����������������悤�ȉ�b������A�ł����݂�D���Ƃ��ẮA�������v�����B
�@���݂�D�����A���̒m�l�͊F�������Ă���Ă���B�o�匋�Ђ̋���u�t�k�v�㌎���̒��ł���l�̐搶���A���̋�̊��z�Ƌ��ɂ��݂���̂��ƁA�t�k�̒��ł͉[�]����̂��݂ꈤ�D�ƂȂ̂͒m���Ă���ƁA�����ĉ������Ă���B�{���Ɋ��������ӂ��Ă���B
�@���N���݂�W�ɗ��ĉ�������������A���͍K�����Ƃ��݂��ݎv���Ă���B
�@�����x�����_�Ŕ��ɐ������Ȃ���A�~�ɂ��炭���݂�̉ԂƉ�b�����Ă���B���݂�
�́A��������̍K���������B�ł���B](vimgtext2342.gif)
![�@�@�D���ȏ�̂���X�@�@�@�@�@���c �[�]�@�@�@�@�@�@
�@�k��B�s���q�́A���ɂƂ��đ��̂ӂ邳�Ƃƌ����悤�B���̂Ȃ�Γ�������̎��ɂ͂ӂ邳�Ƃ͓����Ȃ̂ł���B�ܔN�]����������������q�́A�����Ȃ��������X�v���o���B
�@�d���Ō���A���s���z�e���邵�����Ă������A��\�����z�e���ʼn߂����Ǝ����ō���������H�ׂ����Ȃ�B�����Ń}���V��������A��l�邵�����邱�ƂɂȂ����B
�@���q�͍D���ȊX�ł���B���̗��R�́A�R�E�C�����ď邪����B�V��������܂�w���ӂ͓s��ŁA�f�p�[�g�������͎O�X���������B���̏�A�H�ׂ�mono
�͔��������A�o������l�͂悢�l�����������B�e�ʂ��F�l�����Ȃ������C�I���Y�N���u�ɓ���āA�n��̍s���ɎQ�������藷�s�ɍs�����肵�āA�l�ԂƂ��Ă��w�Ԃ��Ƃ������A�������l���ƌ𗬂�����B
�@�d�����v���悤�ɏo���āA�ܔN�͂����Ƃ����Ԃɉ߂����B
�@�@�@�e���鏬�q�Ɏc��Â���
�@�x���ɎU���D���ȏ���Љ�悤�B
�@�k��B�s�̏��q�֖͊�C���ɋ߂��A�Â�����ʂ̗v�Ղł������B
�@���q��͉i�\�\��N�ɖї����ɂ��z�邳���B�V���\�ܔN�ɁA�L�b�G�g����B����̂��߂ɏ��q��ɓ��邵�Ă���B���̌�́A�ї����M�̋���ɂȂ邪�A�c���ܔN�א쒉�������Ï邩�珬�q�ɖ{����ڂ����B���a�Z�N�����͉B�������Ï�ɓ���B��͍א쒉�������ɂȂ邪�A���̌�F�{��Ɉڂ�B
�@�ς��Ċ��i��N�ɏ��}�����^����A�鉺���͐������ꖾ����N�܂ł̓�S�N�]��ɓn���X���}���������ł������B
�@�����l�N�p�˒u�����s�Ȃ��A����͕ς�B
�@�����O�\��N�A��\��t�c�i�ߕ����݉c�����B���N�A�X���O���R�㕔���Ƃ��Ē��C����B���q�ɂ͉��O�̋�������������B
�@�]�ˎ���ɂ͖���ƌ���ꂽ���̖ʉe�́A���������������Ƃ��o����B��̂���X�ɏZ�ނ��Ƃ��o�����K�������������߂Ă���B
�@�@�@�t����璪���Z�Џ��q��](vimgtext230.gif)
![�@�@�@�Ԃ͐l���Ȃ��A�K���������@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���c�@�[�]
�@�D���ȉԂ͂������邪�A���ɂƂ��Ă̈�Ԃ͂��݂�ł���B
�@�����ȉԂ����A���݂�D���͏��������ł͂Ȃ��B�j���ɂ����Ȃ肢��B�����������Ă�����{���݂ꌤ����̗��ł́A�j���̕����o�ȗ��������B
�@�����s���_��A�����ł́A���N���̍��ɂȂ�Ɓu���݂�W�v���J�Â����B���{���݂ꌤ����͋��^���Ă��āA����̈�Ă����S���̔����o�W���Ă���B���{��A�O����A��z��ȂǁA���ʂ��ɗ���҂������قǂł���B
�@��d�����S�������d�炫������B�Â����肪������̂ɂ́A����ߕt���y���ސl������B
�@���݂�͖��t�̎��ォ��l�̐S�𑨂��Ă�܂Ȃ��B����͐����Ă���Ԃ����ł͂Ȃ��B
�@�F�l����V�N�ɗ����莆�ɁA�u���N�������ς����c����ɁA���݂�̉ԒB���K�����^��ł��܂��悤�Ɂv�ƁA�Ԉ�t�̃J�[�h�ɏ����Ă��芴�������B
�@���ł͖��N�A�����̗F�l���炷�݂���ʂ����i����悤�ɂȂ����B�e�B�[�J�b�v�ɍ����|�b�g�E�M�ނ�^�I���A�n���J�`�[�t�ɊG�͂������X�B�_���{�[������t�ɂȂ�قǏW�܂�̂ŁA���ӂ����N�̂��݂�W�̃K���X�P�[�X�ɓW�����Ă���B
�@��l�ł͏W�߂��Ȃ�����̓y�Y�Ⓙ�����i�ɁA�K���ŋ���t�ɂȂ�B�u���݂�̍����Ђ��v�́A���̏����ȗ�����̏�ŊÂ����g���葶�݊����������B
�@�|�v����̊G���D���Ȏ��́A�ނ̕`�������݂�̉Ԃ��Ȃ����Ƒ{���Ă����炠����A�m�l����ꖇ�̃R�s�[���͂����B����́A���[�c�A���g�̋ȁu���݂�v�̊y���̕\����ł������B���������݂�̉Ԃ������A���̏�ɍ����Ă���G�ŁA�吳�\�ܔN�ɕ`���ꂽ���̂��������B�����{�����������ƋF�O���Ă���B
�@�|�v����͔��l��ŗL�������A�Z�m�I�y���̕\������������f�U�C�����Ă���B�Ԃ̊G�ł͂Ȃ����u�Ԃ��݂�̌�́v�ȂǁA�O�������̂��݂�Ƃ����̂�����������B�܂��A�o���Z�S��̒��ɂ́A���݂�̋傪��傠�����B���ꂩ����V�������������҂��Ă���B
�@�G���ɍڂ��Ă������݂�̎ʐ^���A�J���[�R�s�[���Ă����������l�A����Ƃ��͕l������R�X�~���̊�����}�ւœ͂����B����͉F����s�m�̎�c����ƈꏏ�ɉF���ɍs���ė������݂�̎킩���������ŁA�������������̉Ԃ��炭�B��Ɉ�Ă��̂��ĉ��������̂ŁA�������ӂ��Ĉ�Ăčs�������Ǝv���Ă���B�Ȃ�Ƃ����Ă��F�����݂�ł���B
�@������\�ܔN�̂��݂�W�ɁA�J�̒��ܐl�̋��̐�y�����ɗ��Ă��ꂽ�B�[�厛��O�̂��Ώ��Œ��H�����܂�����ɁA�o�����邱�ƂɂȂ����B���̋�͒p�����������̂��������A�y�����ꎞ�ł������B
�@���̎�����u���݂�̋��v�����܂ꂽ�B�Z������n�܂�A���͏\�Z���ɂȂ����B��A�O�����Ɉ���s�����Ċy����ł���B
�@�����Ȃ��݂������Ől�̗ւ��L����A�y���݂������Ă����B�S���ĉ����������X�ɐS��芴�ӂ��Ă���B](vimgtext220.gif)
![���̌܁E���E��
�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���c�[�]
�@�@�Ԕ�����������Ε��V��
�@�@�Ԑ����l�̌��Ɏ��X��
�@
�@�@�x�����҂��ɂ��݂�炭
�@�@�Ԃ��݂��肻���S�ӂ���߂�
�@�@�ԏҊ�������l���r�̒[
�@�@
�@ �������̖����̗���Ē�
�@�@�@
�@�@���̏h�s���n��ĉ�������
�@�@�@
�@�@���m�ԊÂ�����Ɋ�悹��
�@
�@�@�g�t�╗�͗�����j���߂�
�@
�@�@�T�~��S�ɓ͂����肠��
�@�@�N�E�݂����݂�̂�����{�̒�](vimgtext219.gif)
![�@�D���ȓ��E�����@ �@�@�@�@���c�@�[�]�@�@�@�@�@
�@�D���ȓ��͑�R����B�C�O�Ȃ�A��ԂɃV�����[���[�ʂ�ł���B�N���X�}�X���ɂȂ�ƁA�X�H���ɑ�R�̃C���~�l�[�V�������P�����z�I�ŗ��������B���̃I�[�v���J�t�F�̂��镗�i���悢���A��͂�_������[��ꂩ��̃C���~�l�[�V�����̓��́A���ł��ڂ̗��ɂ���Y����Ȃ��B
�@�n���C�̃��C�L�L�̓��������B�z�e���̑O�ɍL����C�ݒʂ���A�����̐l�ʂ�̏��Ȃ����ɂ����������C���͂����B�[���̊C���Ȃ��߂�̂���������悳������B
�@���{�ł͍��̂��铹���D���ł���B
�@���c�J�ɏZ��ł������́A���[����������Ēʋ��Ă����B���ɗ[���̍��͔������B
�@�����߂��̍������o�X�ɏ���đ�����A�炫���߂���Ԑ���܂Ō��Ă���B
�@���z�̐[�厛�ӂ�ɂ����̓�������B���N���ɍs���Ă���B�Ԃ��������Ɏǂ������āA�����Ԃ��Ȃ�B�����ėt���̋G�߂�����B
�@��ԖY����Ȃ����̓�������B����́A�k�C���̏��O��ɍs���⓹�̍��͂��炵�������B���S��ނ��̍�������A���{�B��̍��̔����ق��������ɂ�����̍��̖������ƕ����B������肵�������̍��̃g���l���ŁA�Ԃ̓f����������悤�ł���B
�@�����������ƗD������������Ă���悤�ȕ��͋C�ɂȂ�B����߂��Ă����̓��͑����čs���B�����l���Ȃ��ŏ�����ĕ������B�n���̐l�̘b���ƁA���d���͈�ԂɌ\�ق�������̂�����Ƃ����B
�@���O�������̂��ړI�ōs�����̂ɁA�v���������Ȃ����̏o��ł������B���͓V�炵���Ȃ����A��Ղɂ����͍炢�Ă����B�����^���|�|����ʂɍ炢�Ă����̂���ۓI�ł������B
�@���O�D�ʼnh�������́A���͐Â��ŊX�̐l�͉��₩�Őe�������B
�@���ق���d�Ԃł��o�X�ł���O���Ԃ�����̂ŁA�ό��q�͒��s�┟�َR�Ɍ����Ă��܂��͎̂c�O�ł���B�������̎����̓^�C�~���O�����邩��A���̓��b�L�[�������Ǝv���B
�@�Ō�ɂ�����D���ȓ���������Ȃ�A���s���䎛�ӂ�̂˂˂̓��ł���B���s�ɍs���ƁA��l�Ȃ疈��̂悤�ɍ��䎛�Ɋ��B�s���x�ɏ����ÂX�Ȃǂ������Ă��邪�A�����������ł���B
�@�|�v����̕��������Ƃ��ĐS�ɂ��݂铹�ł�����B���N���Ǝv���Ă���B
�@���́A���ꂼ����j�������Ă���B���j��������̂��悵�A�����̍D�ݕ��͋C�ł̂�т葫�̂ނ��܂܂������ɂȂ�B
�@�l�̓������j�̐ςݏd�˂ŏo���Ă���B���Ȃ��Ƃ��l�ɖ��f�������Ȃ��ŕ��߂�悢�ƍl���Ă���B�l�Ƃӂꍇ���Ȃ���A�Ԃ̓����������i�߂���K���ł���B](vimgtext217.gif)
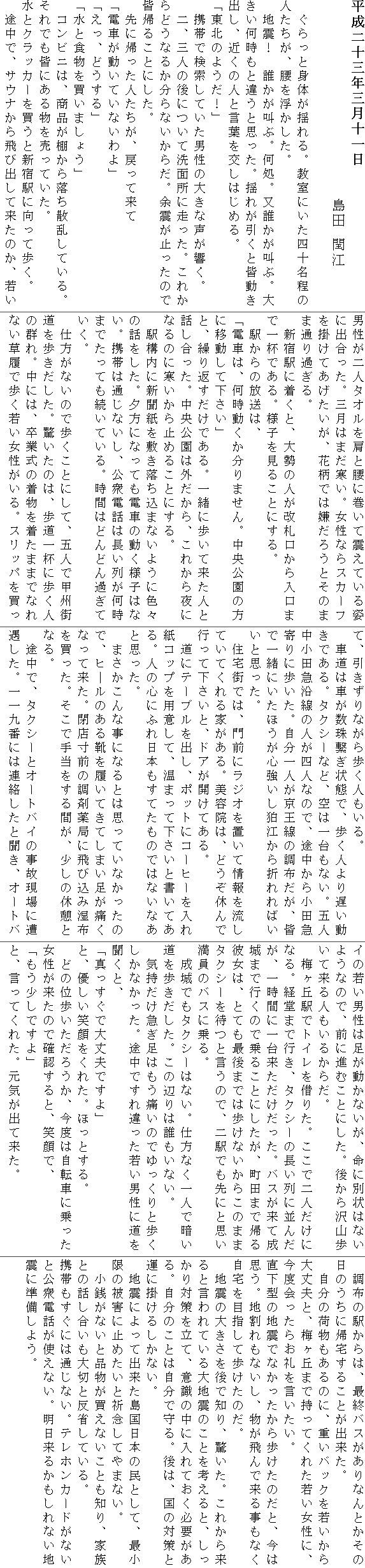
![�@�@���s�E��E���݂�@�@�@�@�@ ���c �[�]�@�@�@�@�@�@
�@��\�N���O�ɂȂ邾�낤���A�G�b�Z�C�����ŏo��e����[�߂ė����F�l�ƁA���N���O����b�������Ă������s�̗����A����Ǝ��������B����́A�O�l�ł̗��ƂȂ�B
�@�\���H�̐[�܂���A�V�������~��āA�v���Ԃ�̋��s�̋�C������t�z�����ށB
�@�w�̒n���ɂ����z�T�[�r�X�ɁA��ו����z�e���ɓ͂��Ă����悤�˗����Đg�y�ɂȂ�ƁA���̖ړI�n�Ɍ������B
�@�����@�̓�\�ܕ�F�̂������{��������ɁA�߂��̐F�Â��n�߂��g�t�̔ߓc�@����A�^�N�V�[�Ő������Ɍ����B
�@�����̕��䂩�牺�ɉ��A�G�͂����ɂ���p�x���畑������グ���B�B��{�g���Ă��Ȃ��E�l�Z�Ɋ�������B
�@�������������̎O�N�������A���E�̓X��`���Ȃ�������B����X�ł͒��ɓ����āA���邭�����Ă���ƁA�F�l�̈�l���A
�u����͂��݂ꂩ����v
�ƁA�����ď��M�������ė��Ă��ꂽ�B�X�̐l�Ɋm�F����ƁA��`�̂��݂�ł���ƌ����B
�@�����ĂƂ��ẮA�F�͒n���ʼnԐF�͔����ł���B�ł��������B�F�l�����́A�^���ɂ��݂�{�������Ă���Ă���B
�@������Ă��炤�Ɩ��A�������B���x���̍����������낤���B���̓x�ɂ��݂ꂪ����A���҂𗠐�Ȃ��B�����狞�s�ɗ���ƁA�����ɂ͗���B�쓩�Ƃ̌�ђ��q�́A���炵�������g��Ȃ��ŏ����Ă���B
�@�O�N�₩���N��ɐ܂ꏭ���s���ƁA����ɓ���X���������B���ɓ����ɕ����Ă݂��B
�u���݂�̊G���͂���܂��v
�u����܂���B�҂��ĉ������v
�A���甠���o���ė����B�J���ƁA���n�Ɏ��̂��݂ꂪ���ꂽ�B�Ԃ��ܗւ��Q����֕`����Ă���B�悭����ƁA�����ɂ��Ԃ��Q����ւ��`���ꂽ�傫�߂̃J�b�v�ł���B�@�@
����肪�A�t�̐F�Ɠ����Ȃ̂������Ă���B�����Ă̓���q�ŁA���s�f�U�C���D�i�W.�œ��I�������R���O��ł��邱�Ƃ��������B�܂��܂��������Ȃ�A�厖�Ɏ����A�����B
�@�����́A���s�ň�ԍD���ȍ��䎛�Ɍ������B
�@����������A�J�R���A�P���A���J���Ȃǂ̒����ɁA�H���̒��ʼn������̒��l���ÂԁB
�@���䎛�̐����̂˂˂̓��́A���������|�v������������Ǝv���ƁA�S�����B
�@���Ɋ�����q�ω@�̈��y���R�̕����A����lj�ɖڂ��_�ƂȂ�B������x�D�݂ƌ����������B
�@�ڂ̉��ɏĂ����āA���͋��s�ŌÂ̑T���ł��錚�m���ɍs���B�n�����S�N���L�O���āA���S�������̑�o���}���V���t�ɕ`����Ă����B���_���_�}���L���ł���B�����ɂ���������A���N�ɂ悢�Ƃ����������K��������ꎎ�����o�����B
�@���̘L����������G�A�͎R���̒�A�����̔����������͈�t�̎�����ł������B
�@�������̊�Ɛ�����̔������ƋZ�A���̂悳�Ή��ƁA�w�Ԃ��Ƃ������B
�@�Ō�ɂ�����A���݂�̎���t�����������B����́A�F�l�̂���l���A���s�ɍݏZ�ŁA���݂�D����m���āA�������ŕ`���ꂽ���݂�̊G�͂����������������Ƃł���B
���̂��݂ꂪ�A��Ɏ��R�ɍ炢�Ă���l�Ȃ��炵���G�ł���B�v���������Ȃ��v���[���g�Ɋ������āA�S������\���グ�����B
�@�ǂ��ɂ������Ă��Ȃ����݂�����ɁA���ȂǖY��ċA�H�ɒ������B
�@�D���ȋ��s�A�d���ł͂Ȃ����O�l�̋C�y�Ȉꔏ����̒Z�����B�C�z��̂悢�F�l�Ɋ��ӂ��A�[�������y���������߂��A�F��̐[�ގ����̋��s�ł������B](vimgtext207.gif)
![�@�@���̌܁E���E�܁@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���c�@�[�]
�@�@�p�X�e���̐F���d�˂Ă��݂ꑐ
�@�@
�@�@���ǂ��ɌN�̖ʉe���݂ꑐ�@�@�@�@�@
�@�@
�@�@�X�H���̎�t�܂Ԃ������̉�
�@�@
�@�@
�@�@���ɏ����C�j�V���������C�ɏ���
�@�@
�@�@��Ȃ��Ė؍҂̍��̂����Â�
�@�@
�@�@
�@
�@�@
�@�@�v���o�̊O�������t��l���ށ@�@
�@�@
�@�@��̒��N�̎莆�̊������ā@�@
�@�@
�@�@
�@�@����ʖ�v���Ȃ��t�̐�@�@
�@�@
�@�@�������̍����̎U�����@�@
�@�@
�@�@������ǂ��N�͉����~�̋�@�@](vimgtext1.gif)
![�@�@�~�̖�@���j�̓�Ɂ@�v���y���@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���c �[�]
�@�X����A�͋��������ėD���ɕ����D�c�M���B�D�c�M���̎q���ł��邱�Ƃ���A��������m���x�������B�t�B�M���A�X�P�[�g�́u�m�g�j�t�v�́A�ɂ�������ʂł������B�c�O�ł���B
�@�D�c�M�����e���r�Ō���ƁA�M���A���ۂ��v�������ׂĂ��܂��B
�@���̋����M���́A�G�g�A�ƍN�Ɠ���������߂���������������A���������[�������̂ŁA�e���r�h���}�ɓx�X�o�ꂷ��B
�@�m�g�j�́u�������ҁv�A�e���r�����́u���}�L�v�ȂǂŁA�{�\���̕ς�M�������������̂������ꔪ�N�͉��{���������B
�@���́A�M���̖��l�I�łȂ����ƁA�{�\���̕ςɋ����������Ă���B�u�{�\���ł́A����ł��Ȃ��v�����x�����Ă���B���̂��߂��A�D�c�M�����������Ă��܂��B
�@���̖{�\���ɂ́A���x���s�������Ƃ�����B�M���̗��h�ȕ�Ɩ{�\���̕ς̐펀�Җ����Ɍf������Ă���B���̒��Ŗڂ������̂��A�M���̏����ŗL���Ȕ��N�E�X���ۂƂ��̒�ŁA�͊ہA�V�ہB�\��̎Ⴓ�łƁA�����̈ӂ�\����l�������B
�@�\�O�A�l�N�O�̂��Ƃ����A���É��Ŏd�����I�������������j�������̂ŁA���R������ċA�邱�Ƃɂ����B�ؑ]��߂��̏�ŁA�B��l�̏��L�ł��������A���݂͖������Ǘ����Ă���B�B
�@�V��̊K�i�͋}�ł������B���܂�ɂ��}�Ȃ������A�b�ɂ��Ɣ��q�q�c�@���A�����ł͌C�𗚂�������ꂽ�����ł���B�c�@�̎ʐ^�������Ă����B
�@�������������܂ŗ����̂�����A���R��Ƃ͉��̂���A�X���ۂ̐��܂ꂽ���R�隬�ɍs�������Ȃ����B
�@���R��́A�ē����O���Ï�R�̒���ɒz��������̂��ƂŁA�����Ƃ��Ă�Ă���B��ɐM�����d�b�̐X���i�悵�Ȃ�j�ɗ^�����B���ۂ̕��ł���B���͓��邵�A���R�i���R�j��Ɖ��́B���A���i���یZ�j�A�����i���ۖ���j�ƁA�O�\�ܔN�ԁA�X�����ݏ邵���B�O��ɂ킽�萮������g�[����A���R��͍L��Ȃ��̂ł������ƁA���@�������ʂł���B
�@�c���ܔN�A�ƍN�̎���ƂȂ�A�쒆���~�Ï�ɍ��ւƂȂ�B����ċ��R��͎���A���ɑg�܂�ؑ\�������A���R�Ɉڒz�����B���R���͐ΐ���O����g�ł���B
�@���̂悤�ȗ��j�̂���A���������̓T�^�I�ȎR�邾�����隬���������ƐS�͒e�B
�@���É��S���Ńg�R�g�R�s����悤�����A�s�����������̂Ń^�N�V�[�ōs�����Ƃɂ����B���R�X���͎�t�̋G�߂ŁA�R���݂�c���͔������B
�@�r���܂ōs���ƁA�u���ۂ̗��v�Ƒ傫�ȊŔ������Ă����B�߂��Ȃ����Ǝv���ƁA�h�L�h�L���Ă���B�����̗�������ސX�Ƃ̕�ł���嗳�R���T���ɂ���肽���Ǝv�����B�����A�^�N�V�[�̉^�]��́A�n���i�����S�ԎR���j�̐l�ł͂Ȃ������̂ŁA���ɖ������肵�āA���������ꂾ�����B
�@���X�Őu���ƁA�隬�͂قƂ�lj����Ȃ���A���Ă���s���̂́A�������Ƃ킩�����B�M���̋x��V�皬�Ȃnj������������A���߂��B
�@�ǂ������̎��Ȃǂ�������ƒT�����B����ƐX���̎��i���ۂ̕�j�̕�̂����Ǝ��ɂ��ǂ蒅�����B
�@�ˑR�̖K��ł��������A�������痈�����Ƃ�`����ƁA�������ɓ���Ă����������B
�@���܂�傫�Ȏ��ł͂Ȃ����A��{���͗��h�ł���B���Q�肵����A�K�˂��킯��b���ƁA���ۂ̕�ł��閭����̕�Ɉē����Ă�������B���̐X�Ƃɉ��̂��������̕�ɂ�������킹���B
�@���~�Œ��ق̐ڑ҂����Ă�����������ɁA������摜���������Ă����������B���ꂾ���ł����������̂ɉ�����ؔ��������Ă��Ă����������B���ɔ����z�ő�ɕ��ł��������g�́A�Ȃ�Ɨ��ۂ̎g�����V�i�₶��j�ł������B
�@�����Ă��悢�Ƃ��������o���̂ŁA�g���k����v���ŁA����Ŏ����グ���B���̍e�������Ȃ�����A�������Ȃ����k���Ă���B
�@�����V���A�ǂ����ď�Ǝ��ɂ���̂��肩�ł͂Ȃ����A�߂����ɐl�Ɍ����Ȃ����̂��A���Ζʂ̎��������Ă������������Ƃ́A��ςɍK���Ȃ��Ƃł���B
�@�����͂�����x�K�˂Ă݂����B
�@���R����ӂ́A���q����͂��߂Ƃ��āA��������̏隬������B�������A������茩�ĉ�肽���B
�@�����āA�����M���̌�����A�M���̈�̂̂Ȃ������{�\���̕ς̐^���������B
�@����ǁA�܂��͐M�����I�����s�b�N�ŋ����_������邱�Ƃ��F�O���Ă���B
�@���NjL
�@�@�@�X����i���ہj�́A�Z�B�⑺���ŁA�ܖ���
�@�@�@�������B�\��ŏ�傾�������Ƃ́A���܂�m��
�@�@�@��Ă��Ȃ��B
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����P�W�N�P�Q���P�O���E�L](vimgtext30.gif)
![�@�@���̌܁E���E�܁@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���c�[�]
�[�Ă�����Y���e�̎��~�܂�
�@�@�@�@�@���ǂ��ܑ�����V�̐�
�@�@�@�@�������̌N�̌̋�������
�@�@�@�@�H����ܕS�����ɌN������
�@�@�@�@�[�Ă����̉��������̂���
�@���ǂ��ܑ�����V�̐�
�@�@�@ �������̌N�̌̋�������](vimgtext52.gif)
![�@(�o��)
�@�@�@���̌��܁@�@�@�@���c �[�]�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@
����⏬�w����܂��܂�����
�@�@
�@�@�Ȃ���̂ʂ�����c�����݂ꑐ
�@
�@�@���݂��N�Z�ފX�ɔ�т䂯��
�@�@
�O�����h��������N������
�@�@
�U��ĂȂٍD���ɂȂ肽��H��
�@�@
�؍҂�s�����藈����A�蓹
�H�����������ȉw�ŌN�܂Ă�](vimgtext80.gif)
![�R�X���X�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���c �[�]
���������~�J���悤�₭������ƁA��T�Ԃŗ��H�ƂȂ�B
�U���̓r���ŁA�H�n�̉��ɐ����̃R�X���X���������B�W���s���N�̉ԕق��A�킸���ɗh��Ă����B
�R�X���X�⏬�����h�炮�H�n�̉�
�R�X���X�́A���̍D���ȉԂ̈���B�R�b�v�ɑ}������ւ����ŗǂ����A�y��ȂǂɈ�ʂɍ炫�A���̂܂܂ɗh�炮���i���A�Y�ꂪ�����B
�g���b�R�d�ԂŃR�X���X�����ɍs�������̂��Ƃ��A�v���o���B
�d���ŋ��s�̖��ɍs�����A��ɁA�n�����X�X�ŃR�X���X���̊G���������B
�u���̊G�̏ꏊ�ɍs���Ă݂����̂ł����v
�u���Ԃ�g���b�R�d�Ԃł�����Ǝv���܂��v
�u���肪�Ƃ��������܂��v
�����A���[�j���O�R�[���ŋN����ƁA���H�����������Ƀz�e������ɂ����B
���R�ɍs���g���b�R�d�Ԃɏ��B�쉈���𑖂�̂ŋC�����悭�A���X�s�������D�̐l���������U���Ă��ꂽ�������B
�T���w�ʼn��Ԃ��āA�����Ȃ��������炭�����ƁA�R�X���X���̊Ŕ��������B
�O�S�~���x�������ɓ���B�����͂ǂ̂��炢�̍L�����킩��Ȃ����A�ׂ����̗����ɔw��قǂ�����R�X���X���A�������h��Ă���B�l�����Ƃ��ɂ͕������邪�A�ǂ��ɂ���̂������Ȃ��B
�ԂɈ�t�̋C����������B
���y�Y�ɃR�X���X���\�{���炢�A�K���C���Ńo�X�ɏ��A�i�q�̋T���w�Ɍ��������B�ےÐ�̐쉺����y���݂Ȃ��痒�R�ɖ߂����B�u���ȗ��ł������B
�k��B�ɂ����Ƃ��̂��Ƃ��v���o���B
�e���r�̉�ʂ����ς��̃R�X���X�����āA�����p�ɕ����ԓ��ɍs�����B���[�^�[�{�[�g�ŏo���ɍs���A�^�N�V�[�ɏ�芷���ď����s���ƁA���n������R�X���X�ň�t�̋u�ɒ������B�x���Ȃ̂ŁA�J�b�v����e�q�A�ꂪ�ʐ^���B���Ă���B�Ԃ̔������䂦���A�F�������Ƃ���������Ă���B��l�ł������ގ��́A�������т��������B
�����ɔ����p����������B�H�̋�̐��ƁA�ԐF�������ڂɕ�����ł���B�S�̒��̃R�X���X�́A���܂ł��������h��Ă���B
�R�X���X�̉ԊԂɌ����������p
�|�X�g�ɁA���H�̌Ós���s�̂c�l���͂��Ă����B�H�̋��s�ɁA�}�ɍs�������Ȃ����B
���A��ŁA�܂������R�X���X�̌Q�������ɍs���Ă݂悤�Ǝv���A�ό�����ɖ₢���킹���B����ƁA���̓g���b�R�d�Ԃōs���Ƃ���ɃR�X���X�͂Ȃ��A�i�q�̋T���ɋ㌎���ɍ炭�̂�����ƌ���ꂽ�B���X�c�O�ł���B](vimgtext44.gif)
![�@�@�@�@���̌��܁@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���c �[�]�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�Ȃ���̂ʂ�����c�����݂ꑐ
�@�@���݂��N�Z�ފX�ɔ�т䂯��
�@�@�O�����h��������N������
�@�@�U��ĂȂٍD���ɂȂ肽��H��
�@�@�؍҂�s�����藈����A�蓹
�@�@�H�����������ȉw�ŌN�܂Ă�
�@�@�N�����H�_�����������@�@�@
�@�@�N�����X�e�b�v���߂ΊO�͐�
�@
�@�@�������̂Ђ�ɂ̂��N�݂�
�@�@�������̑z���ЂƂ��т��݂�炭](vimgtext89.gif)
![�V���[�g�V���[�g����
�F�����ȏ���l�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���c �[�]
�V�������ɍs���l�����ޒẤA�V�h�̍��w�r���̈ꎺ����Z�����s�������l�������낵�Ă����B�ӂƁA�v���Ԃ�ɗǑ��̐������������A�Ǝv�����B
�u���V���V�A���B���C�ɂ��Ă�H�v
�u�������ˁB�N����d�b�Ȃ�āv
�u�ԍ����ς�����̂ˁB�T������B�����z�����́H�v
�u�e�g�ɂȂ��Ă���鏗���ƁA�����}���V�����̏㉺�ɏZ�ނ��Ƃɂ����v
�u�����c�c��������́H�v
�u���[��A���͗�����[�߂�w�͒��A���ȁv
�u�����l���ď��Ȃ�����A��ɂ��Ăˁv
�u�d�b���肪�Ƃ��B�d���撣���v
�u���悤�Ȃ�B�����d�b���Ȃ�����c�c�v
�@�@�w���𑲋Ƃ��č��Ǝ����Q�l���������Ǒ��B�w�Z�A��ɂ悭�V�h�̊X�ŁA�H���₨����������A�ނ̉ƂɊ���Ĕނ̒e���M�^�[�����肵���B������x�A�������������B
�w������̗F�����ȏ���l�����̊W�́A�g�������悤�ɏI������B](vimgtext117.gif)
![�@�܁X�̔o��Ɏv���Ă̖�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���c�[�]
�@�Â��m�[�g�����Ă�����A�������̏��q����ɍ�����o����������B�\�N�ȏ���O�ɁA�����P�g���C�Ő��N�Ԃ��߂������Ƃ���ł���B
�@�y�������������A�d���A�����A�����_�̂悤�Ɏ��X�ƗN���o�����B
�@���̂���A�x���ɂ́A�Ƃ��ǂ����A��ŗׂ̑啪���ɏo�������B�R�z�@���n��A�F���_�{�A���������c�c�B�����Ő��܂��������̖ڂɂ́A�ǂ������������V�N�ɉf�����B
�@���ɁA�����������璭�߂��C�͔����������B�����͂܂��A���\�����ȏ�Ɏl�S�̈ȏ�̖��R�����U�݂��邱�Ƃł��m���Ă���B�������Ƃ����n��������B
�@�Ă̏��߂ɁA���̍��������̌F�얁�R�������ɍs�����ƁA��Ђ̒��ԂɗU��ꂽ���Ƃ��������B
�@���X�ɉו���a���āA�X�j�[�J�[����A��������A���̉��̌������R�����O�S���[�g���قǓo��B
�@�悤�₭�H�蒅�����Ǝv������A���������\��i����Βi���X�ɓo��ƕ����A�~�߂����Ȃ����B���Ԃɂ́A��ɍs���Ă��炤�B
�@�c�c�������A���̂��߂ɂ����܂ŗ����̂��A�Ǝv�������A�[�ċz�����Č��ǂ����B
�@���ς݂��ꂽ�Βi�͓o��Â炢�B�召�̐��蓖���莟��ɐςݏグ�č�����悤�ȁA���\�ȑ���ł���B
�@��ɏ������āA�����ɋC�����A�����o���B
�@��\��i�������ďオ��ƁA�L��ɏo���B�����ɂ́A�u�₩�ȏ��Ă̕��������Ă����B�����Ȃ���������������������B
�@�ق��Ƃ��Č��ƁA���R�����������B�������č����s�������B�E��ɂ͑���@���B���ɏ��������̂����邪�����́A�킩��Ȃ��B
�@�s�������͍����������[�g�������邻�����B�O�K���炢�̍������낤���B���h�Ȋ炾�B����@���͂�����ꃁ�[�g�����炢�Ⴍ�āA�������B
�@�����̍r���̑��́A��������ɍ��ꂽ�Ƃ����B�C�s�Ƃ͂����A�R��̊R�Ɍ������āA��S�s���ɕ����葱�����M�S�ɁA���|�����v���������B
�@�߂蓹�ł̘b��́A���ς݂̐Βi�̂��Ƃ������B
�u�S���ςƕ���������ǁc�c�v
�u����ۂǁA���\�ɐς̂ˁv
�u�S�Ƃ����́A�p���������A�l��H���Ƌ�����Ă�����ł��傤�H�v
�u�ł��A�z����̐�������v
�u����NjS�ɋ߂��A�c���Ŏv�����̂Ȃ��l�́A����������ˁv
�u������A�S������\��i���ς��R���m�肽����v
�u�����ŕ����Č��܂��傤��v
�@�s�������l�Ɛ����|�������Ȃ���A���X�ɒ����B�X�j�[�J�[��Ԃ��A�ו������A���ӂ��ēy�Y�����߂��B���̂��ƁA�������̎��̖�����B
�@�Z�E�Ɏ������̋^��ɂ��Đq�˂�ƁA
�u�̘b�ł����A���̕ӂ�ɋS���o�Ăˁ\�\�v
�@�Ⴂ�����тɏo���Ȃ��ƍr�炵���̂ŁA���������l���������k���āA�閾���܂łɐΒi��S�i�ςݏI������A���������o�����Ƃɂ����̂��������B
�u�S�͖����Ő�ς�ł������̂ł��v
�u����ő召�̐����藐��Ă���̂ˁv
�܂��邪�����Ȃ������ɁA�S�i�ɋ߂��Ȃ��Ă����̂ŁA���l�����͓���������B
�u���̂Ƃ���l�̒m�b�҂��A�{�̖�����^���܂����B�S�͖邪������Ǝv���A��\��i�ςƂ���ł�����߂��̂ł��v
�@�l�ɖ��f�������Ȃ��B�͂�m�b���o�������A��ςȂ��Ƃ������ł���B��\��i�̐Βi�����āA�撣���ēo�����Ƃ��̑u�����͉��ɂ������������B
�@����ȋ��P�̂��߂��A���ς݂̐Βi�́A�����z���Ă����̂܂܂Ȃ̂ł��낤�B
�@�Βi�̓䂪��������A�}�ɋ��o���A�s���Ɍ����������ɒ��s�����B
�@�\�N�ȏ�O�̗��̎v���o�ł���B
�@��l�ł͍s�����Ƃ̏o���Ȃ��ꏊ�ł��邾���ɁA���������Ă��ꂽ���q�̒��Ԃ����ɁA�S��芴�ӁB
�@�@�����̖��R���ɂ��Ă̕�
�@�@
�@�@�������ēo������ɖ��R��](vimgtext132.gif)
![�@�����ɂ���˂NJ����ЂƂ萆��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���c �[�]�@
�@�o�����т�Ă����N���𓊔����Ȃ���A������グ��ƓV�C�\��ɔ����āA�d���_�����ꍞ�߂Ă���B�\�肵�Ă����f�p�[�g�s���͎~�߂邱�Ƃɂ��āA����ɋ߂��̃X�[�p�[�Ɋ�����B
�@������߂��̑�̏�ɁA�����̓������������Ă����ׂĂ���B�����͎������̓����ƁA�������Ă���悤���B
�@�����Ɓc�c�ƁA���̖��O���v���o���Ă݂�B
�u�Z���A�i�Y�i�A�S�M���E�A�n�R�x���A�z�g�P�m�U�A�X�Y�i�A�X�Y�V���A���ꂼ�����v
�@�v���o�����I�@�i�Y�i�͂��y�����̂��ƂŁA�S�M���E�́A�����q���̂���n�ɉ��F���Ԃ��炩���Ă����G���̃n�n�R���̂��Ƃ��B�n�R�x���̓n�R�x�B�X�Y�i�̓J�u�ŁA�X�Y�V���͑卪�B
�@�y���y������n�n�R���Ȃǂ͖Ȃ̂��낤���A����Ȃ��Ƃ͒m��Ȃ��Ă��A����T�����Ȃ��Ă��A�Ƃɂ����Ђ��Ĕ����Ύ�����������B�֗��Ȏ���ɂȂ������̂��B
�@�����͓܂肾�����̂Ő������߂邱�Ƃɂ��āA�������N�����B����H�ׂ悤���B
�@�������̓��Ȃ̂��v���o���āA����Ă��̂����ƁA�X�Y�V���ƃX�Y�i������B�₲�т�����B
�@�卪�𔖐�ɂ��A�t�ׂ͍������ށB�J�u�͗t�������g�����B
�@�����ő���A�ʂ�ܓ��Ŗ߂��ă_�V�����B���т����čŎς�B���Ƃ���卪�Ȃǂ������āA���炩���Ȃ��Ă����Ƃ���ŁA�ݖ�����������t���ꂽ�B�Ō�Ƀ~�c�o�Ɗ��g���U�炵�ďo���オ��B
�@�ő��̃_�V���悭�o�Ă��āA���������B
�@�Ƃ�̎������Ȃ�A����ŏ[���B
�@�e���r������ƁA�O���ō��Ƃ��������ԑg���f���Ă���B�����̗����l������������邽�߂ɁA�卪�̗t���������݂Ȃ��猾�����B
�u����������Ȃ��Ă�������ł���B�̂����đS�����낦��̂͑�ς������ł��傤�v
�@���ʂ̗����ԑg�Ȃ�A�^�ʂ�Ɏ�����p�ӂ��邩������Ȃ����A�{���ɔޏ��̌����Ƃ��肾��A�Ƌ������o�����B
�@���N�O�̐����ɂ��A�~�c�o�Ƃ��荇�킹�̍ޗ��Ŋ������A�����o��ɂ��ē��債����I�ɓ��������Ƃ�����B
�@�������̂�����A���������m������ŏȗ����A�����̔�ꂽ�݂����Ŗ����B���ꂪ�������ꂽ�̂��Ǝv���Ă���B
�@���ꂩ����������ł���Ă������B](vimgtext151.gif)
![�@�@�Ԃ���āc�c
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���c �[�]
�@
�@���c�}���̔~���u�w����k���ܕ��̉H���،����ɂ͖S�{�̍g�~���~�A�}����~������A���N�ɂ́u��������~�܂�v���Â����B
�@�l�\�N�O�́A�l���قƂ�ǂ��Ȃ��������̌������A���͂��Ȃ�̐l�o�ł���B
�@�o��F�����ƁA��l�Ŕ~���ɍs�����B
�@�~�D���Ȓ������A���̌������悭�U�Ă������Ƃ��炩�A��������B�~�܂�̊��Ԓ��ɂ́A�o����W���Ă���B
�@��N���債����A�v�����������I���āA���̋߂��Ɍf������Ă����B
�@�@�Ԃ���Đ������ė���t�̕�
�@�~�܂肪�I��ƁA���N�̓��I��ɕς��B
�@���グ��ƁA�~�̎}�ԂɐL�����Ă���B�����炫�̉Ԃ��ʐ^�ɎB��A�~�̍���w�Ɍ������o���B
�@�����Ȃ���A��N�̔~�܂���v���o�����B
�@�m�l�Əo�������B���J�ɋ߂��~�̖��o�b�N�Ɏʐ^���B���Ă�����A�߂��ɂ����Z�\���炢�̒j�������������Ă����B
�u����������B�����ق���������v
�@������ꂽ�悤�Ɉʒu��ւ��āA�m�l�ƌ��݂ɎB���Ă���ƁA���̐l������Ă��āA
�u��l�ꏏ�ɎB���Ă������v
�@���߉�Ȃ��A�Ǝv���Ȃ�����J������n���ƁA
�u���������E�A������Ə�����āv
�@�|�[�Y�܂Ŏw�����āA�V���b�^�[������B
�@�o���オ�����ʐ^�̒��̎������́A���X���߂Ɍ�����B�ł��A��l�ꏏ�Ɏʂ��Ă���̂͂߂����ɂȂ�����A�ǂ��v���o�ɂȂ����B�ނ̂��߉�Ɋ��ӂł���B
�@���������A�\�N�ȏ�O�ɂ������悤�Ȃ��Ƃ��������B����̏��a�L�O�����ɁA�|�s�[�̎ʐ^���B�e���邽�߂Ɉ�l�ōs�����Ƃ��������B
�@���a�L�O�����͍L��ŁA�l�G�܁X�ɍ炭�Ԃ������ł���B�r������A�X�����`�̃{�[�g��������ł����B
�@��������\���قǕ����ƁA��ʂ̃|�s�[���ɏo���B����s���N�����邪�A�قƂ�ǂ����̍D���ȐԐF�ł���B���̍����܂ŏ䂪�L�тĂ�����̂�����B
�@���́A�Q������Ԃ��|�s�[�Ɍ������ĉ�����V���b�^�[������B
�@�߂��ŎO�r�𐘂��āA�ʐ^���B���Ă������V�̒j�������Ɍ������āA
�u�悩������A���Ȃ����B���Ă����܂��傤���v
�@�B��͍̂D�������A�B����̂͂��܂�D�܂Ȃ��B�S�O���Ă���ƁA
�u�Ԃ͎ʂ��Ă��A�����͎ʂ��Ȃ��ł��傤�v
�@�����͂�����B���肢���܂��ƌ����āA�J��������n�����B
�u�������������āv
�@�V���b�^�[�����ƁA�����ɃJ������߂��Ă��ꂽ�̂ŁA�����Ă݂�B
�u���B�肵�܂��傤���v
�u����A�Ƃ��߂��ł������Ă��邩��v
�@����ɁA�O�r������Ύ����ŎB���B�l�ɗ��ނ��Ƃ͂Ȃ��킯���B
�u���肪�Ƃ��������܂����v
�@�|�s�[���\���y����ł���A�ƘH�ɂ����B
�@���̎B�����ʐ^�͏�X�̏o���������B�ʂ��Ă�������ʐ^�̒��̎��́A�Ԃ��|�s�[�����o�b�N�ɏ��Ă���B���R�̂ŁA�C�ɓ������B
�@�������̏�ɏ����Ă���B
�@�@�ԍD���̓J�����������ďt��ǂ�](vimgtext158.gif)
![�@�@�@���̔����R
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���c �[�]
�@�o��̉�̗F�l�Ɠ�l�Ŕ����ɏo�������B�~�J�̍Œ������A���̓��̓V�C�\��́u�܂�v�������B
�@�����́A�厩�R�̎R�ƌA�O��N�O�̉Ό��Ղ�֏��A�_�ЁA���j�̒��Ȃǂ�����B���p�قȂǂ́A����ł͉��Ȃ��قǂ̐�������B
�@�������A�Ȃ�Ƃ����Ă��A��Ԃ̖��͖͂L���Ȍ��炠�ӂ�鉷��B������⋍���̂悤�Ȑp��ȂǁA�ꏊ�ɂ��Ⴄ�̂������B���A��������\�ł���B
�@�~�J���ɓ���ƁA�����̓o�R�d�Ԃ́q���������d�ԁr�ɂȂ�B�ԑ��������o���Γ͂������ȋ����ɍ炫����鎇�z�ԁB�Ԃ̍Ő����ɂ͖�́q�����������r������A���C�g�A�b�v���ꂽ�Ԃ��y���ނ��Ƃ��ł���B
�@���̓d�Ԃɏ��̂��y���݂��������A�܂��͔������{����o�X�ŁA���m�ΔȂ̌������Ɍ������B
�@���͍���̏����s�́A������̉��������˂Ă���B���̎d���̊W�ŁA�S���̓��Ǝ҂Ɖ�ł���B�q���̂��납�牽�\����s���Ă��锠���Ȃ�ē��ł���ƁA�������������̂������B
�@������̂��Ƃ͓��s�̗F�l�ɂ͓`���Ă���B
�@�o�X�͓��m��A�啽��A�{�m���Ə����i�݁A���O�J�����肩�獶�ɐ܂ꂽ�B����ɎR�̒��ɓ���B�J���~������~�肷��B
�@�}�ɂ����肪�Â��Ȃ����B���ł���B�o�X�̑O�́A�ԓ��قǂ����悪�����Ȃ��B�o�X�̃X�s�[�h�������A���C�g�������B�^�]��́A���ꂽ�l�q�Ńn���h���������Ă���B
�@�F�l���O�����߂��܂܌����B
�u���������ƂɂȂ�����ˁv
�u������ƕ|����v
�u���̊C�Ȃ�Ėő��ɂ݂��Ȃ���v
�u�V�C�\��͂͂���ˁB����Ȃ̏��߂Ă�v
�u�o��ɂȂ邩���v
�@�������A�o�咇�ԁB���悢���ɓ]�����Ă��܂��B�C���y�ɂȂ����B
�@���������邭�Ȃ�������A�������ɒ������B�O�ɏo��ƁA�܂��J���~���Ă����B���m�͂قƂ�nj������A�݂ɋ߂��Ƃ���ł����r�g�ł���B���߂Ă̌��i���B
�@�J���������Ȃ��Ă����̂ŁA�z�e���̃V���g���o�X�ɏ悹�Ă�������B�z�e���͌ΔȂɂ���A�����Ȃ��������ƌ��s��������D�Ȃǂ�������̂����A�i�F�͊D�F��F�Ŏc�O�ł���B�J�h������˂Ă����Œ��H���Ƃ邱�Ƃɂ����B
�@�P�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ʼnו��𑝂₵�����Ȃ��������A���A�����������Ă��܂����B�H��ɔ��X���̂����āA���̑�D���ȉԂ��h�J�����^�I�����������̂��B���̎��Ŏh�����X�~���̉Ԃ���ڂ������Ȃ������B
�@�\��ł́A�C���D�ŌΐK�ɍs���A���[�v�E�F�[�ő��_�R�ցA�P�[�u���J�[�ŋ����֍s�����肾�������A������߂��B
�@�o�X�ŋ����܂Œ��s���邱�Ƃɂ����B
�@�J�̏オ�������������ŁA�Ƃ�ǂ�̂����������J�����ɔ[�߂��B
�@�ړI�̈�ł�����������z�e���Ɋ������Ă���A�A�H�ɂ����B
�@�o�R�d�Ԃ̋����w����A���������d�Ԃɗh���A���z�Ԃ��\���Ɋy���݂Ȃ���A���{�܂ʼn������B
�@�V��ɐU��ꂽ������������A�A��̃��}���X�J�[�̒��ł́A
�u���́A�����̃����b�N���p�قɍs���܂��傤��v
�@�g�t���������f���邱��̔����R�̗�������B
�@�@����������@���̕������@�����R](vimgtext160.gif)
![�@�@�����A����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���c�[�]
�@���s�ł̎d�����I��������ƁA��l�ɂȂ����C�y���ŁA���䎛�܂ő����������B
���䎛�́A����ƍN���L�b�G�g�����߂Ɍ������A�G�g�̖k�̐����E����@����e�����߂Ɍ��Ă��N���������킹�������������B
�@�l�G�܁X�̒뉀�͔������A�d�v�������������āA���̍D���ȌÎ��̈�ł���B
�@���䎛�����\�������ƁA���������ʂɂ������ƕ����Ă䂭�ƁA�ӂƁA�X��̏�������ɓ������B
�@�G�͂����Ȃǎl�A�ܓ_��I��ŁA�X�̉��ɐ���������ƁA�a���p�̏����ȘV�w�l���o�Ă����B����Ă��炤�̂��ڂ���Ƒ҂��Ă������A�ӂƁA�X�Ɖ��Ƃ̋��̕ǂɓ̎���������Ɋ|���Ă���̂ɋC�������B�悭����ƁA�������̏������`����Ă���B�h�L�b�Ƃ����B������Ǝv���A
�u���̎��c�c����ł����v
�@���͍��A�|�v����ɖ����Ȃ̂��B
�u�����A�����ł��v
�@���܂�ɂ���������ƁA�Ԃ��Ă����̂ŋ������B
�@�V�w�l�ɂ��ƁA�����䎛�̋߂��ɏ����ƏZ��ł����Ƃ��ɂ������Ȃ��Ȃ�ƁA���̓X�ɊG�������Ă��Ă͔����ė~�����Ɨ��݂��̂��Ƃ��B���̂Ƃ��ɂ��̘V�w�l���n�������������Ƙb���Ă��ꂽ�B
�u���̂܂܂łܑ͖̂Ȃ��ł��ˁv
�u�悭���������܂��B���ǂ��ܕS���~���̈�疜�~���̂Ŕ����ė~�����ƁA�l�͗��܂�����ǂ��A���������Ă��邤���͍��̂܂܂ɂ��Ă�������ł��v
�@�ޏ��́A�͂�����ƌ��������B
�@�l�ʂ肪�����A���ʼn����̂ɂƎv���Ȃ���X����ɂ����B
�@���̊G�̏����́A����̗��l�̕F�T�ł��낤�B�吳�Z�N���玵�N�̒Z���Ԃ̓�l���Â�A�}�ɖ����g�߂Ɋ������B
�@���l��ŗL���Ȓ|�v����́A�܂��A���ɂ��ڂ�鎍�l�ł���o�l�ł��������B
�@�����\���N���R���ɐ��܂�A���a��N�㌎�A�\��ڑO�ɁA�M�B�Ő��U���I�����B
�@����c���Ɗw�Z���o�āA��\�O�̎��ɓǔ��V���Ђɓ��ЁB���̔N�ɁA��ΔN��̑�����ƌ��������B��N��ɗ������邪�A���̌���������Ēj�q�O�l�����������B�F�T�̏o���ɂ�肻�̊W���I������B
�@���O�\��ŗ��ɗ��������肪�A�F�T�ł���B�܂����q���p�w�Z�̊w���ł��������߂ɔޏ��̐e�ɔ�����A��l�͋��s�ŕ�炷�悤�ɂȂ�B����ɗ��s���ɕF�T���a�C�ɂȂ�A���e�����ē����ɘA��߂������߁A�ʂ�邱�ƂɂȂ����悤���B
�@���̌�A����������ɖ߂�A������ɂ���e�x�m�z�e���œ�N�]���߂��������A�ĉ�邱�Ƃ͂��Ȃ�Ȃ������B�吳��N�ꌎ�A�F�T�͒Z���l��������B
�@����͎O�\�܍̂Ƃ��ɁA��\�ΔN���Ń��f���̂��t�Ƌe�x�m�z�e���œ������A���̌�a�J��F����Ɉڂ�Z�B�����l��������������H�c���l�ŁA�{�����J�q���i�J�l���j�Ƃ����B
�@���������邩�炱���A�d���ɒe�݂����A���ꂪ����B���������A���̓s�x�A�{�C�ň������̂ł���B
�@�����̐��������т����ނ́A��Ƃ̎R�c���q�ȂǂƂ��t���������������B���̑��A��ʂɂ͒m���Ă��Ȃ������������̂ł͂Ȃ����낤���B
�@�@�҂Ăǂ��点�Ǘ��ʐl��
�@�@���҂����̂�邹�Ȃ�
�@�@�����͌����łʂ�����
�@�吳��N�A��\��̏I���ɍ��ꂽ���̎��̐Ȃ��Ɣ������́A���̐����Ƌ��ɖY����Ȃ����A����Ȏ�������B
�@�@���Ƃ��ӏ�����
�@�@����邽�߂ɗ���������
�@�@���m��ʒ��������
�@�@�����ڂ�����T��
�@�吳�\�O�N�l�\�̂Ƃ��̎��Łu�Ⴊ�������v�ł���B�ǂ���ɂ��A����炵�������ȋC�������o�Ă���Ǝv���B
�@�@�Ƃ���ŁA����͎������ł͂Ȃ��A�����̔o����c���Ă���B�o��D���̎��ɂ͌������Ȃ�����̈�ʂł���B
�@�@�X����ԏ�̉�������@�@�@�@����
�@�@�H���␅��̐Α��G��T�@�@�@����
�@���͍��A����̋�W��T���Ă���B�o��̒��ɖ����T�肽�����炾�B���X��o�ŎЂɂ��Ȃ��̂ŁA�_�c�ӂ�̌Ö{���ɍs���Ă݂悤�Ǝv���Ă���B
�@�o��������Ȃސl�̒��ɂ�����t�@���͑����A�㌎�ɂ́A�ɍ��ۂŁu������o����v���J�Â����B
�@���ӔN�ɋC�ɓ������Ƃ����ɍ��ۂɂ́A�L�O�ق�����A���̗L���ȃN���l�R����������̊G�u���D���v���W������Ă���B
�@����̐��܂ꂽ���R�ɂ͖��y���p�ق�����A�����{���ɂ��|�v������p�ق�����B
�@�Z��قǏo���������A���{��A���ʉ���͂��߁A�X�P�b�`�A�ʼn�A�{�Ȃǐ��X�̍�i���W������Ă��āA�S�𑨂���B�Ԃ������𒅂������̊G�̑O����́A���ꂪ�����B
�@�����������Ƃ̗��̒��ŁA����̐��X�̍�i�����܂ꂽ�B���̍�i���珗���ɑ���v���ƐS���`���A�������邩�炩�A�N��ɂ�����炸���p�ق�K���l�͑����B
�@�܂��A����̓}���h������e���Ă���B�N�ɏK�����̂��낤���B�m�肽�����̂��B
�@����Ȃӂ��ɂ��āA���́A��������Ƃ��Ȃ��l�E�|�v����ɁA�ǂ�ǂ�S�������Ă�����Ă���B
�@������ɐ����āA����Ɖ���Ă݂��������Ƃ����v���B�s���͐�������Ă��A�S�͎��R�ł���B����Ȑ����������Ă݂����B
�@�@����̊����}����������Âԁ@�@�[�]
�@
�@���䎛�E�G������Ă��Ă��A������������������|�����̒��̕F�T���C�ɂȂ��Ďd���Ȃ��B�����A������x���̊G�ɉ�����ƓX��K�˂����x�݂ł������B�������́A����ׂ����Ă���j���ɕ����ƁA���j�ȊO�͉����ԊJ���邩�킩��Ȃ��ƌ����B
�@�|�v����́A������܂��܂�����Ȃ��Ȃ����B
�@�@�����ĂȂٓ�����ɖ��ā@�@�[�]](vimgtext165.gif)
![�@�@��z
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���c �[�]
�@�}���V�����̏W���|�X�g����X�֕��̑������A�����ɖ߂����B
�@��ʁA��ʁA�ǂ����炩���m���߂�B��Ԑ�ɓǂނ̂͗F�l����̕ւ�B�K���ɂȂ��Ă���B
�@�I��킯�Ă���ƁA����H�Ǝv���������������B���Ȃ����ƁA���ԍ��͍����Ă���̂ɉ䂪�ƈ��ł͂Ȃ������B�c����������������A�Ƃ̎莆�����ꍞ��ł����肷��ꍇ�͂��邪�A����Ȃ��Ƃ͒������B
�@�悭�悭����ƁA�\������}���V�����̓��ԍ��������Ă���B�z�B�l�����ԍ������ʼn䂪�Ƃ̗X�֎ɓ����̂́A�������Ȃ��̂��B�e���̈�K�ɂ���W���|�X�g�̕\�D�Ŋm�F���Ăق����B
�@�ŋ߂́A�p�[�g�̔z�B�l�������Ă��邪�A�p�[�g�ł����Ă��A�v���ӎ����~�����B
�@�́A���c�J�́u��k��v�ɏZ��ł����B�g�ѓd�b��[���̂Ȃ����ゾ��������A�X�֕��͑����������ł���B����ł��A�莆�ɏ����ꂽ�䂪�Ƃ̏Z�����u�k��v�Ə�����Ă��Ă��A�u���k��v�ł��A�����Ɠ͂����B
�@�X�Lj��͈�x�T���Č�����Ȃ������X�֕��������A��A�����ɂ܂��A�T���Ȃ������B�����炱���䂪�ƈ��̏���������Z���ł��A�k��ɂȂ���A�\�Ȍ���T���ē͂��Ă��ꂽ�̂��B
�@�Z���𐳂��������Ȃ��͈̂�������ǁA�����ɓ͂���v�����������Ďd��������̂��v���B
�u���c����A���̕ӂ�ɍŋ߈����z���Ă����ƁA�Ȃ����Ȃ��v
�@�ƁA�x�e�����Lj����A�����Ă������Ƃ�����B
�@����̌�z���ǂ����悤���ƍl�����B�tⳂ����ċǂ̃|�X�g�ɓ����A���o�l�ɖ߂邾�낤�B�c�l������@�ւȂ����ł��������A���o�l�͌l�ł���B�����͑���ɓ͂��Ă���A�ƐM���Ă���ɈႢ�Ȃ��B
�@���͎莆�������y���݂��A���炤���������m���Ă���B������������������Ȃ����A��M�Y���ĊǗ��g���ɑ������Ƃɂ����B�g���Ȃ�ΑS���Z�l�̖��낪���邩��T����Ǝv�������炾�B
�@�Ǘ��g���̘A���|�X�g�ɁA��z�̗X�֕�����ꂽ�����B
�@�O�o����A���āA�X�֕������A�����ɓ������B�莆�������̂悤�ɑI��킯�Ă���ƁA�`���V�Ɍ������āA�������Ɏ菑���̕�����������B
�u�������|�X�g�֓������������������́A���̂j���̂��̂ł����B���������܂Ŗ����A���͂����邱�Ƃ��ł��܂����B���肪�Ƃ��������܂����v�ƁA�Ǘ��g������ł������B
�@�킴�킴���ʂ��A���Ă��ꂽ�̂��B�莆�����q�ɂȂ炸�ɂ悩�����ƁA���S���Ă���ƁA�d�b�̃x������A��b��������������B
�u�j�ł������܂��B���̂��т́A���e�ɂ��肪�Ƃ��������܂����B�莆���܂����v
�u���Ă��˂��ɁA�d�b�����������������ł��v
�@�悩�����A�����������ɂȂ�Ȃ��āB
�@�@�t�̕��@�͂��Ăق����@���̂���](vimgtext200.gif)

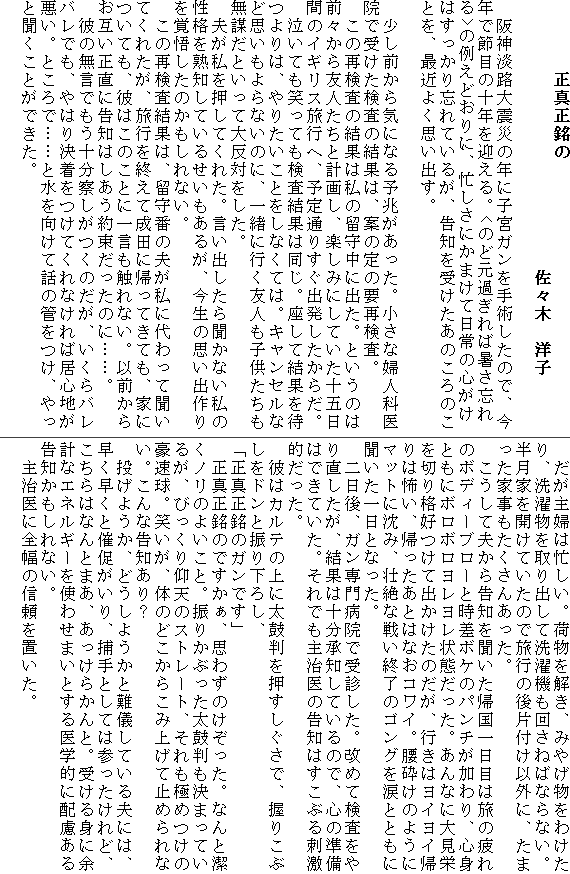
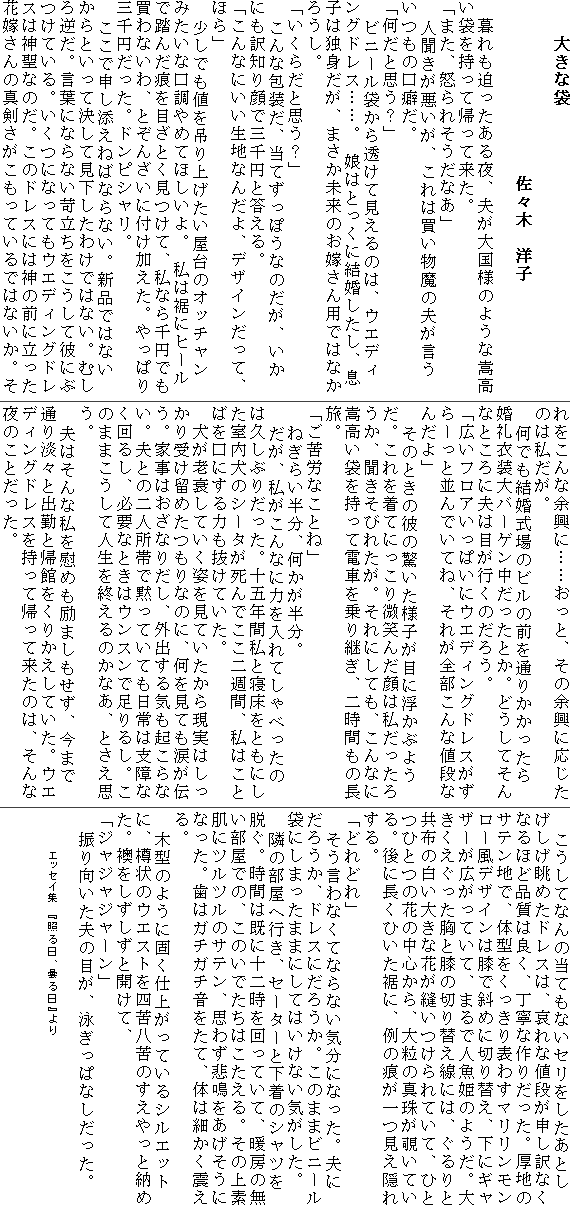
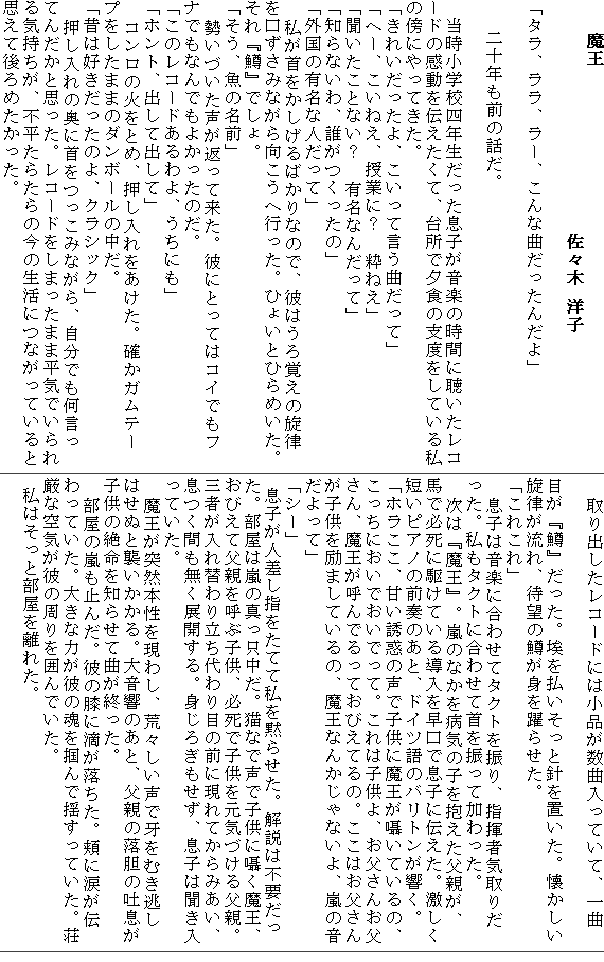
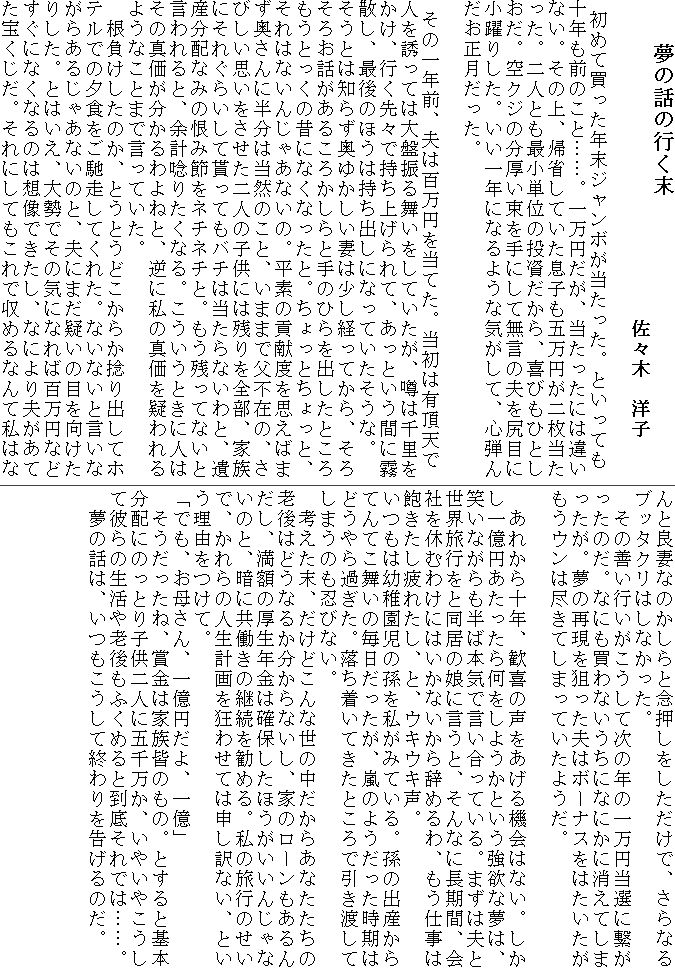
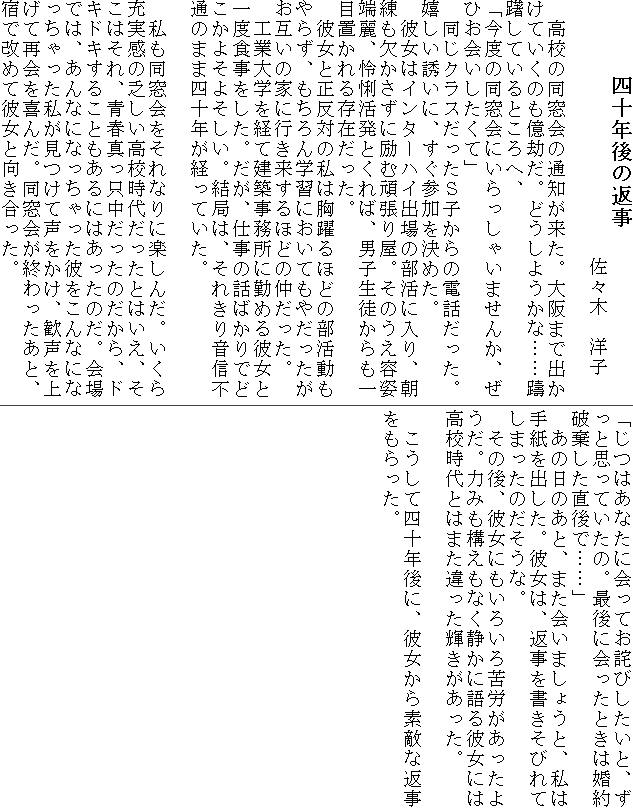
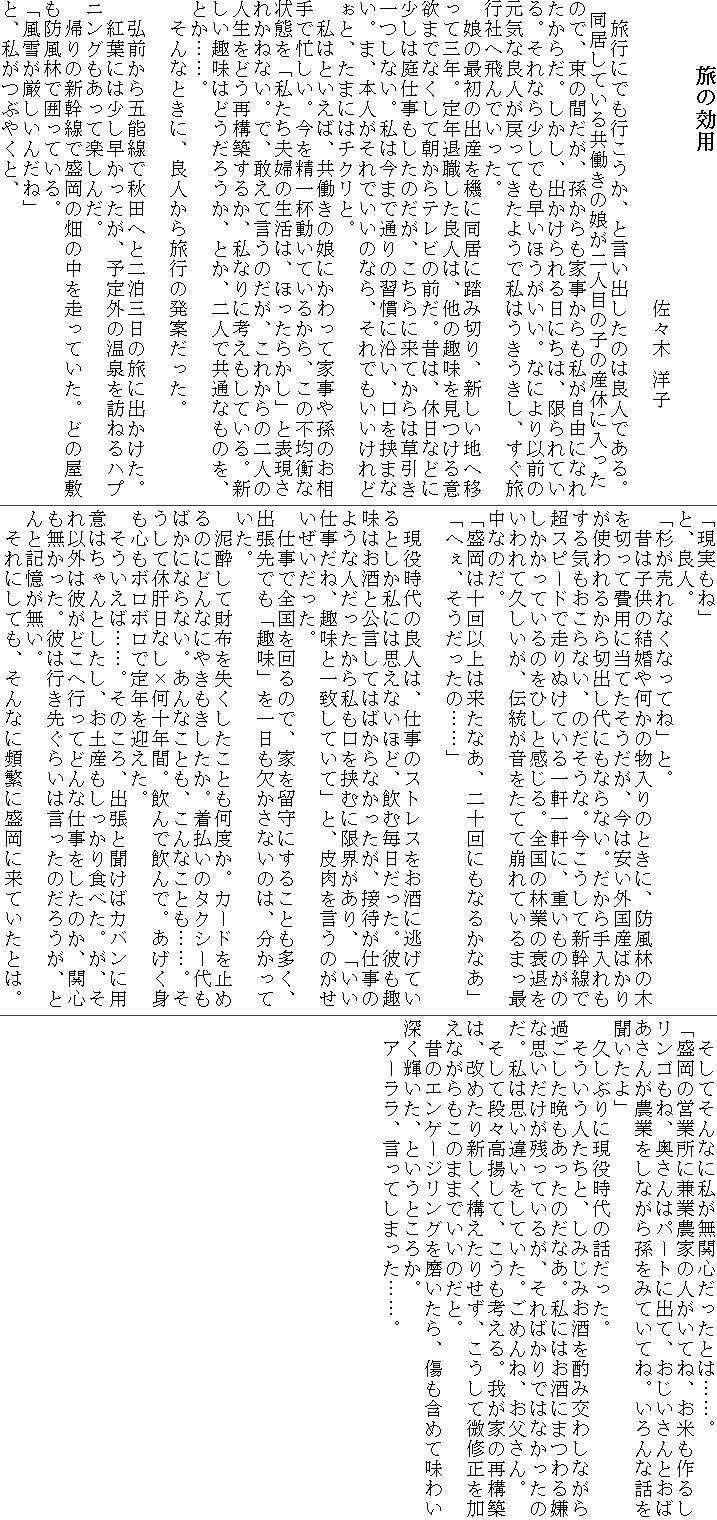

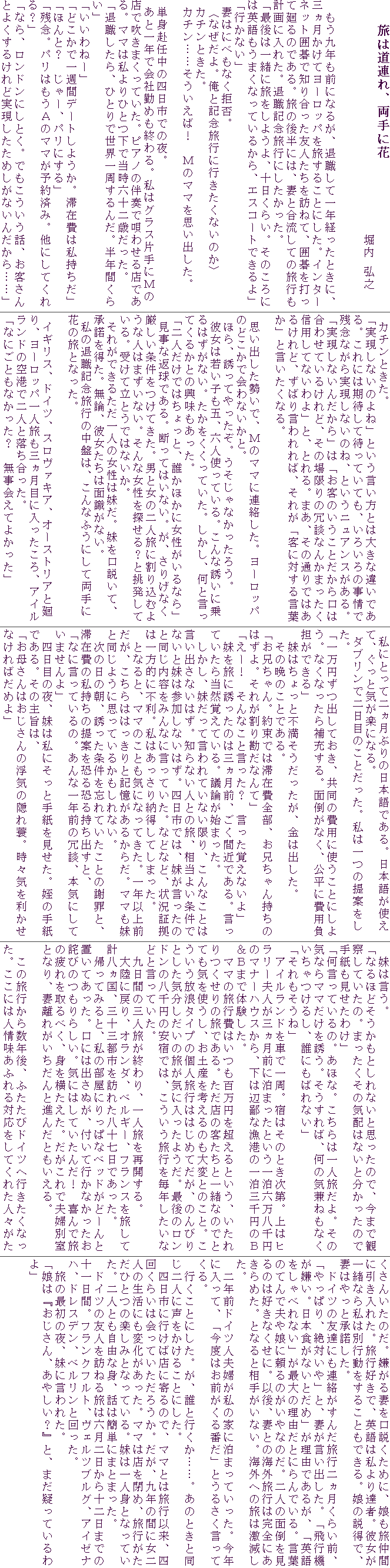

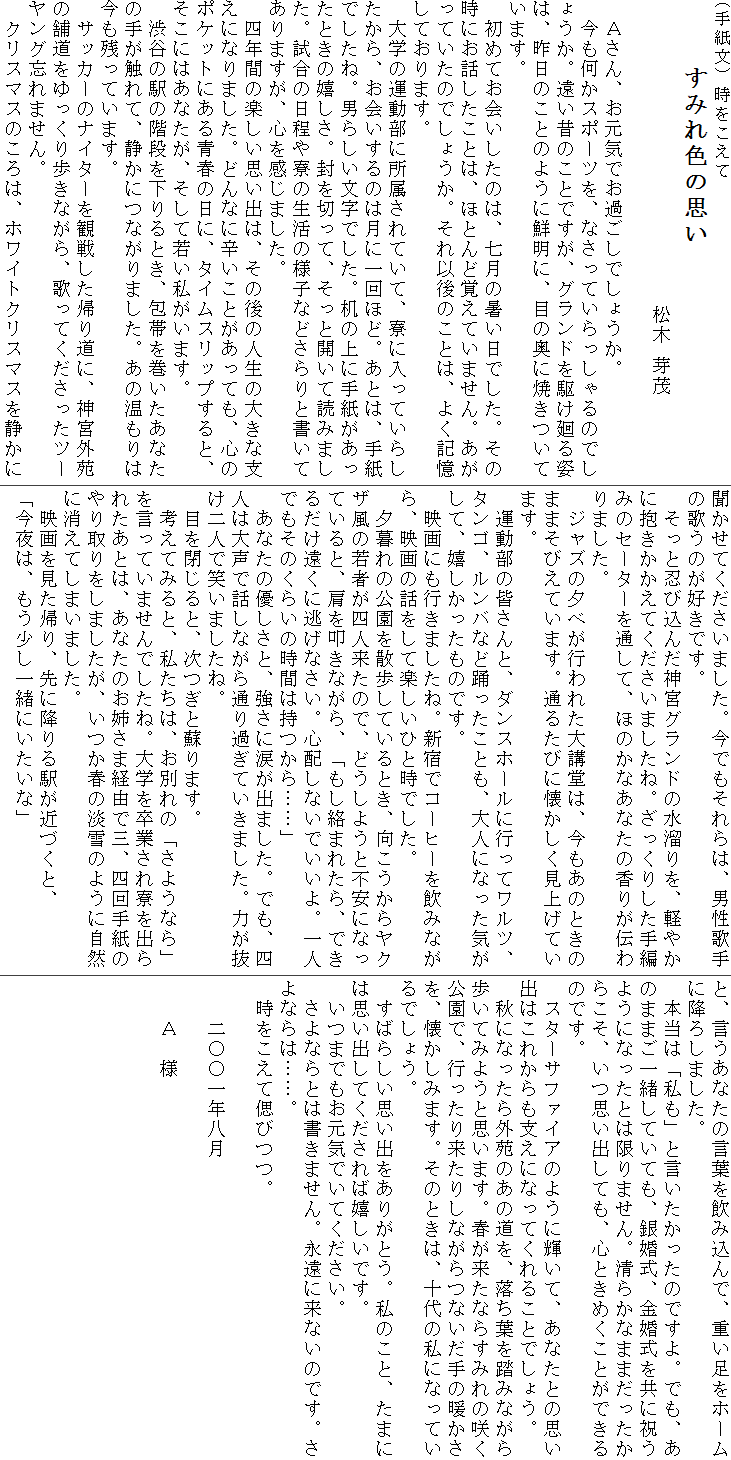
![�@�@�@�Y��Ȃ����@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���� ���
�@�@�@�@
�@�I��L�O���B���͐푈�̖{���̈Ӗ����悭�킩��Ȃ����w�Z�̒�w�N���������A���̓��A�����\�ܓ��͌����ĖY��Ȃ��B
�@���a��\�N�܌���\�ܓ��A��B�z�c�ɓ����Ă��炭����ƁA���ɋN�����ꂽ�B��P���Ђǂ��Ȃ肻�������璅�ւ���悤�ɂƌ�����B���̔N�̉��x�ڂ��̓����̑��P�������B
�@���́A���]�Ԃɉו���ς݁A��́A��ɂ��Ȃ�Ȃ����̒�Ԃ��A�����߂��������B���͂��������l�ɂȂ��̎���ɂ���A���̌�ɂ��ċ}�����B
�@�����@�̕ґ����߂Â��Ă���B����ŁA�������L�����ƌ���B�����ďĈΒe���o���o���Ɨ����Ă���B���̂��ƁA�a�Q�X�����e�𗎂Ƃ��B�R���鉊�ŕӂ�͖��邢�B
�@���ȂȂ����߂ɁA���ɂ����Ȃ����߂ɁA�Ђ����瓦�����B
�@�L�������ςɍs���ƁA���͂̌������ԁX�ƔR������Ă����B��C���M���B�����M���������A�ו���ς傫�ȓ���Ԃ����̑O�𑖂��Ă����B����������Ă��Ȃ��̂ɑ����Ă����B
�@�Ƒ��Ō����A�吨�̐l�����ƈ������������B
�@���A�ڊo�܂��ƌ��n�������肪�Ė쌴�������B�䂪�Ƃ́A�Y�ɂȂ��Ă����B�c�����̂͒�̐Γ��Ă����B�h�̒��ɂ�������Ȕ��ẮA�Ԓ��F�ɂ����āA�����Ԃ��Ă����B
�@���̂��������ɏĂ������̂��]�����Ă���B���Ȃ��悤�ɂ��āA�悯�ĕ������B
�@���̑��P�̌�A�Ƒ��͉��̂Ő�t�݂̍ɑa�J�����B�������͊w���a�J�����Ă��Ȃ������̂��B
�@���قnjo�����ċx�݁B�c�ɒ��Ɉꌬ�����Ȃ������ɍs�����B�����ȓX�́A�q�ǂ��ň�t�������B
�@�X�̎�͈�l�ʼnc�Ƃ��Ă��āA�q�ǂ������Ɂu���o����v�ƌĂ�Ă����B
�@����Ə��Ԃ������Ƃ��A���o���A
�u�\����A�V�c�É��̂��b������̂ŁA���炭�҂��Ă��Ăˁv
�@���������ƓX�̉��ɓ����čs�����B���Ȃ蒷�����Ԃ��߂������A�X�ɖ߂��Ă��Ȃ��B
�@���ꂩ���A�u���o���[��v�Ɛ����������B����ƁA
�u�����͋A���āI�@�����A�ߌ�͂��x�݁v
�@�������́A���܂Ō������Ƃ��Ȃ����o����̌`���ɋ��������A�d���Ȃ��ƂɋA�����B
�@���̖�A�푈���I�������Ƃ�m�炳�ꂽ�B���́u�푈���I���Γ����ɋA���v�ƁA��B�|����P�͂����Ȃ��̂��B
�@���̓����A�����\�ܓ��������B
�@�푈�͐�Ɍ����B�e���r��f��̐푈�������B����ȑ̌��͎q�ɂ����ɂ����������Ȃ��B�̌��L�����ꂪ�ŏ��ŁA�Ō�ł���B](vimgtext92.gif)
![�@�@�@�|�X�g�ɃA�C�X�N���[��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���؉��
�@��b������ƁA�e�����F�l����ł������B
�b�̒��ŋ��������Ƃ���B�����ޏ��ɏo�����n�K�L�ɁA�X�ǂ̕tⳂ����ē͂����Ƃ����̂��B
���e��v��ƁA
�w�|�X�g�ɃA�C�X�N���[���𓊂����l�����āA�n�K�L������Ă��܂��܂����B�o������肫�ꂢ�ɂ��Ă��͂����܂��x
�@�M�����Ȃ��悤�Șb�ł���B
�@�ޏ��͎��ɉ�Ƃ��ɂ��̃n�K�L�������悤�Ǝv���Ă������A�҂�����Ȃ��ēd�b�����̂��Ƃ����B
�u�ǂ߂�悤�ɂȂ��Ă�������ǁA�ǂ�Ȑl�̂�������Ȃ̂�����v
�@�X�ǂ���̕tⳂ̘b�́A���������B
�䂪�Ƃɓ͂����X�֕��ɁA�傫�߂̕tⳂ��\���Ă������B
�w�}���V�����̏W���X�֎�����N���W�b�g�J�[�h�̕s�ݔz�B�ʒm���𓐂ޔƍ߂��������Ă��܂��x
�������e�ɂ́A�т����肵���B�Ɛl�͎��l���`�̌��N�ی���^�]�Ƌ����U�����A�X�ǂŕ��������A���̃J�[�h���g�p����̂��������B�s����̂�h�����߁A
�w�s�ݔz�B�ʒm���ɂ́A���l�̖��O���J�^�J�i�ŋL�ڂ��Ă��܂��x�Ə����Ă������B
�@�M�����Ȃ��Ƃ������́A�I���I�����\�̉��s���鎞�ゾ���炱���A���肤��Ǝv�����B�����f�����ƍ߂��B
�@�|�X�g�ɃA�C�X�N���[���𓊂������ɂ���A�s�ݔz�B�X�ւ̕s����̂ɂ���A�܂��A���X�ƈ������l������̂ł���B
�@�x�@�����ł͂Ȃ��A�ߏ������͂������A�������ڔz��p�S���邵���Ȃ��B
�@���ȍ��ɂȂ������̂��B](vimgtext204.gif)

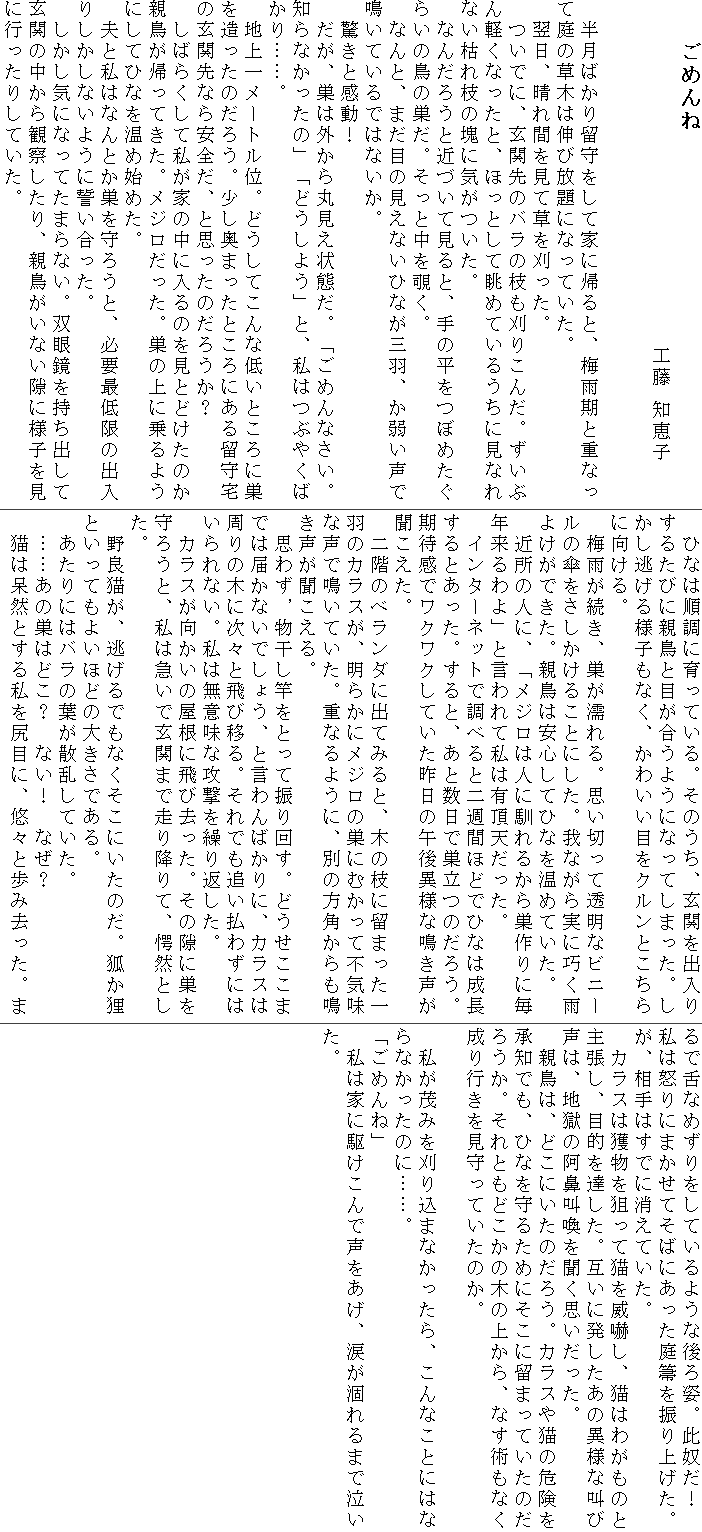
![]()

![]()
![�����C���𗚂��Ȃ����R
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����
�@�܂������\�ܓ�������Ă��܂��B���ȏ��ł́u�I��L�O���v�������ł����A�u�s��̓��v�u�s��L�O���v�Ȃ�s���Ɨ���̂����̔N��ł��B
�@���̓�����Z�\���N���o�����݂��A�푈�̐^�������ɐ������҂Ƃ��āA�����s�����Ȃ��z�����Q�������Ă��܂��B
�@�����~�ł��C���𗚂��Ȃ����R���A�����ɂ���܂��B�a�J�n�ł̑̌���Y��Ȃ����߁A���q�ɓ����o���������Ȃ����߂ɁB
�@���l�l�N�A���͏��w�Z�N�̉ċx�݂ɁA��̗��ł���ɑa�J���܂����B�O�N�ƈ�N�̖����ꏏ�ł����B
�@�ꂪ�A�Ԃ�V�������N�q�̒킽���ƁA�˂����A��đa�J���Ă����̂́A���N���߂��Ă���ł��B
�@�������̐��܂�̋����Ƃ����Ă��A�����ł́A�������́q�悻�ҁr�B
�@���̂���̏��w���݂͂�ȃI�J�b�p�������̂ɁA���͂��ł��o���đO�̖т���Ō���ł��܂����B����Ȕ��^�ЂƂł��A�݂�ȂƈႤ�Ƃ����ăC�W������Ȃ�āc�c�����̂悤�Ɉ��������āA�͂₵���Ă��܂������A���́A�ꂪ�u��������v�ƌ����Ă��ꂽ���^��ς��܂���ł����B
�@�̎s������������Ǔ~�͐Ⴊ�����A���͓��������Ŋ����Ȃ���Ȃ�܂���B�������͂��ꂾ���ł������܂����B
�@��̒��̓o�Z���A�������͉��ʂɂ����Ⴊ���Ƃ��Ȃ��āA�悭�]�т܂����B�������́A���̂��тɂׂ��������A��Ɋ��ꂽ�n���̎q�������͎w�����ď��܂��B��l���܂����́A�����ĂȂ����܂���B
�@�ᓹ�̐^�œ��������Ȃ��Ȃ�A䩑R�Ɨ����s�������Ƃ����A����������H������܂����B�S�̒��ł́u���������[��v�Ƌ�������ł����̂ɁB
�@�a�J��̏��w�Z�œ~�x�݂ɏo���ꂽ�h�肪����܂��B�ǂ��ƂɁu���x�ݒ��ɂł��邱�Ƃ�I��Ŏ��s����v�B
�@���z���C�ǁA���ܖ����ǂȂǂ�����A���͌�҂�I�т܂����B���͒n���̎q���ɕ�������̂��Ɗ撣���Ă��܂��܂����B
�@�ᓹ�Ŋ����ē]��ł͂Ȃ����ꂽ�艺�ʂ����ꂽ�肵����A�͂����Ŋ撣��c�c���ł́u���̃K���o���͂n�^���t�̐�����Z�������̂ł��傤�v�Ə��Ȃ���b���܂��B
�@�s��̔N�̏H�A���w��N�̎���������ɓ����ɖ߂�܂����B�Ƒ��ꏏ�̓����������Ăюn�܂����̂́A���̔N�̏t�ł����B
�@�푈�Ɋ������܂��̂͂�����������B���̂Ƃ��̑z�������������Ă��āA�������͌C���𗚂��Ȃ��̂ł��B](vimgtext42.gif)