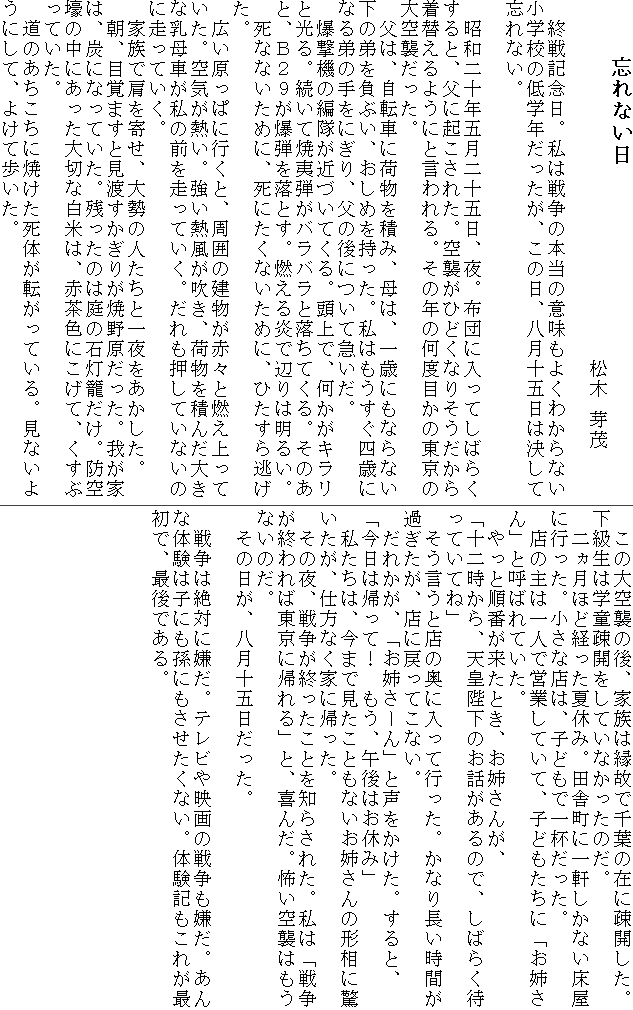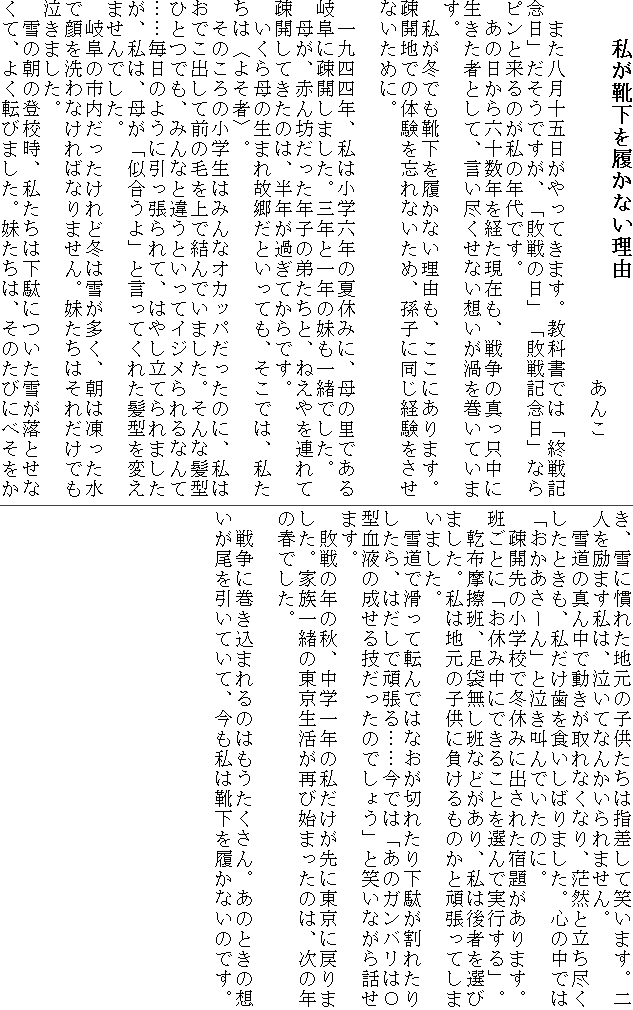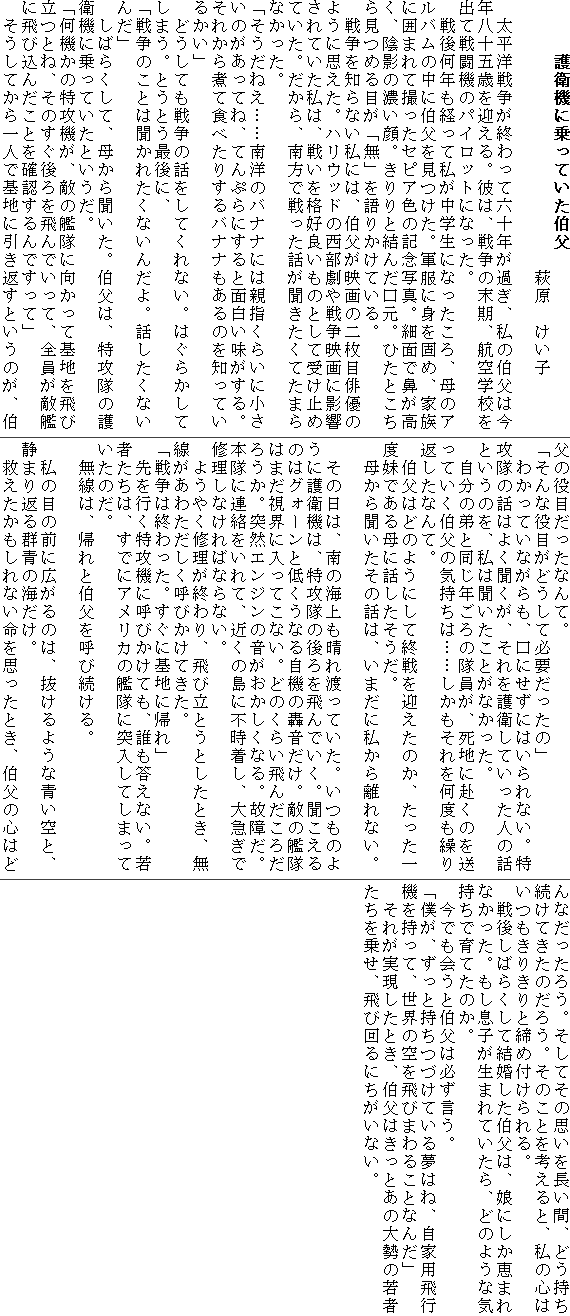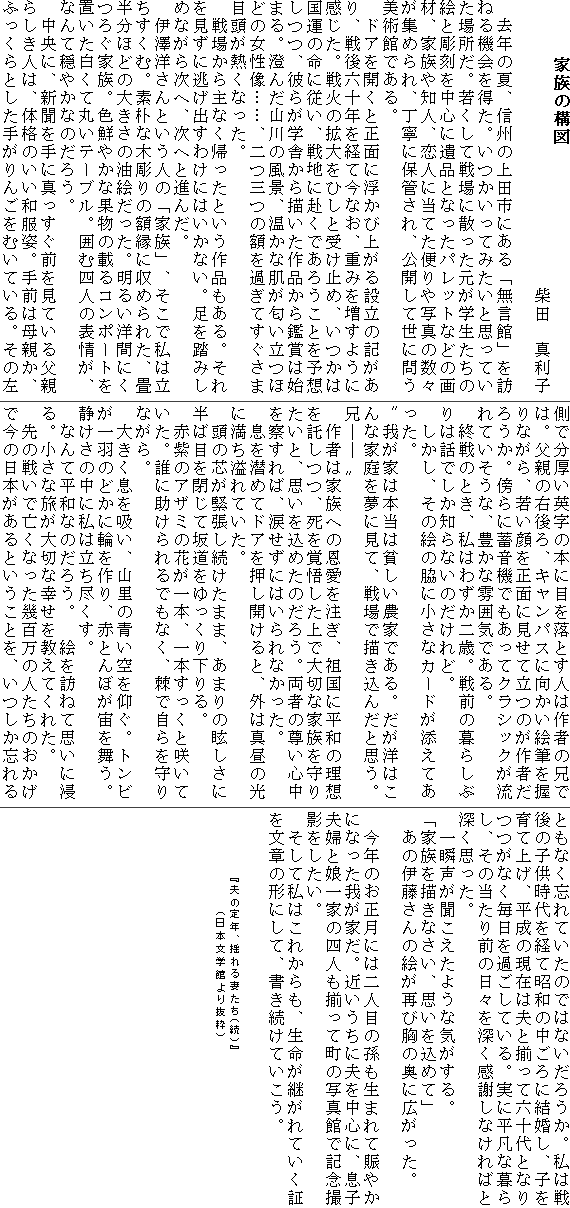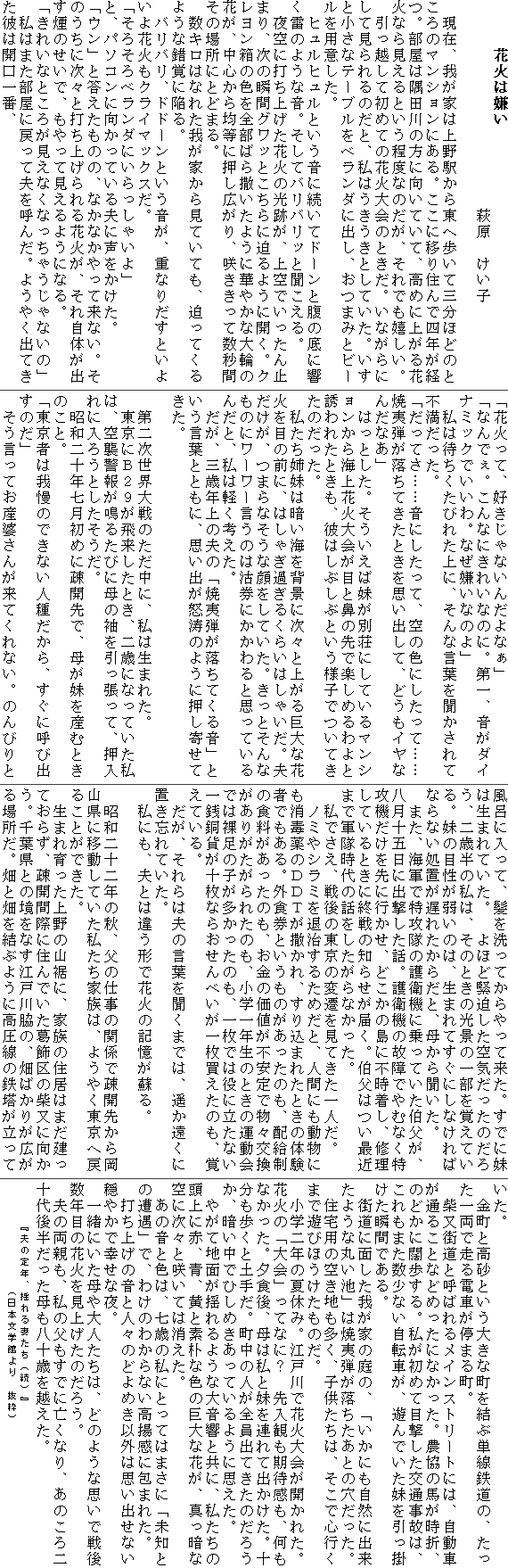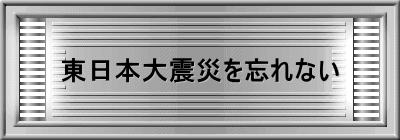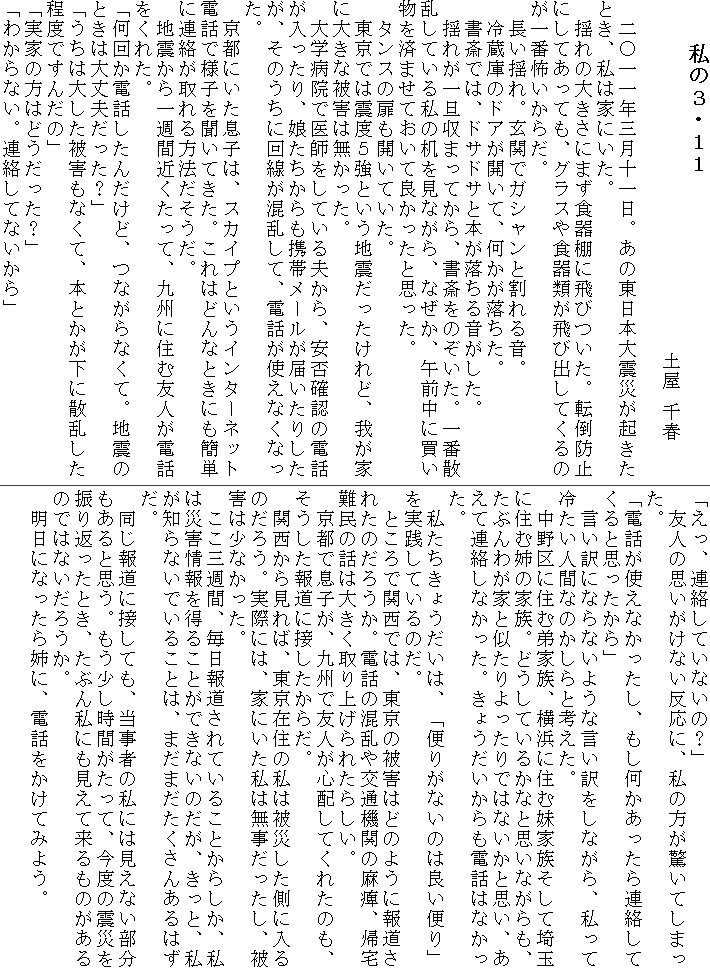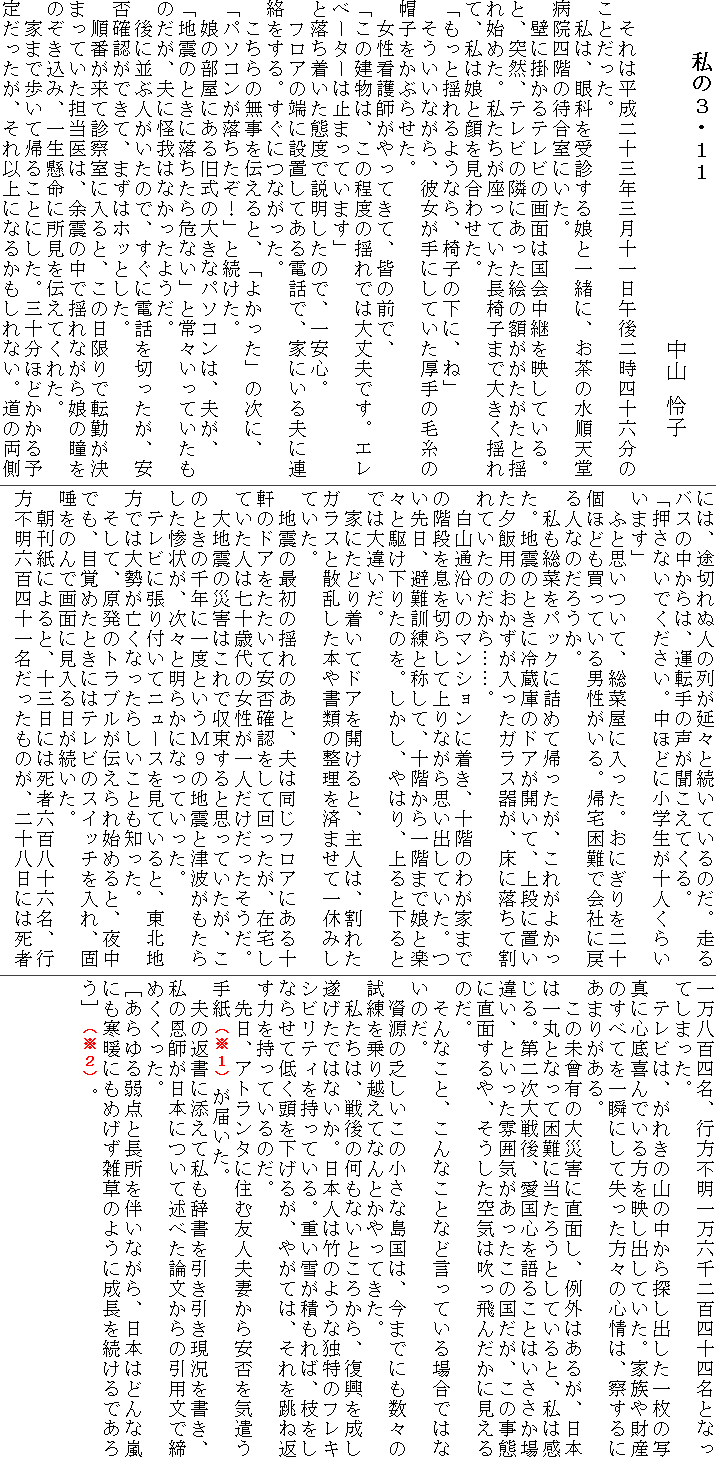|
|
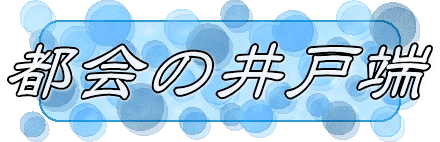 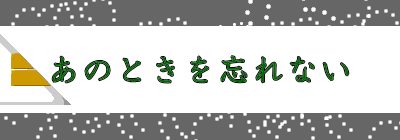 大戦後の風景へ 東日本大震災へ |
|||||||||
|
||||||||||
| ※1945年8月15日、第二次世界大戦が終わった。幼かった私たちの記憶はまだ鮮やかに残っています。 それがセピア色になってしまう前に、体験したことや感じたことを書きとめておきたい。 反戦を声高に叫ぶことはなくても、あの戦中戦後の生活を書きとめておきたい。 ※2011年3月11日に起きた東日本大震災。震度も津波も原発事故も……何もかもが想定外でした。 そのとき私たちはどう感じたか、そのあと私たちはどのように過ごしたか、そのことも記録しておきたい。 そう思って少しずつ書きためています。 |
||||||||||
 |
|||
| 私が靴下を履かない理由 あんこ | 護衛機に乗っていた伯父 萩原けい子 | ||
| 忘れない日 松木芽茂 | 家族の構図 柴田真利子 | 花火は嫌い 萩原けい子 | |
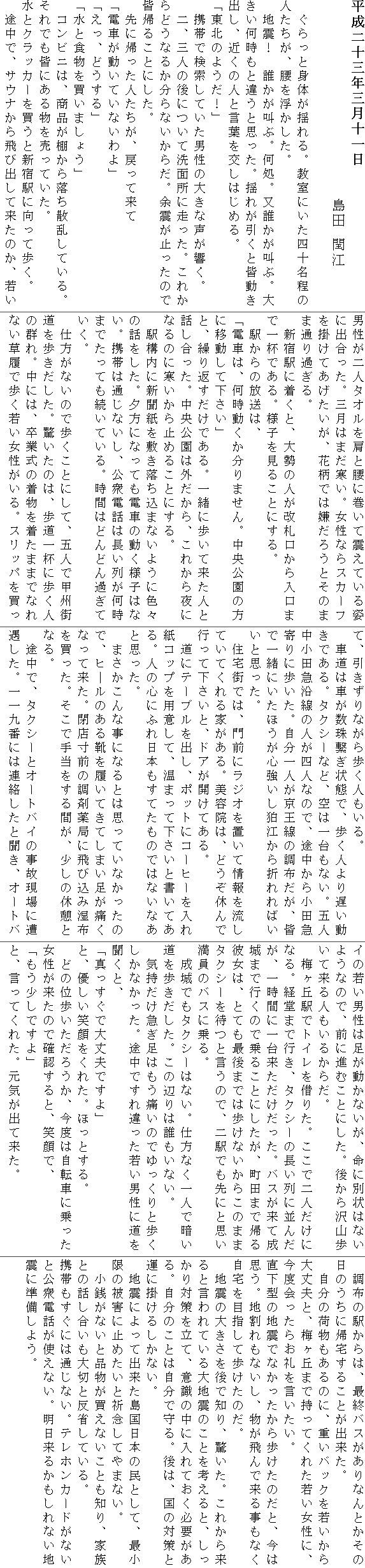 |