 |
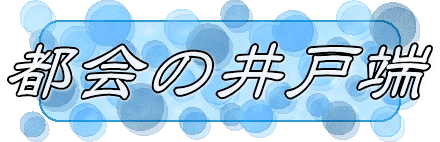 |
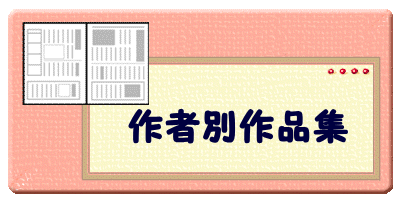 |
| あんこ | 北崎理子 | 工藤知恵子 | 小松なつみ | 小璃間けい |
| 佐々木洋子 | 篠宮亜季子 | 柴田真利子 | 島田閏江 | しらす・よみひと |
| 須釜敏子 | 土屋千春 | 中山怜子 | 掘内弘之 | 松木芽茂 |
| 萩原けい子 | 山本浩三 | (故)嶋岡忠 | のりすけ |

| 作者名 | 須釜敏子 (自己紹介へ) |
||
| タイトル | スイカとゆず | 紅葉狩りのおまけ | 菜の花 |
| 私の秋 | お花見 | 涙の山菜おこわ | |
| すみつかれ | いらっしゃい、お母さん | 思い出の庭 | |
| 眠れないホウレン草 | 帰郷 | 蜂の分封 | |
| 野鳥の楽園 | カラスと知恵比べ | ブナの話 | |
| 発展と衰退 | 野らぼう菜 | new! 薫風 | |
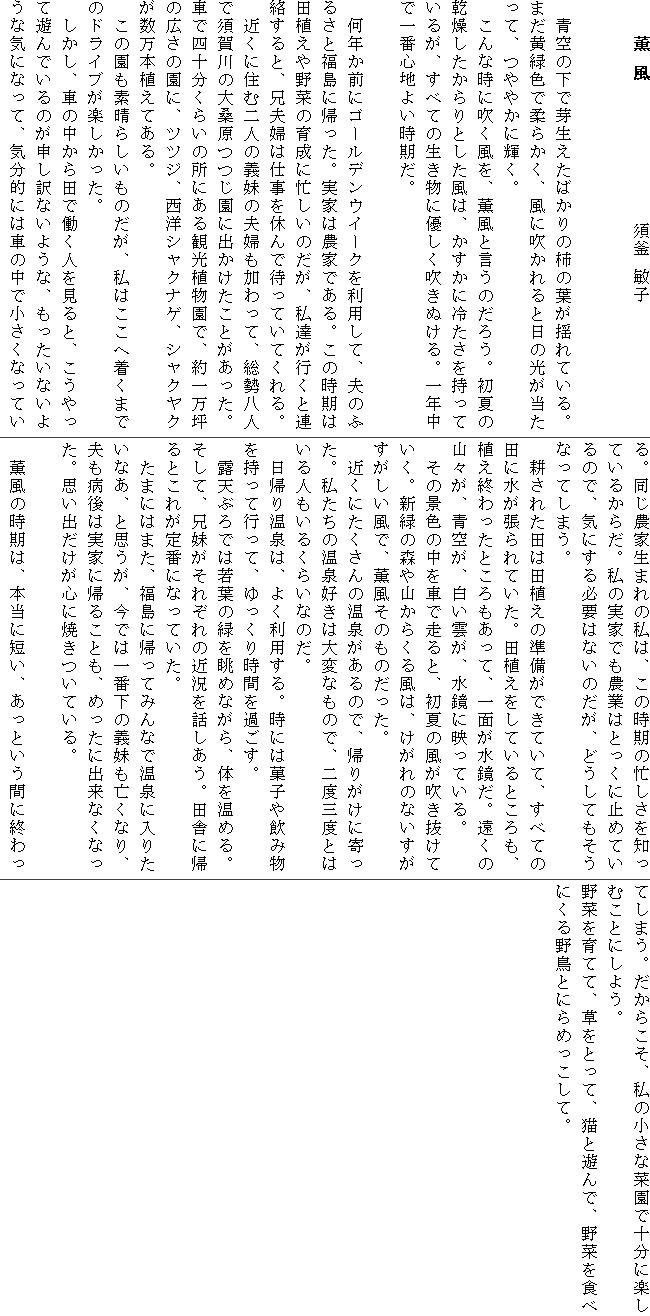 |
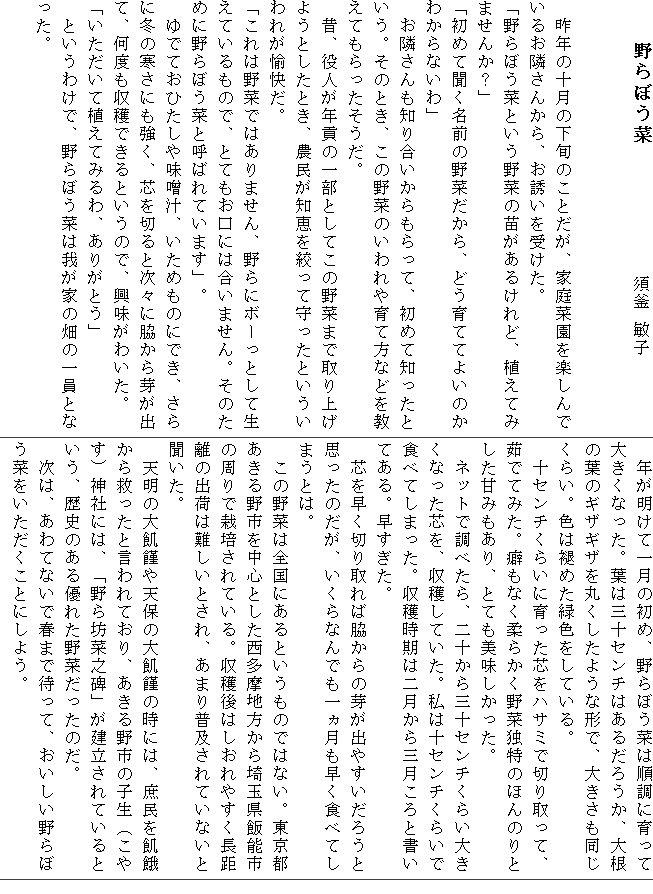 |
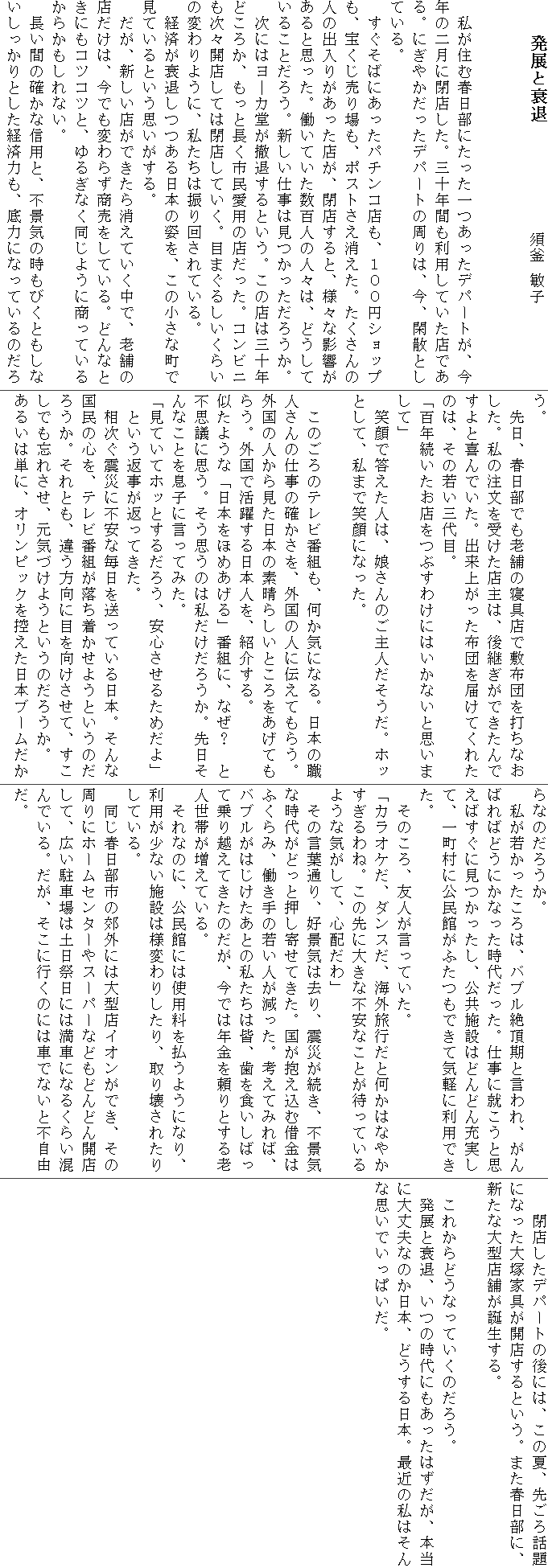 |
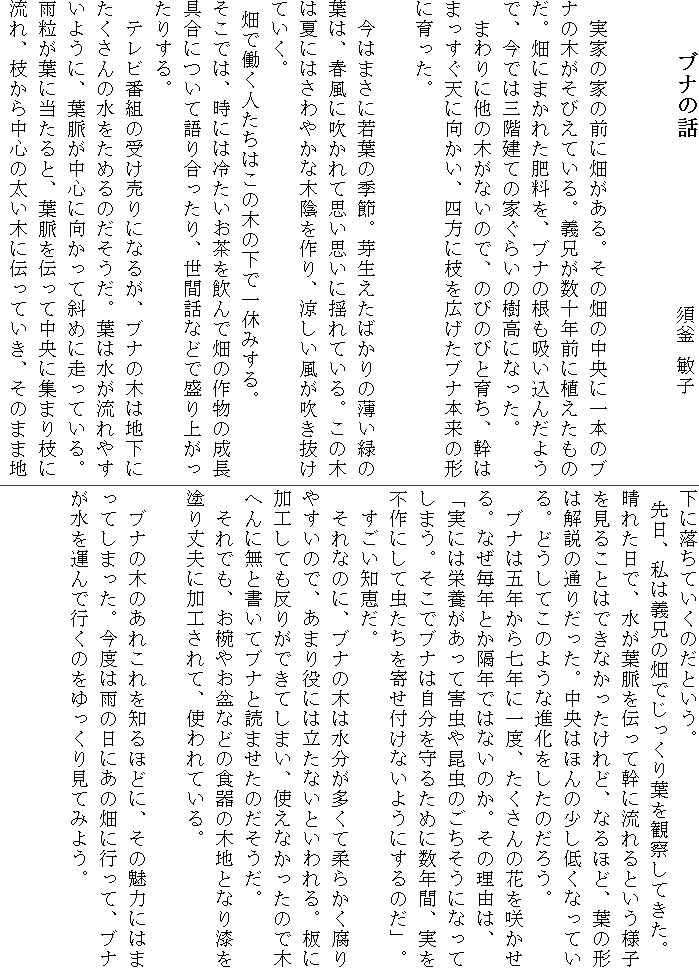 |
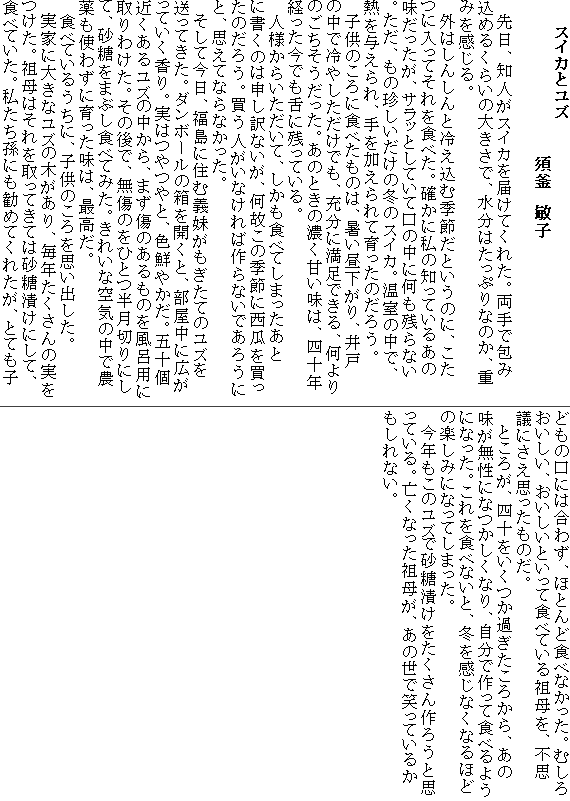 |
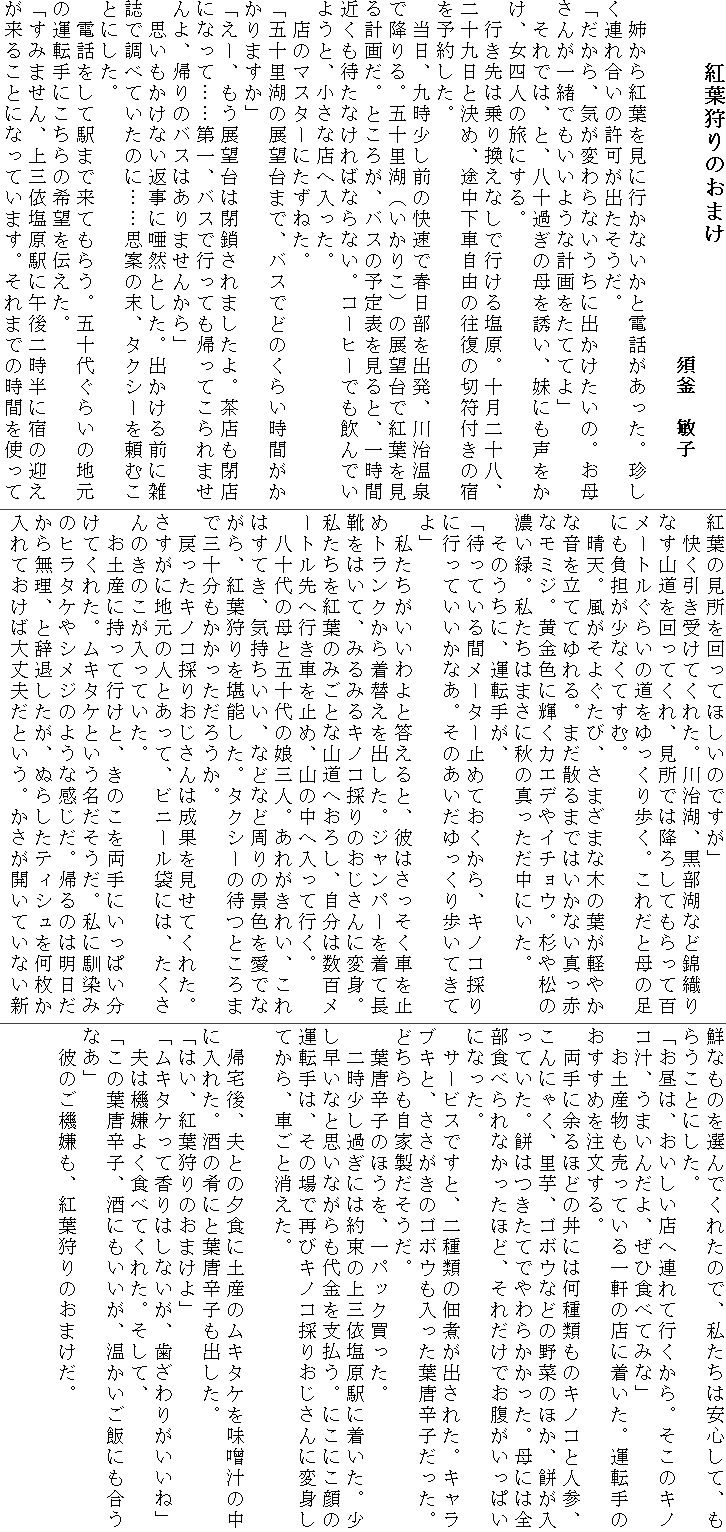 |
 |
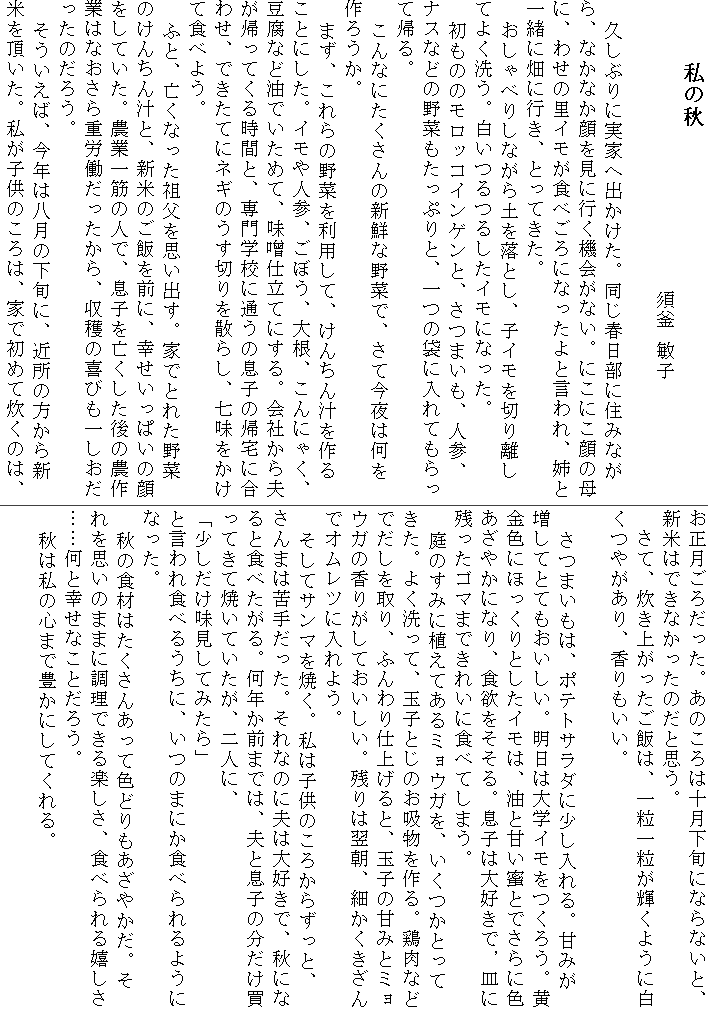 |
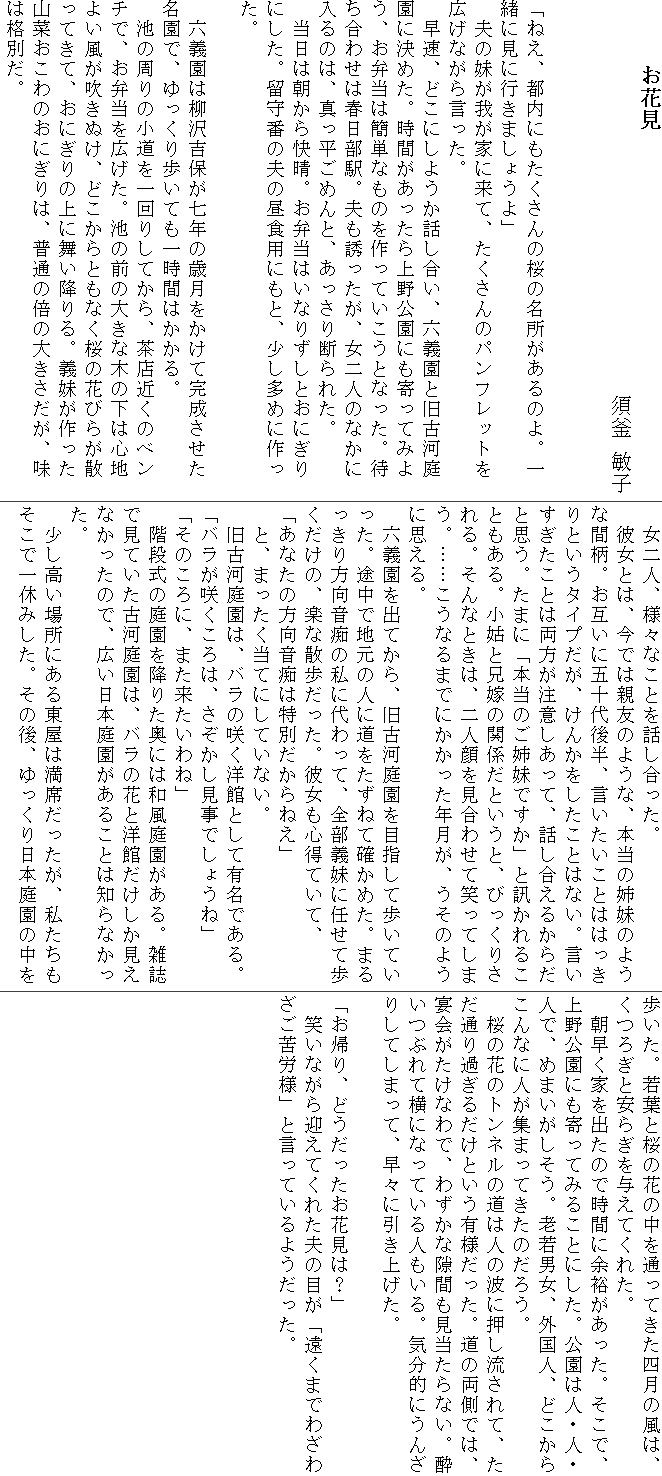 |
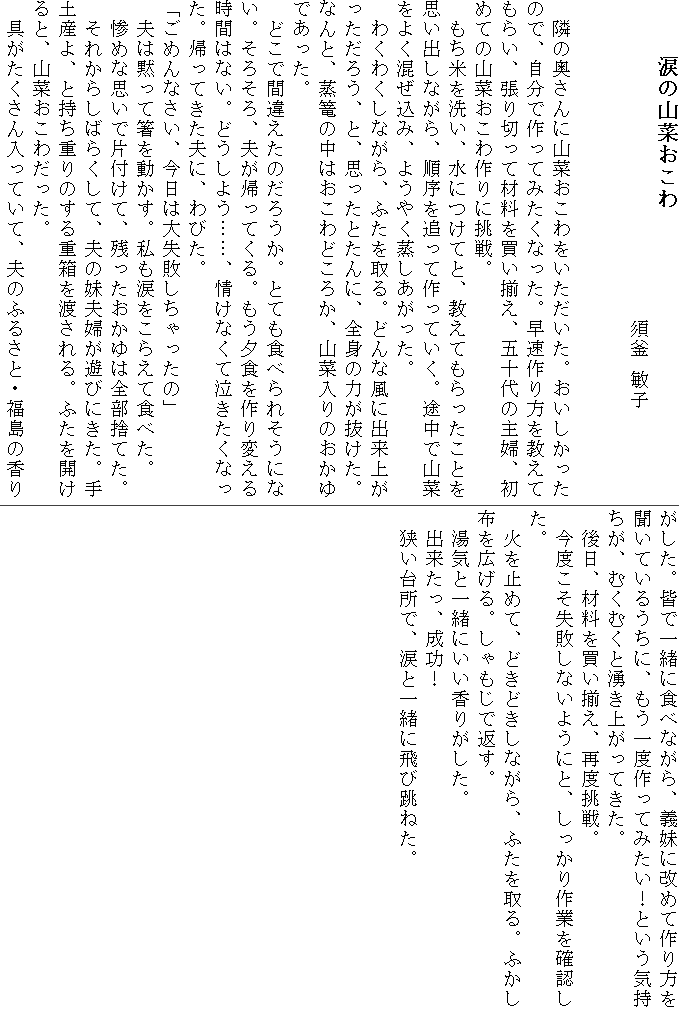 |
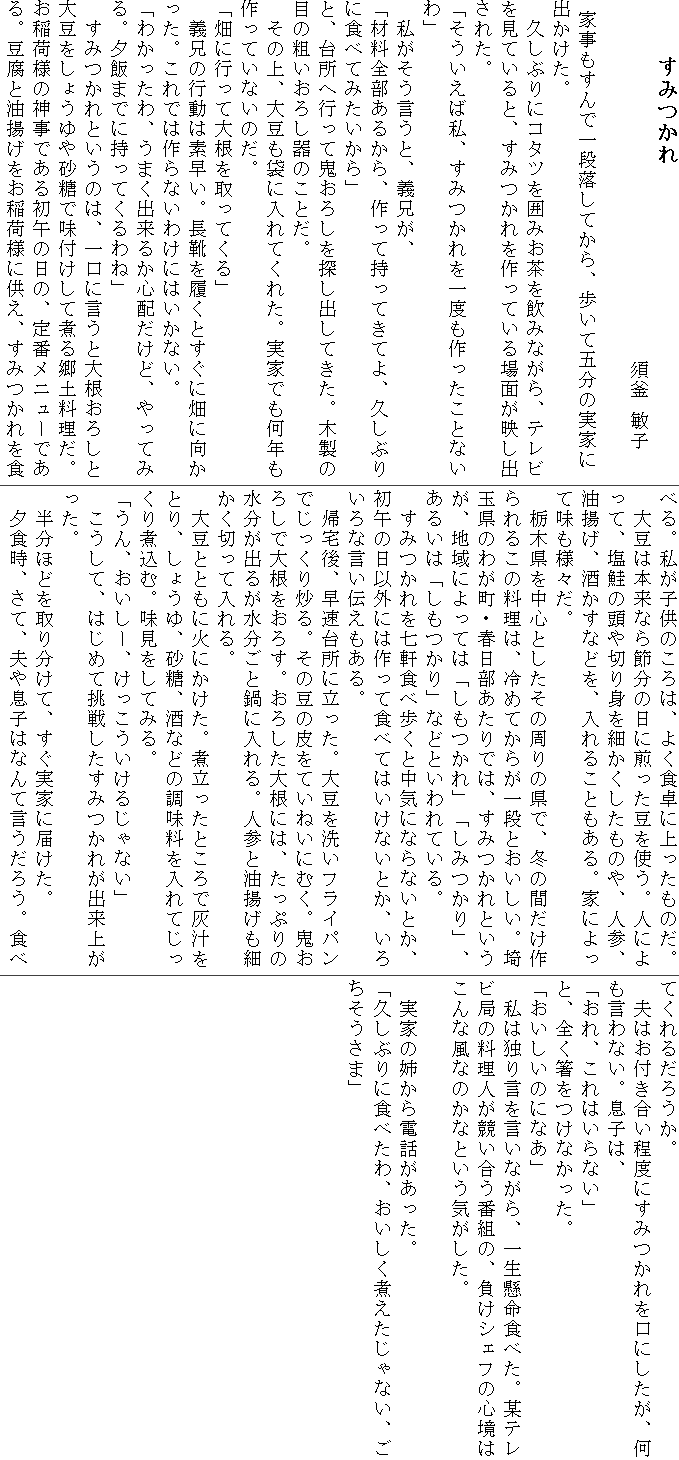 |
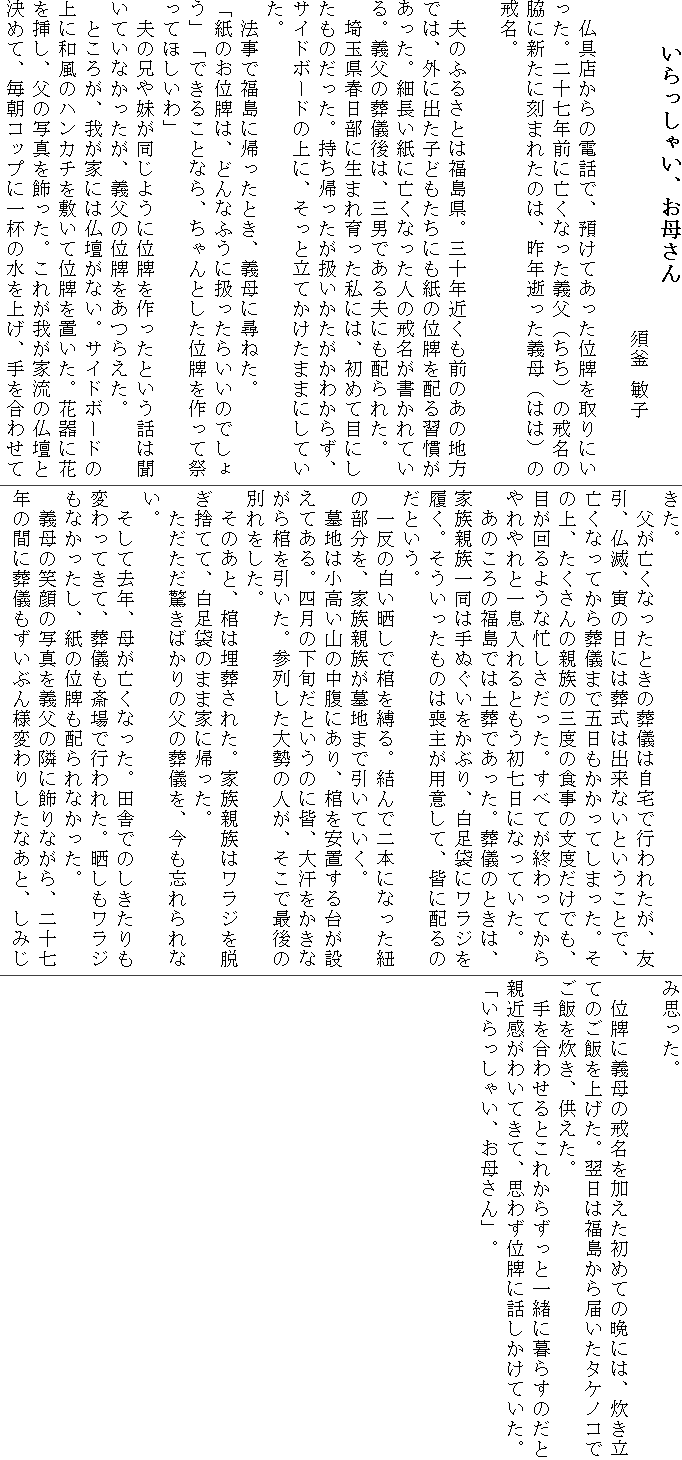 |
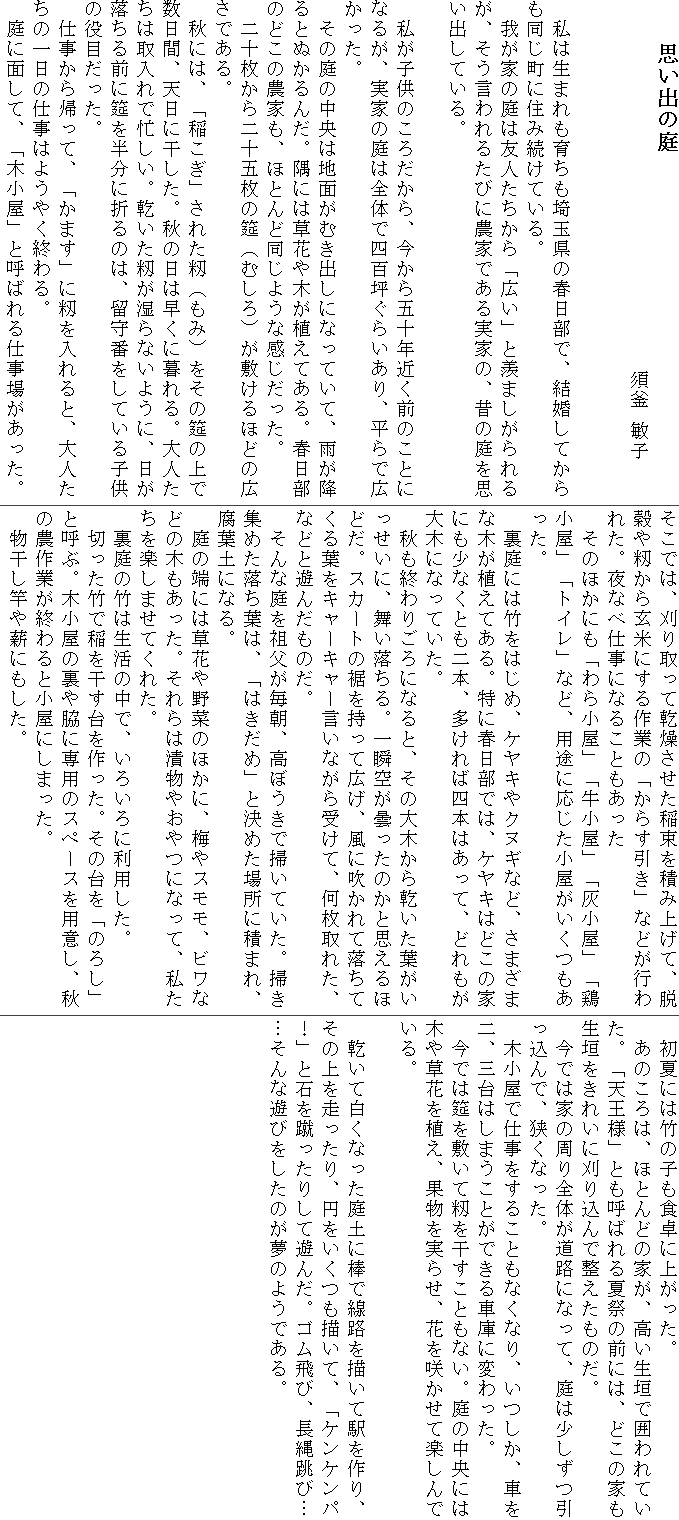 |
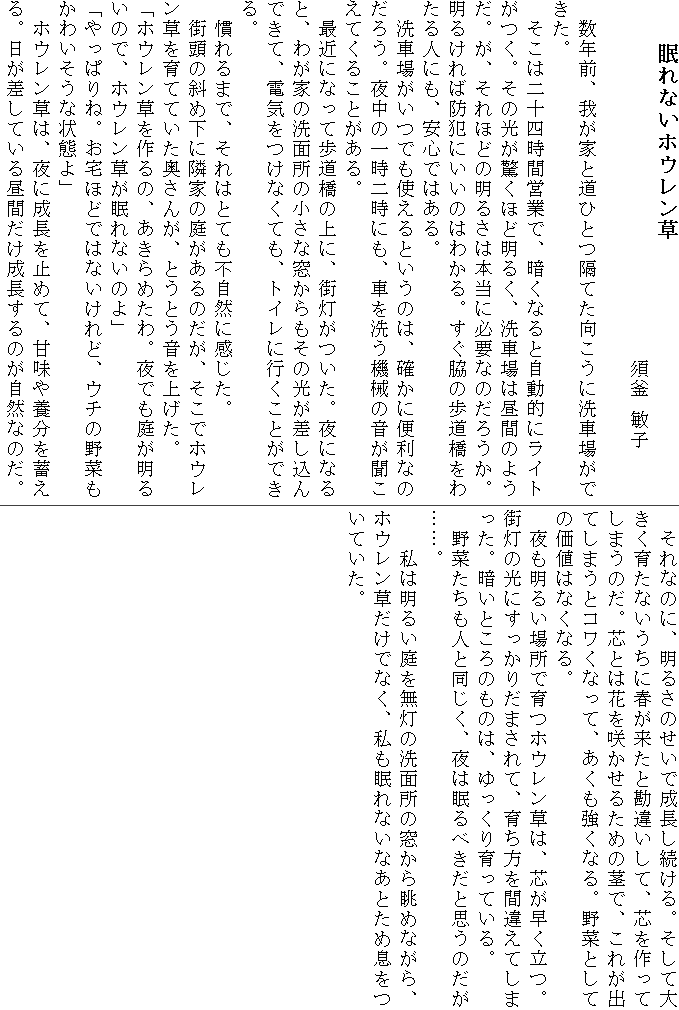 |
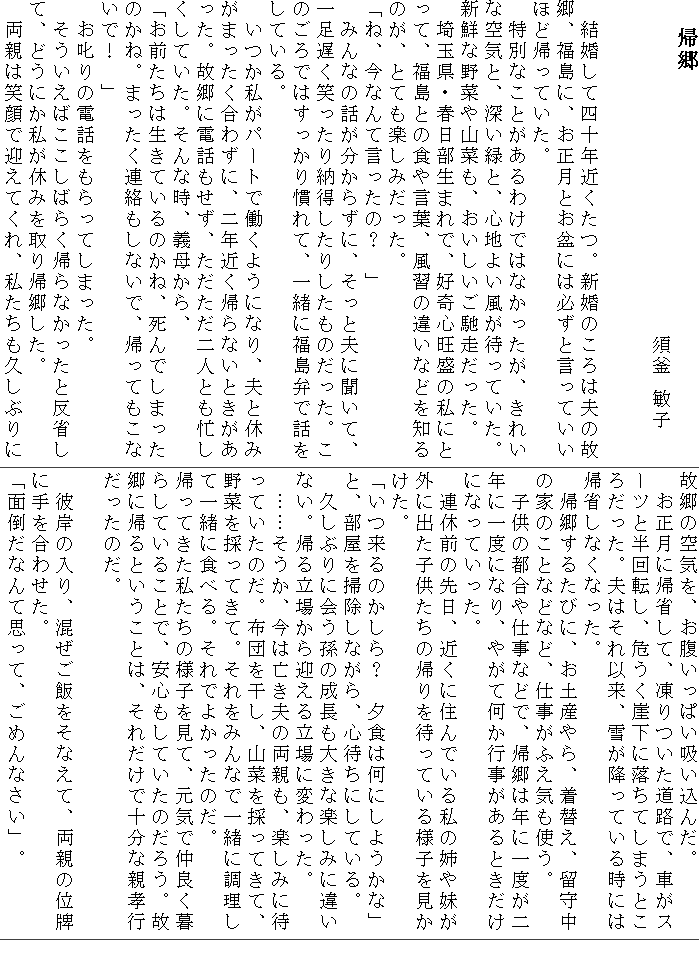 |
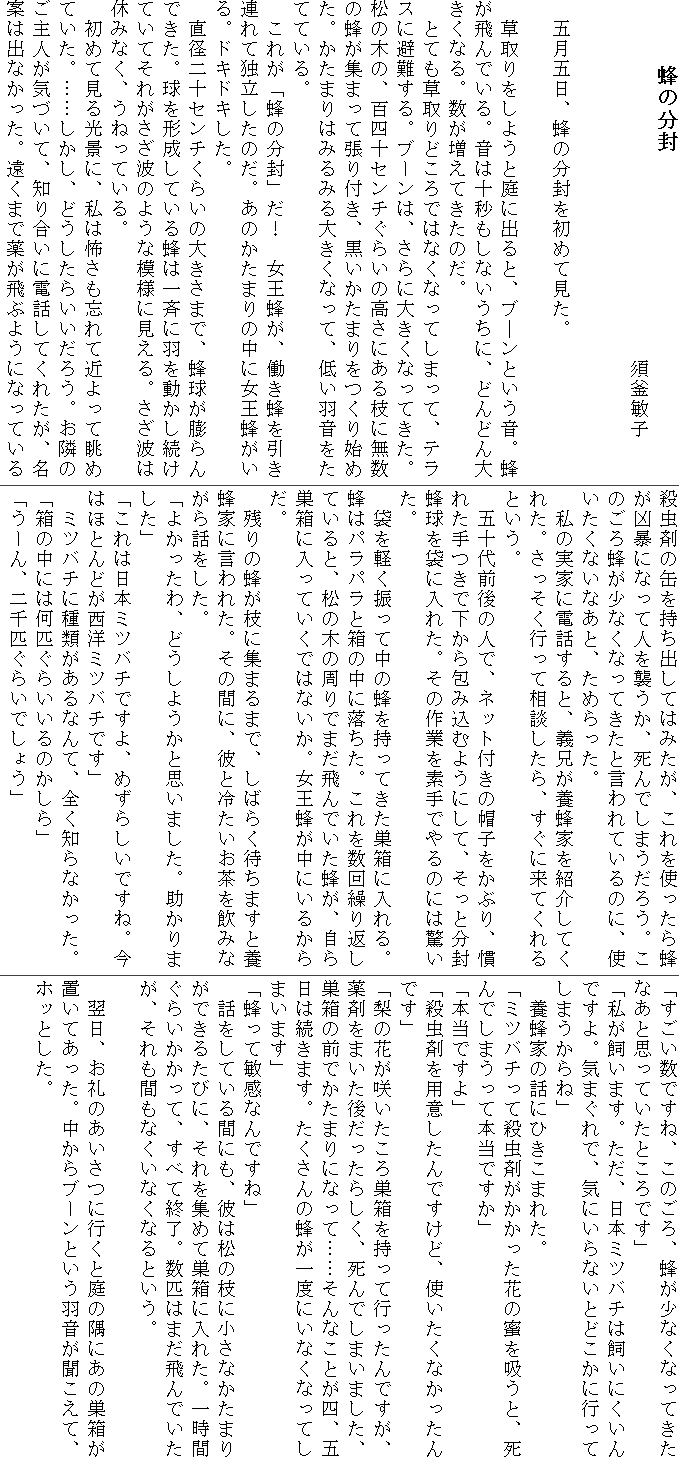 |
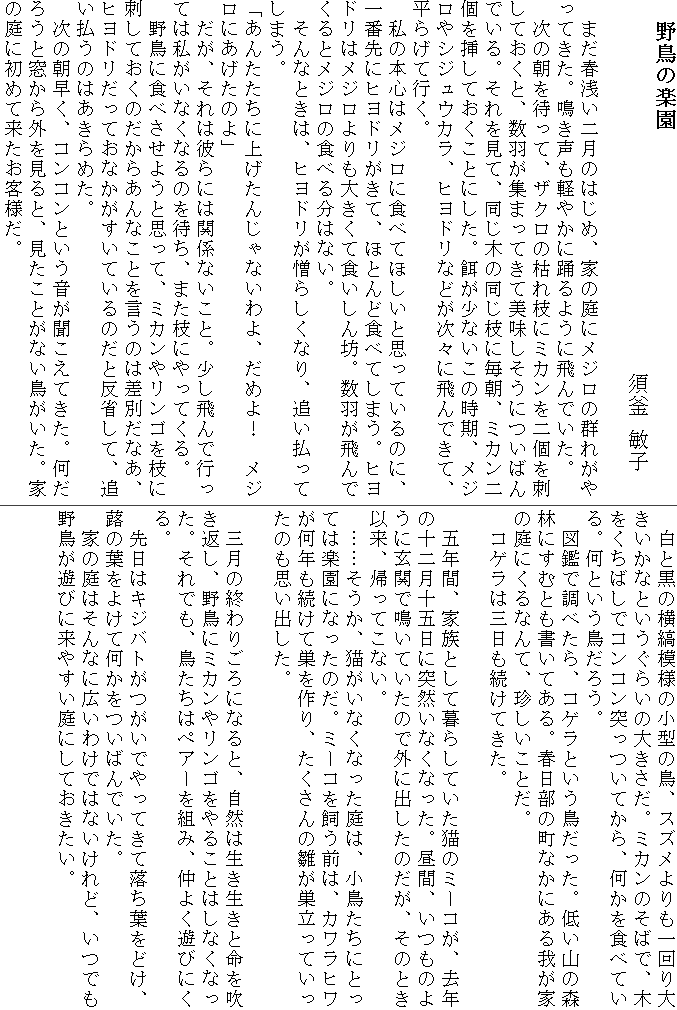 |

| 作者名 | 山本浩三 (自己紹介へ) |
||
| タイトル | 午後の居酒屋で考えた | これが私 | 安倍峠 |
| 私の中の私 | つかの間の道連れ | ちょっといい話 | |
| 近況報告 | |||
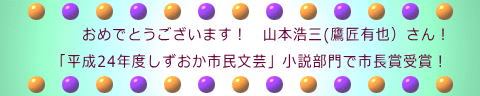
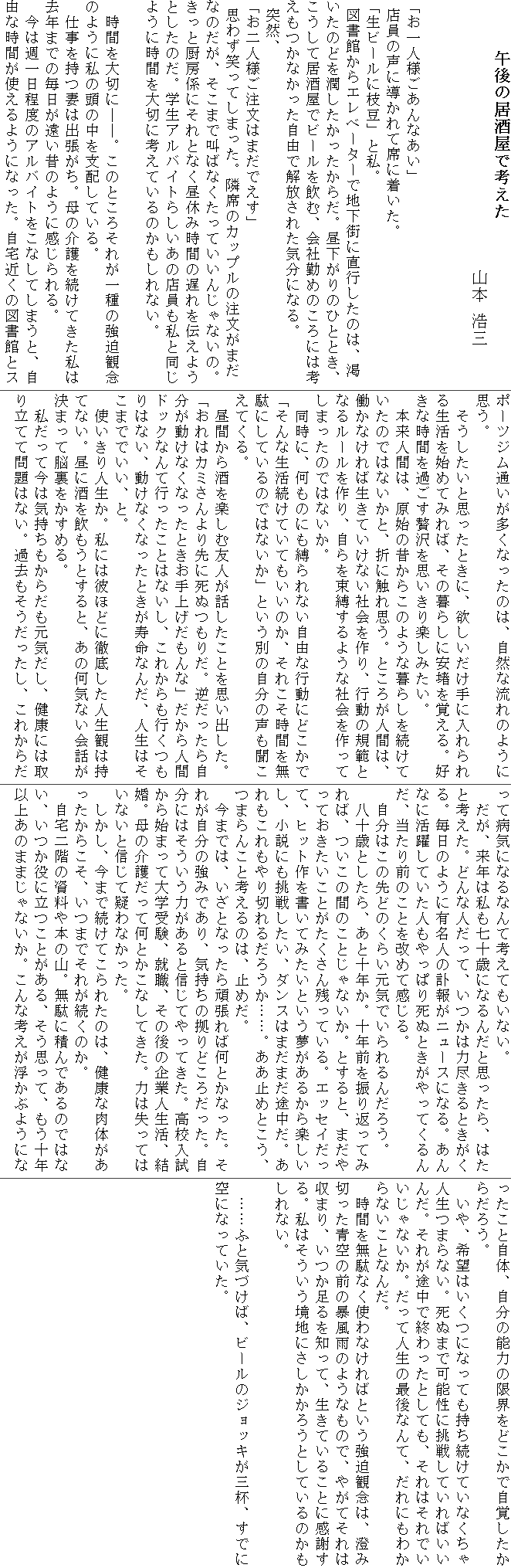 |
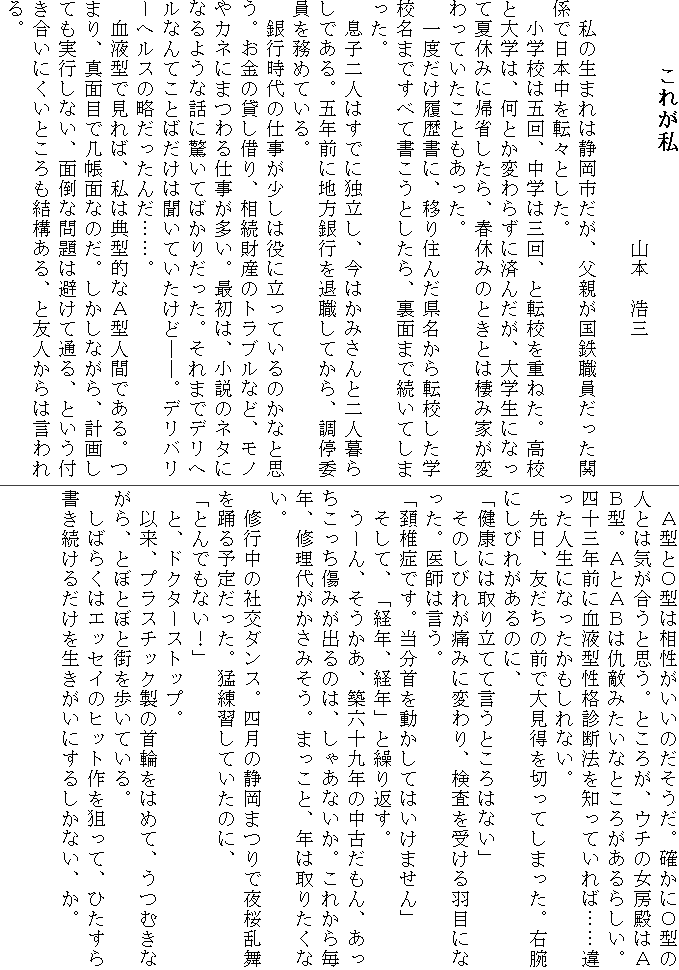 |
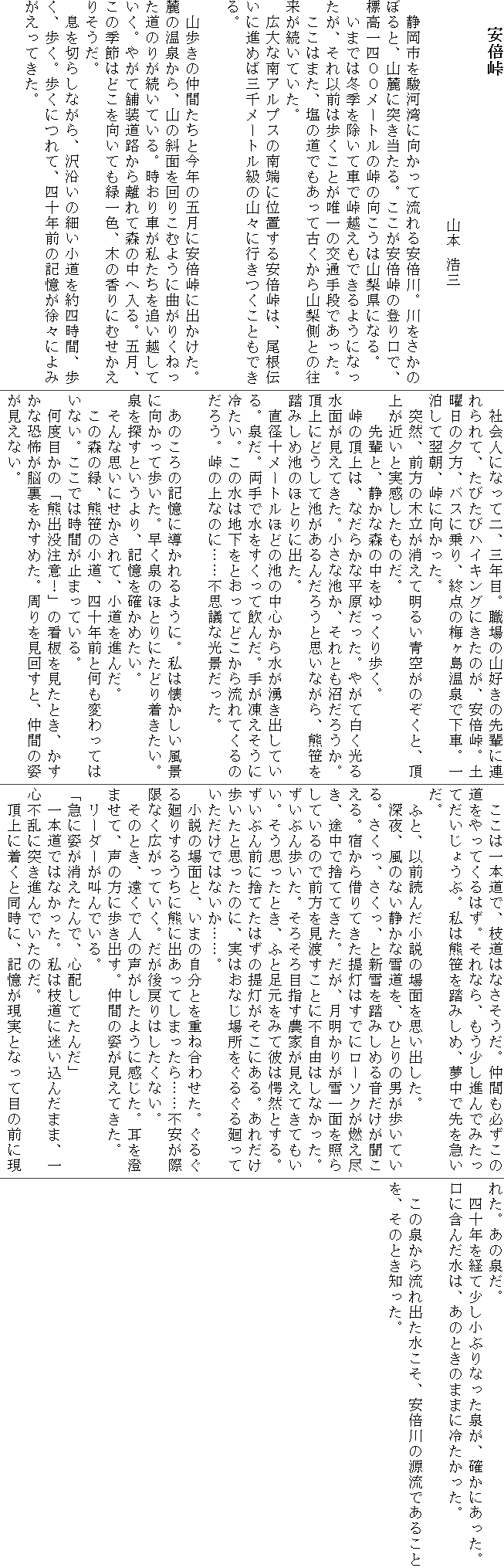 |
![私の中の私
山本 浩三
仕事の関係者であるSさんとはメールでやりとりすることも結構ある。彼に宛てたメールでも、メーリングリストに登録されている仲間には同じ内容が同時に配信される。興にのって地元・静岡の「しぞーか弁」でやってみると……。
[送信者]S
[件名]マツモト酒店、やっとみつけた!
山本さん。今日の会合にゃー、自転車で出かけだけんね。終わって帰ろうとしたときさあ、踏切を渡ったとこで思いついただよ。そうだ山本さん自慢の「マツモト酒店」は、たしかこの辺って聞いてたっけ。
頼まれもしないにやたら首つっこむのが好きだもんでその先を日吉町方向に右折してみただよ。山本さんから聞いてた「自慢の酒店」の道順を思い出しながらさ、この辺かやーって首を左に向けた途端に、あったよ、あった。「マツモト酒店」、だけん看板は「松本酒店」ってなってたっけよ。店長はキヨシさんかどうかは聞きそびれたけんね。
何やら、ちーっと雰囲気がある店だね。子供の頃の同級生のうちが酒屋でさあ、思い出すねえ。あのころ、まだ明るいうちっから近所のおじさん連中がその店に寄り合ってさ、コップに酒をなみなみ注いで飲んでただよ。
つまみは、ガラス瓶に入ってるピーナッツだの塩豆でね。一升瓶から注いだのか、樽からだったか憶えちゃいねえが……。はっきり覚えてるのは、なんでこんな明りいうちっから酒飲むずらって、不思議だっけね。
山本さんも、こう暑い日じゃあ夕方っから、マツモト酒店のガラス戸をくぐって、顔見知りとワイワイ、チビリっとやっているのかやあ。この年んなると、やっぱウラヤマシイッて感じるなあ。まだ仕事中だけえが、ちーっとらっつ飲んでりゃわかんねかなー。
いつも何飲んでるだか? あっ今ごろはちょうど現地で給油中の時間かあ、このメールを読むのはもうちーっと後んなるだね。
[送信者] 山本
[件名] 魚由商店
わざわざ訪ねてったのかやー、マツモト酒店へ。中へ入いりゃええのに。ところでさ、マツモト酒店の常連客の一人に魚由さんちゅう人がいるだよ、「うおよし」って読むだけんね。
伝馬町通りの鮮魚問屋・魚由商店の社長なんだよ。だけえが社長っちゅうよりか魚屋の親父っていったほうがぴったりだね。笑うと目が無くなるとこが、なんともいえずいいだよ。いちど見りゃあ忘れない顔だね。
魚由さんは、魚屋だけん寿司も造ってて、小売もやってるだよ。通りに面した軒先に「本日お寿司あります」って書いた週刊誌ぐれえの札がぶら下がって、風に揺られてぺろん、ぺろんて舞ってるだよ。
たいていは、夕方までで売り切れになっちゃって札が外されちゃうけどね。
寿司は、握りとちらしと二種類だけで、ワンパック三百五十円、三パックなら千円、安いよう。握りは九かんで、ネタはその日によって変るだよ。ちらしは、これがすんげえ、「地」のシャリが見えねえくらいネタで覆われててさあ、鮮度も保証済みだね。なんしろ毎朝暗えうちから息子さんが市場へ行って仕入れてくるだよ。本ものの寿司屋か、それ以上の味だね、ありゃあ。一度行ってみるとええよ。
だけん、昼時十二時から一時間、店ん中あ真っ暗になるさー。行くとき時間見てった方がええ。魚由商店は、近所の人っちとか、OLさんちでいっときゃ賑わうだけん、かんじんの昼どきは社長が、昼寝してるもんで、店員もいなくなっちゃうさー。
「かきいれどきずら、なぜっ?」って訊いたら、「そんなん儲かんなくてもいいだだよ」と、例の笑顔さ。
魚由さんは、仕事を片づけるとマツモト酒店に姿を現すね。畳サイズのテーブルを囲んで、おらっちと団欒のひとときを過ごすってわけさ。
魚由さんとは同年代、いつまでもお互い元気で、いい飲み仲間でいたいと思うよ。
知り合いにこのメール文を見せたら、
「いつもと違う感じで、おやっと思った。普段より実感がこもっていて面白いよ」
と、言われた。
話し慣れた言葉だと、体面や建前の世界とは違う自分になれるのだろうか。一種の快感が湧いた。他人を意識して面白がらせる心理、とも違うように思える。
静岡弁を話す私を、共通語の私が眺めている……というようないわく言いがたい感覚なのだが、それを不自然と感じないのが、愉快だ。](vimgtext100.gif) |
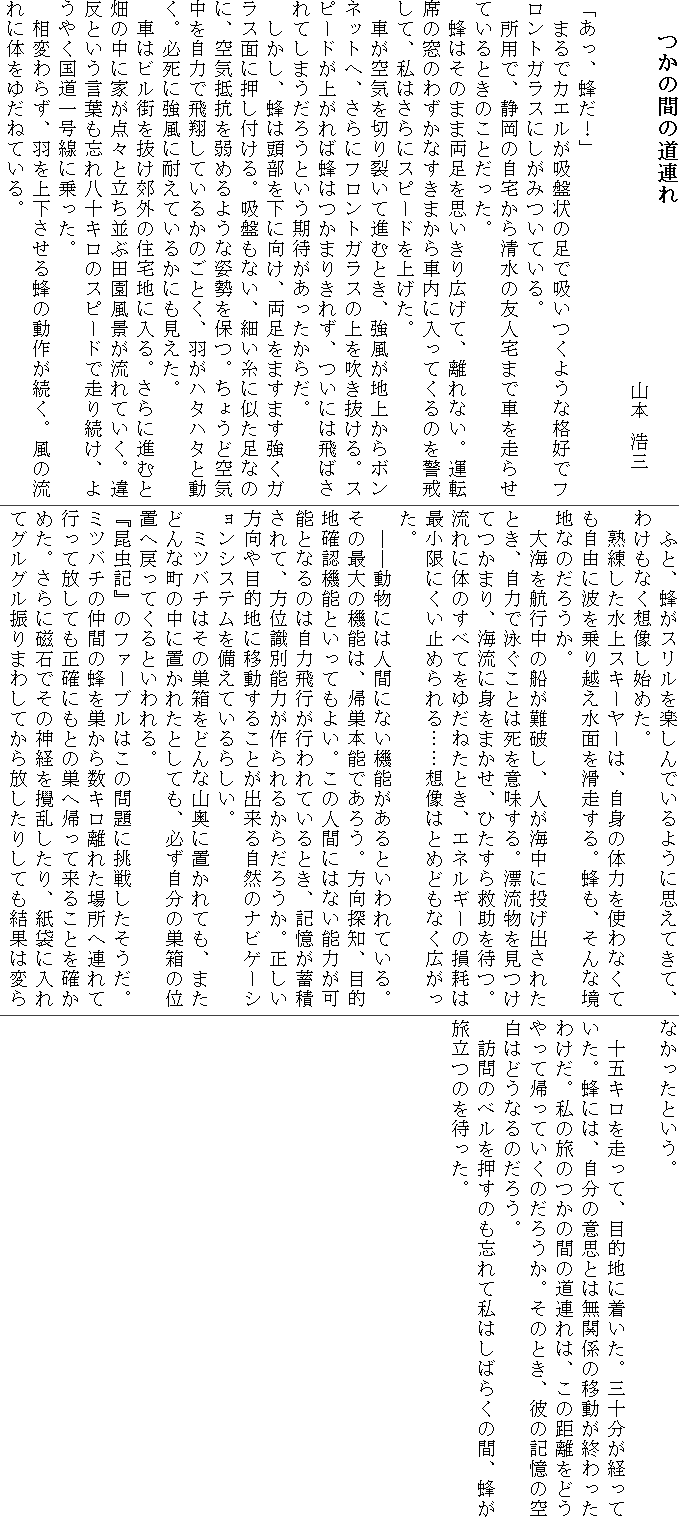 |
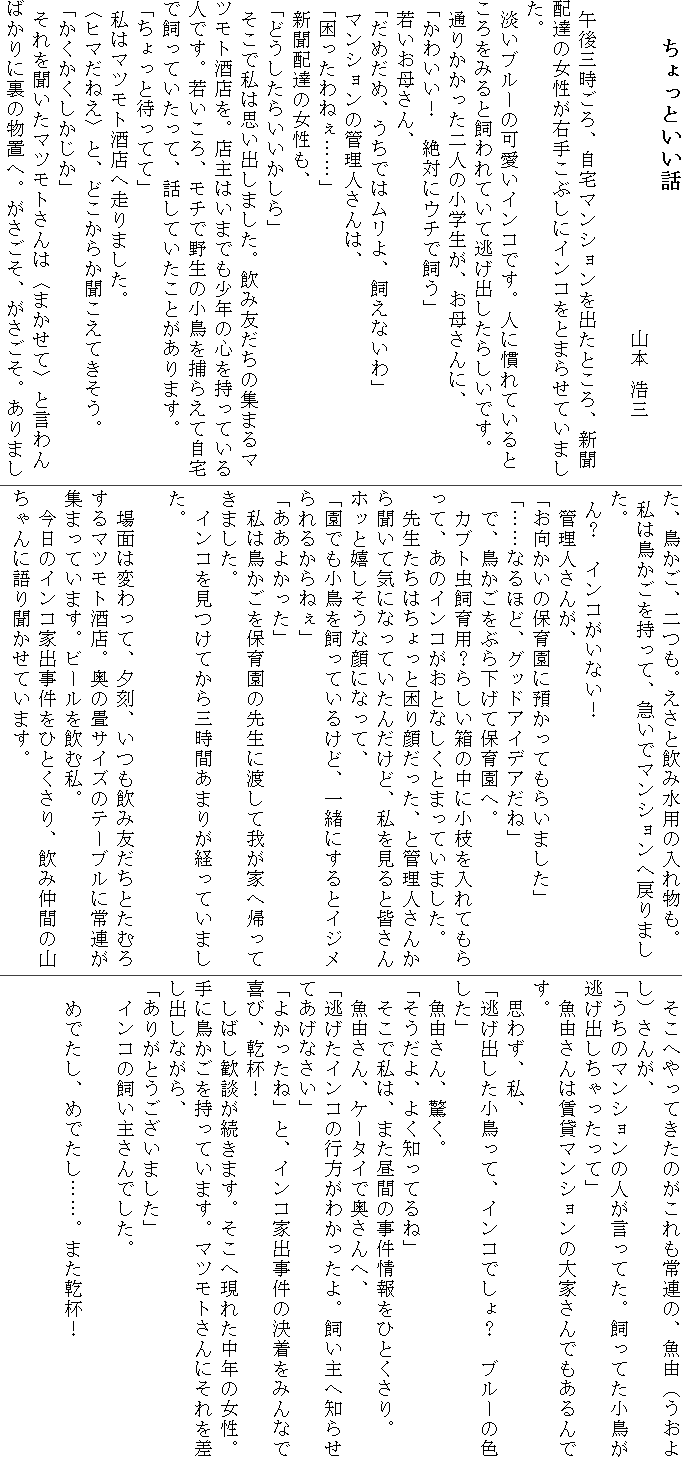 |
| 太宰治の、句点のない文体にあこがれています。無謀と知りつつ挑戦してみました。 (山本浩三) |
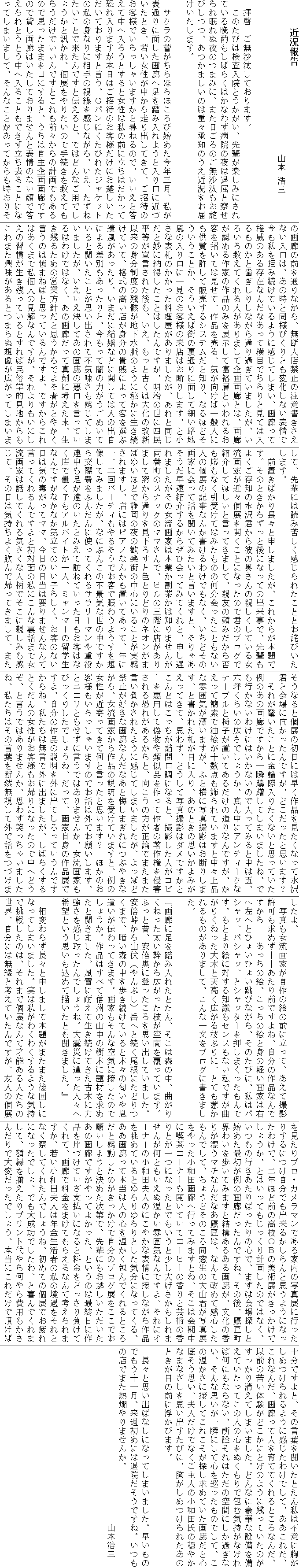 |