 |
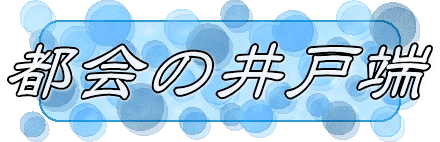 |
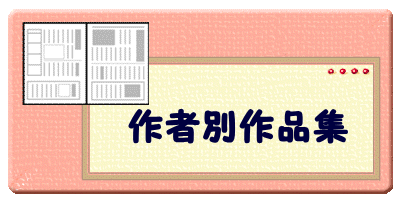 |
| あんこ | 北崎理子 | 工藤知恵子 | 小松なつみ | 小璃間けい |
| 佐々木洋子 | 篠宮亜季子 | 柴田真利子 | 島田閏江 | しらす・よみひと |
| 須釜敏子 | 土屋千春 | 中山怜子 | 掘内弘之 | 松木芽茂 |
| 萩原けい子 | 山本浩三 | (故)嶋岡忠 | のりすけ |

| 作者名 | 土屋千春 (自己紹介へ) |
||
| タイトル | 新聞が好き | バーベキューは大ぜいで | ばばちゃま神話 |
| 大正生まれの母たち | 神様の贈り物 | ラプソディー イン ブルー | |
| ぜいたくな朝 | 我が家の味 | ご苦労さま | |
| 携帯メール | 葬式無用 戒名無用 | 戒めの五百円 | |
| 嵐を呼ぶ男 | new! 季節の贈り物 | ||
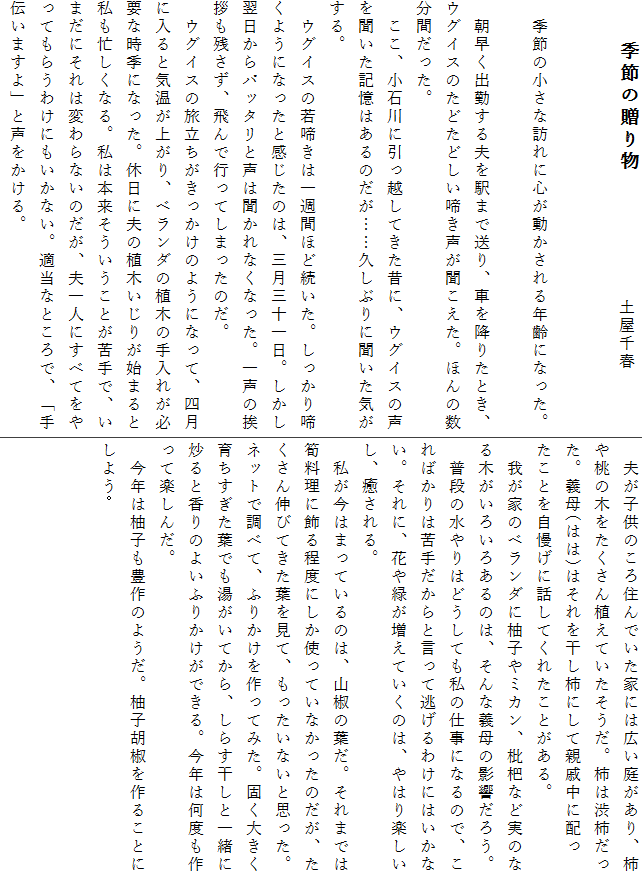 |
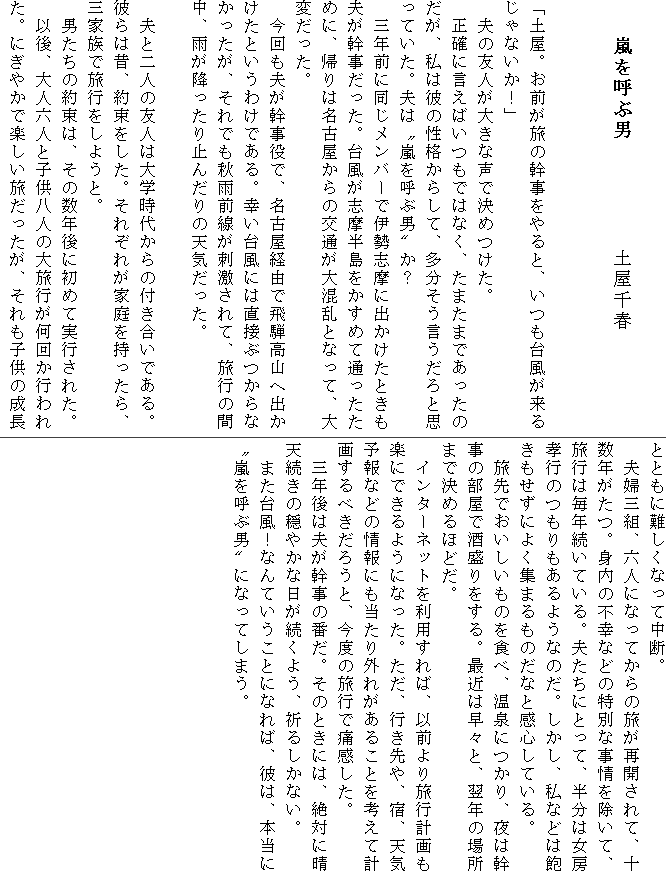 |
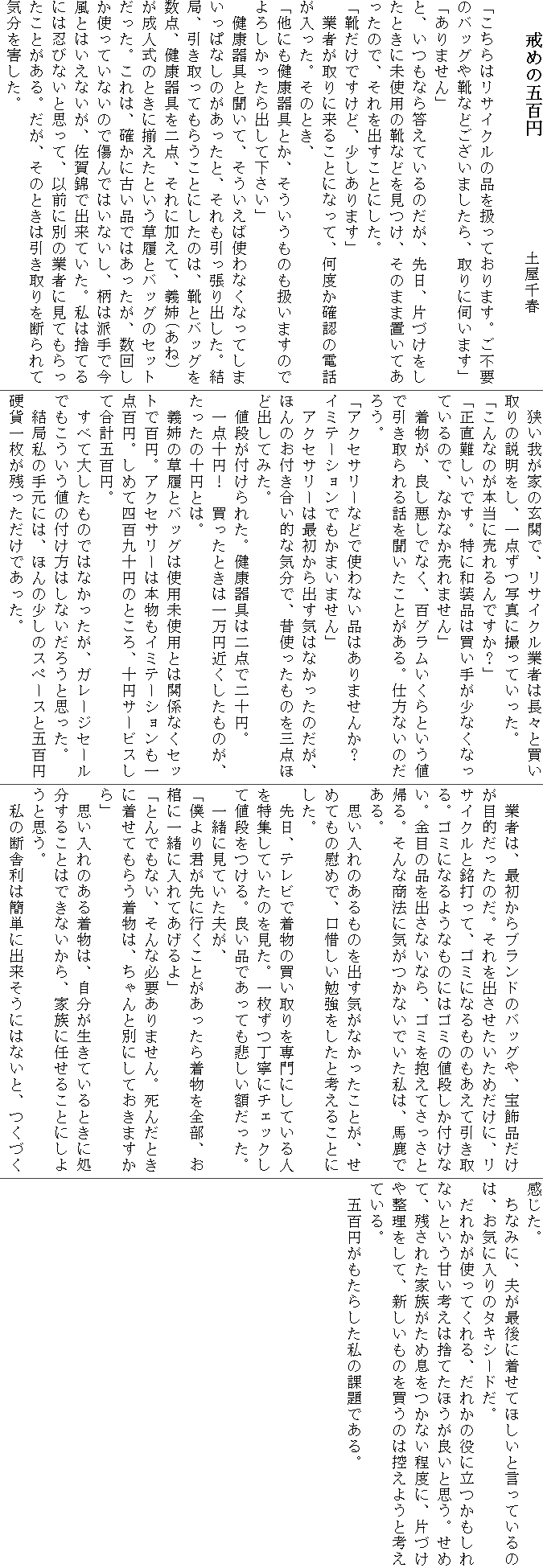 |
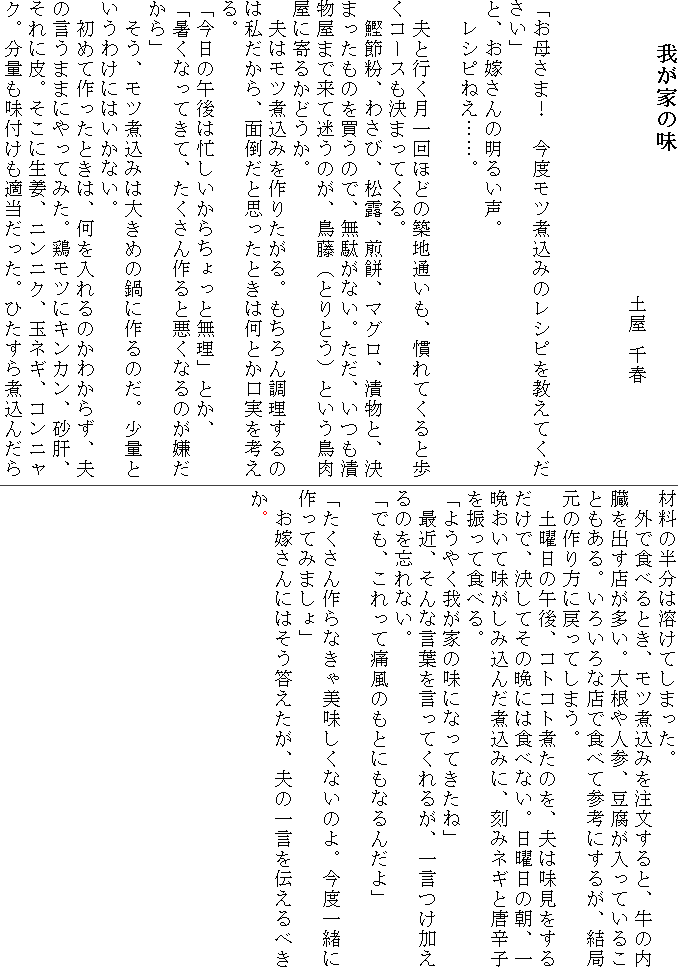 |
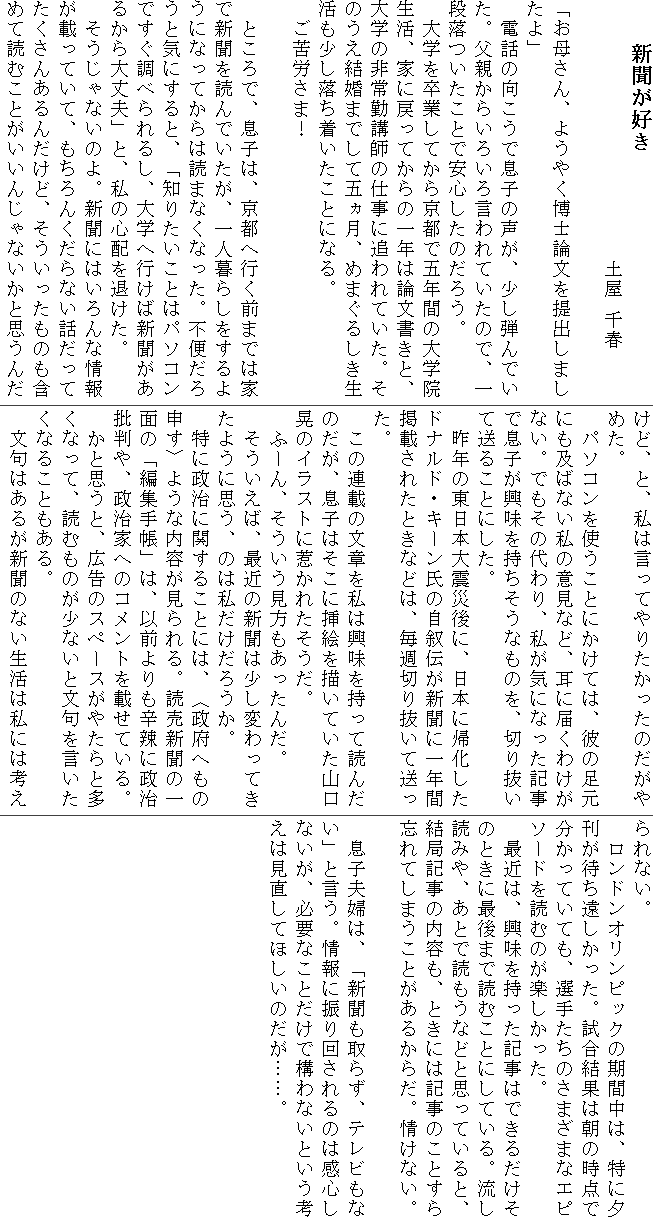 |
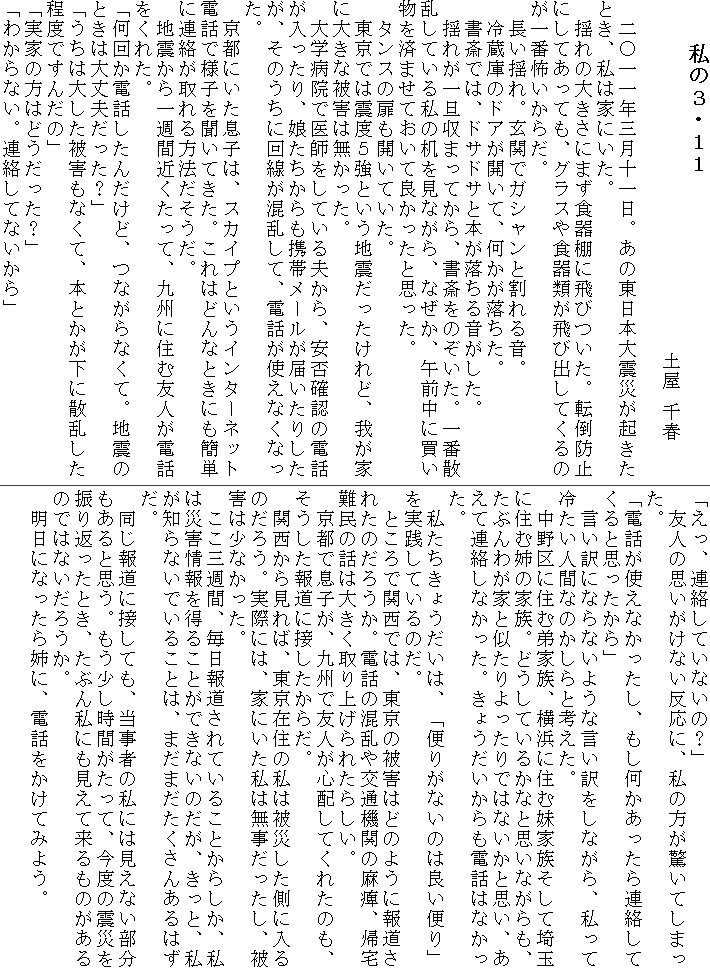 |
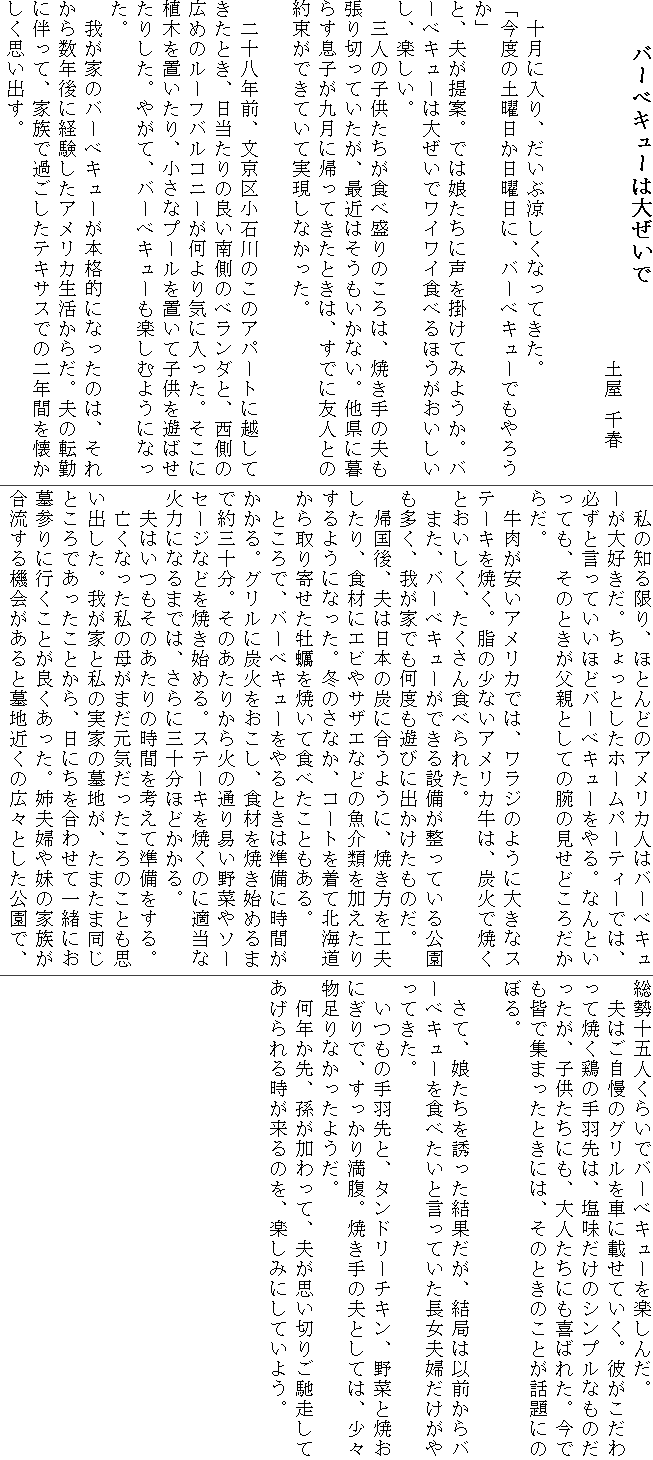 |
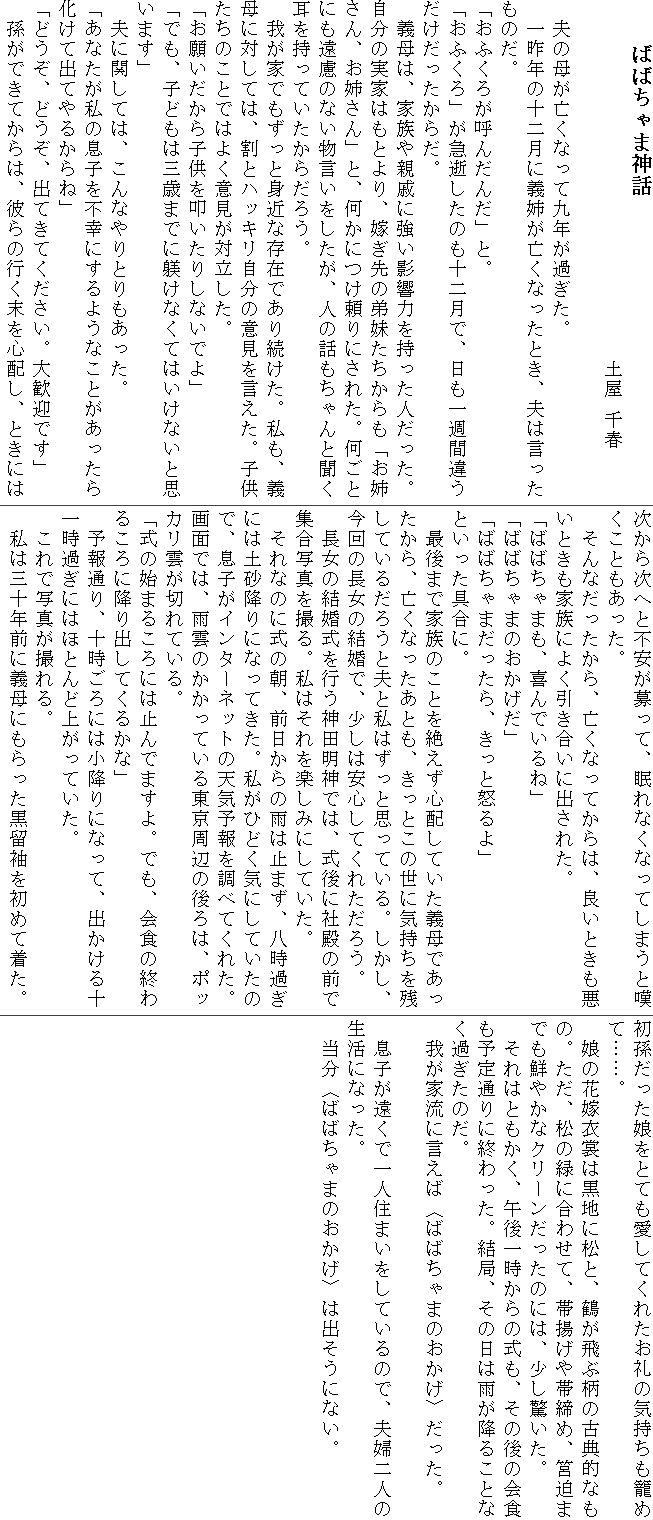 |
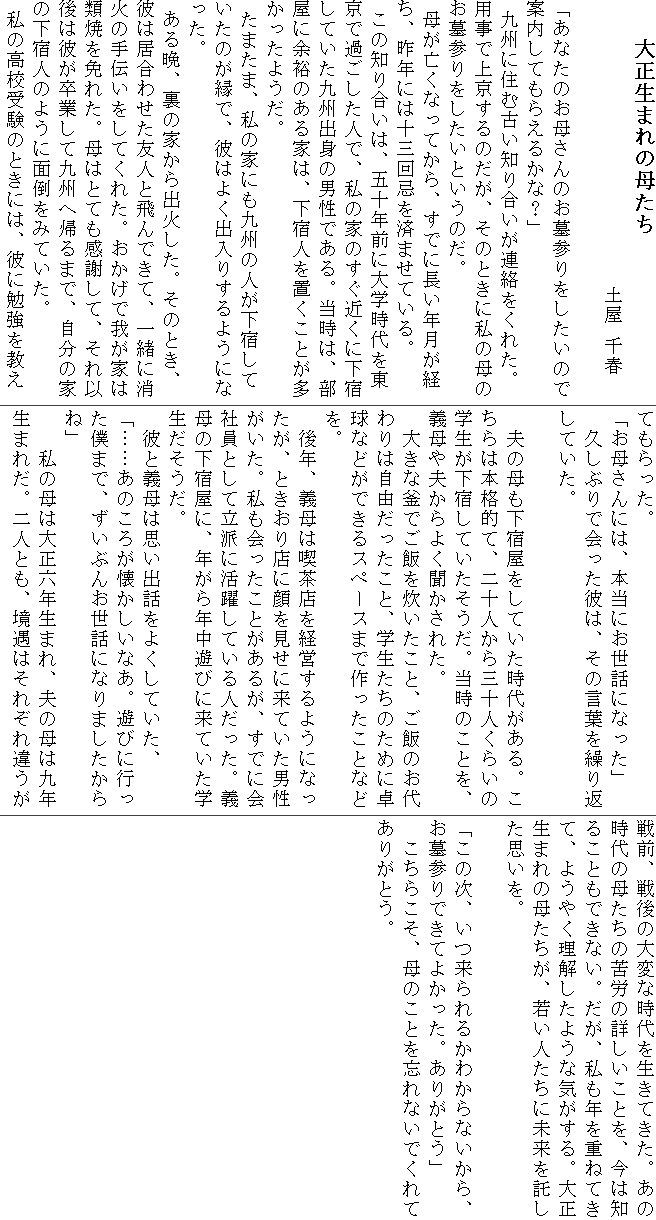 |
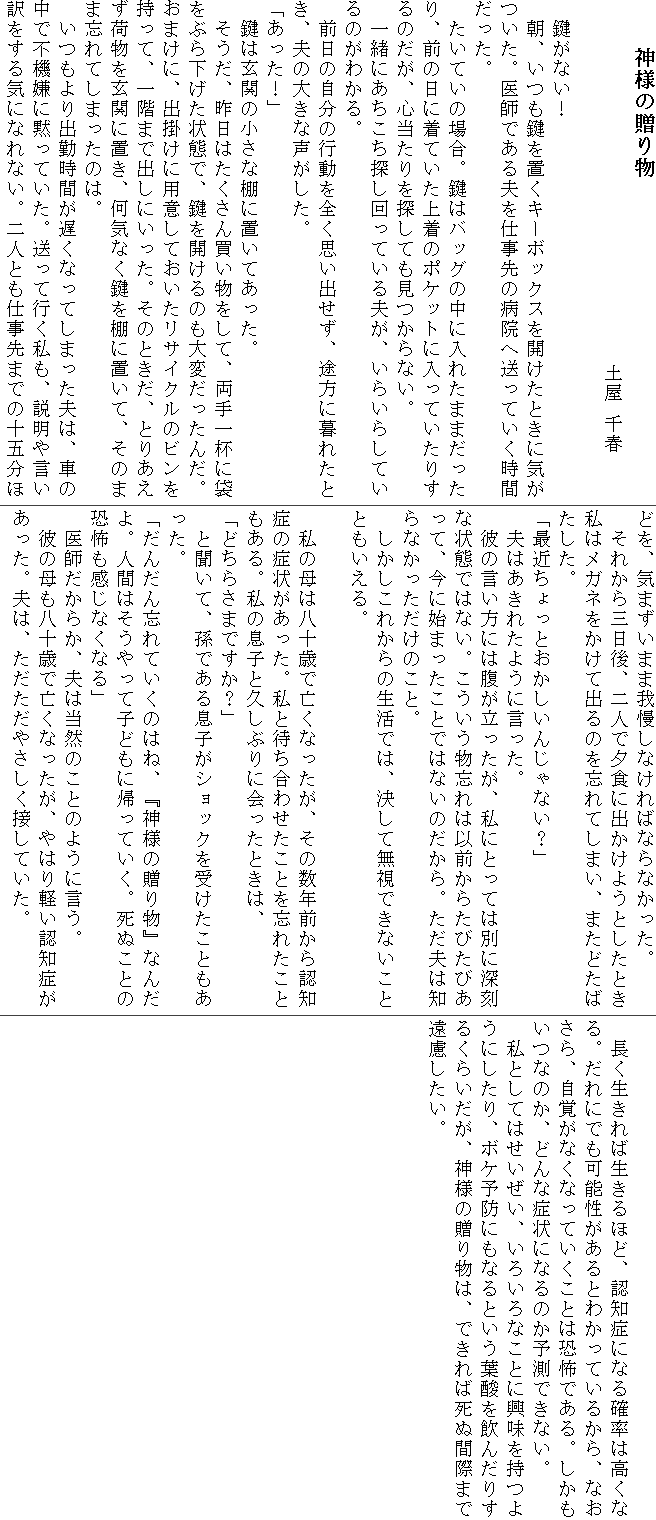 |
 |
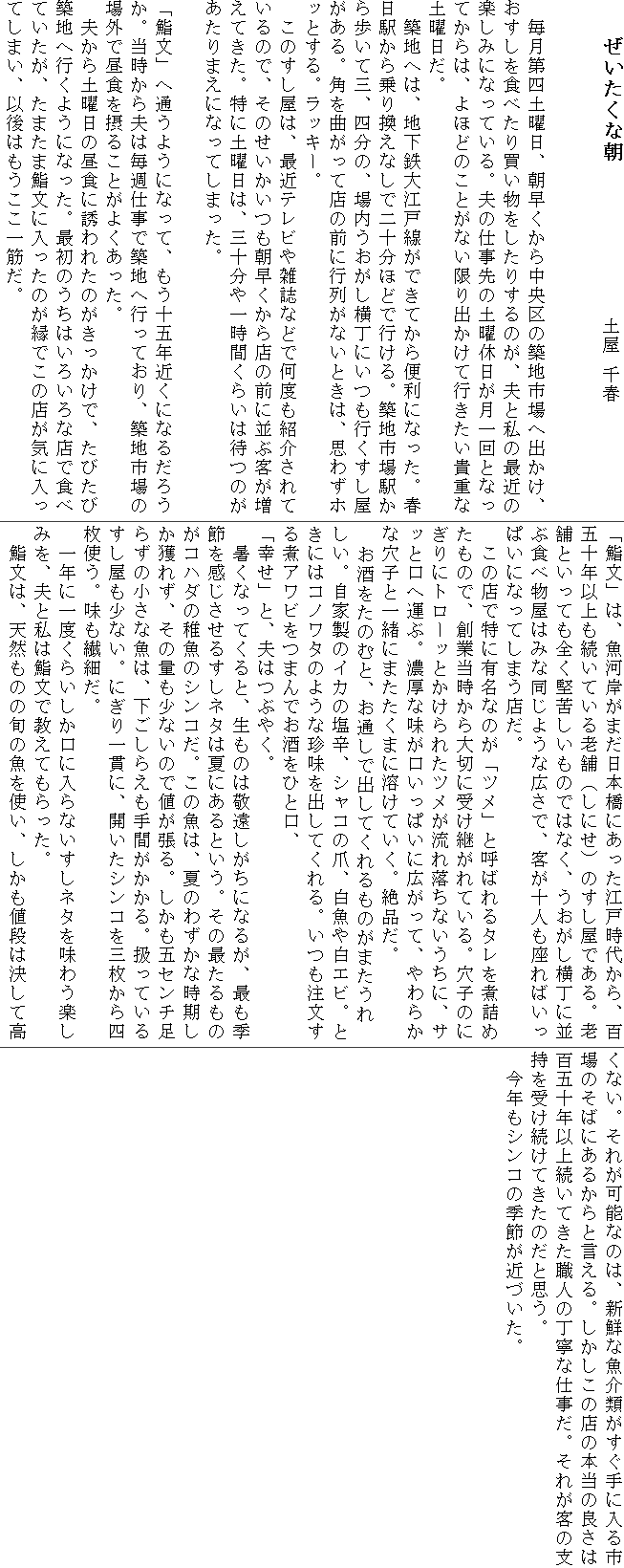 |

| 作者名 | 中山怜子 (自己紹介へ) |
||
| タイトル | 私の3・11 | 紅茶のおいしい喫茶店 | 銀杏の味 |
| 貧乏神 | 切手帳をひらくと | 家庭の事情? | |
| 3回連載・文京区の洋菓子店「カド」の歴史をたどる さくらんぼが実るころ 第1回、 第2回、 第3回、 |
|||
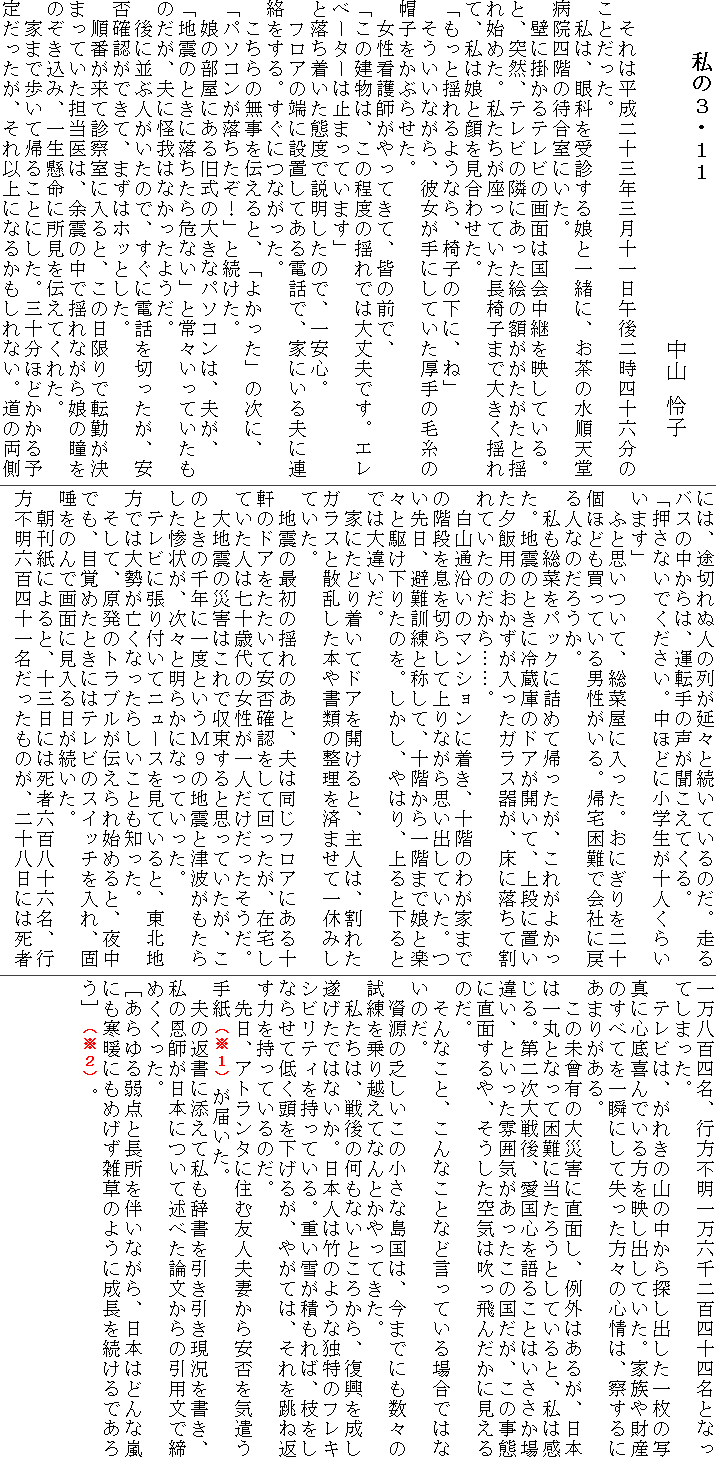
|
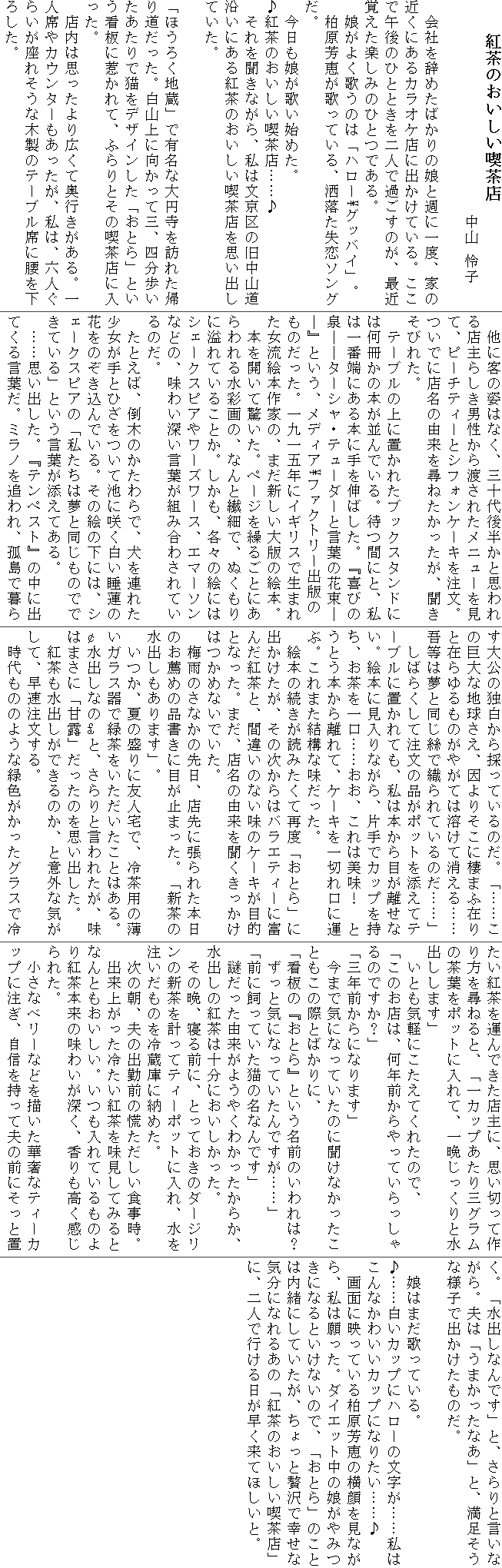 |
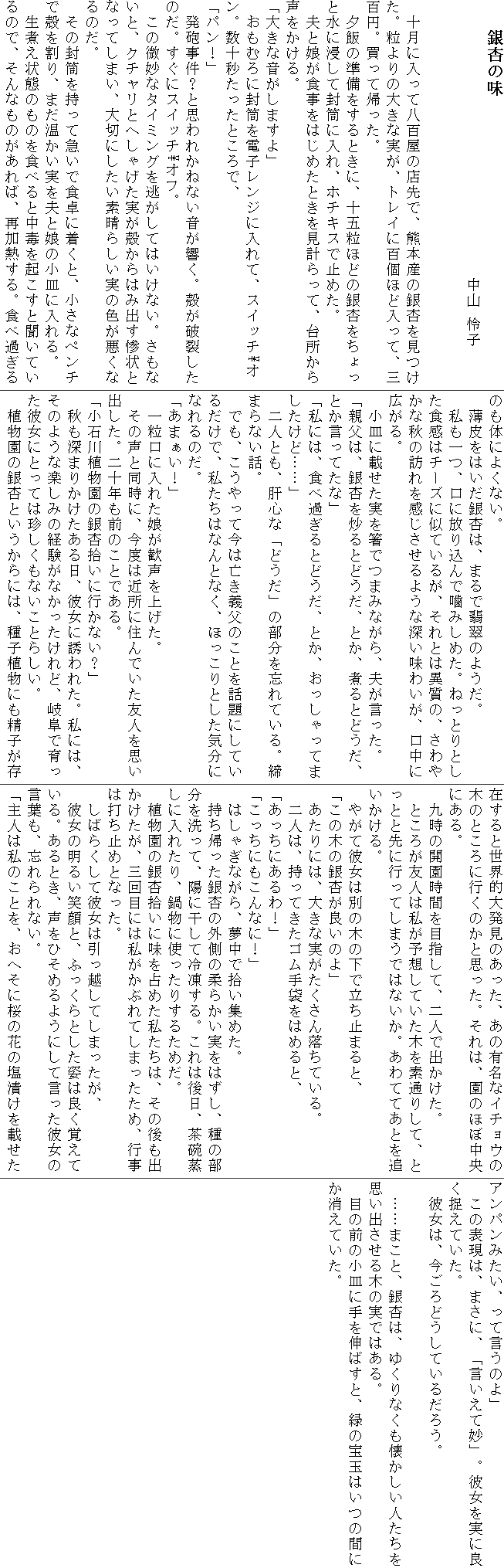 |
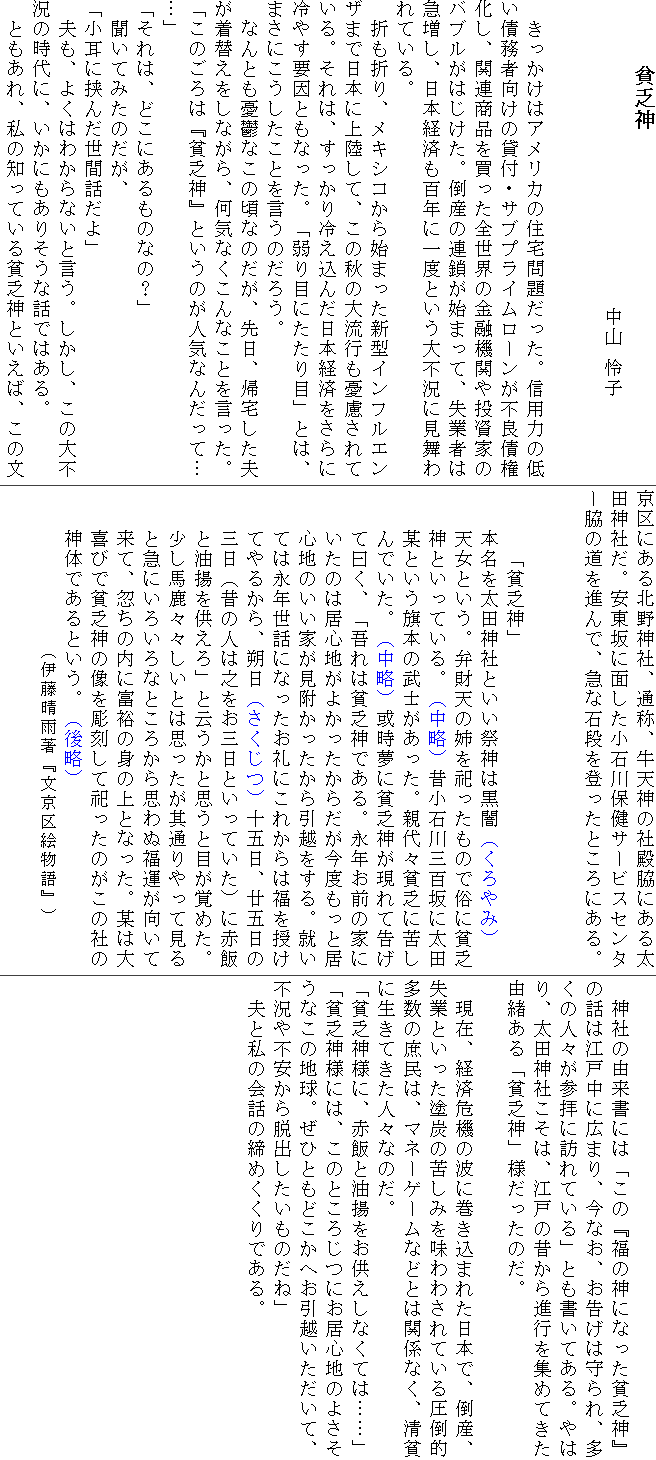 |
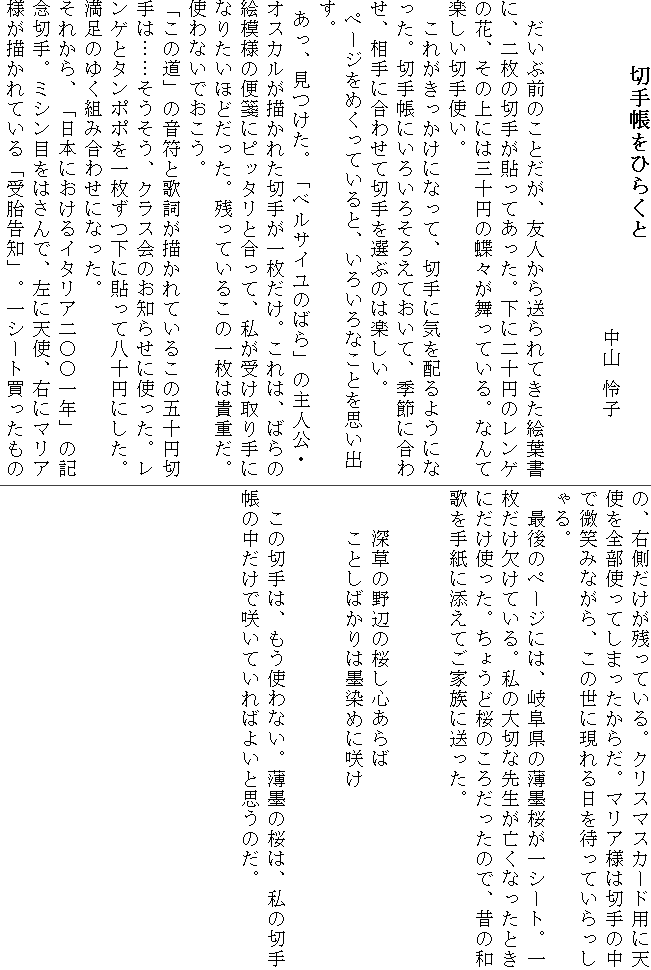 |
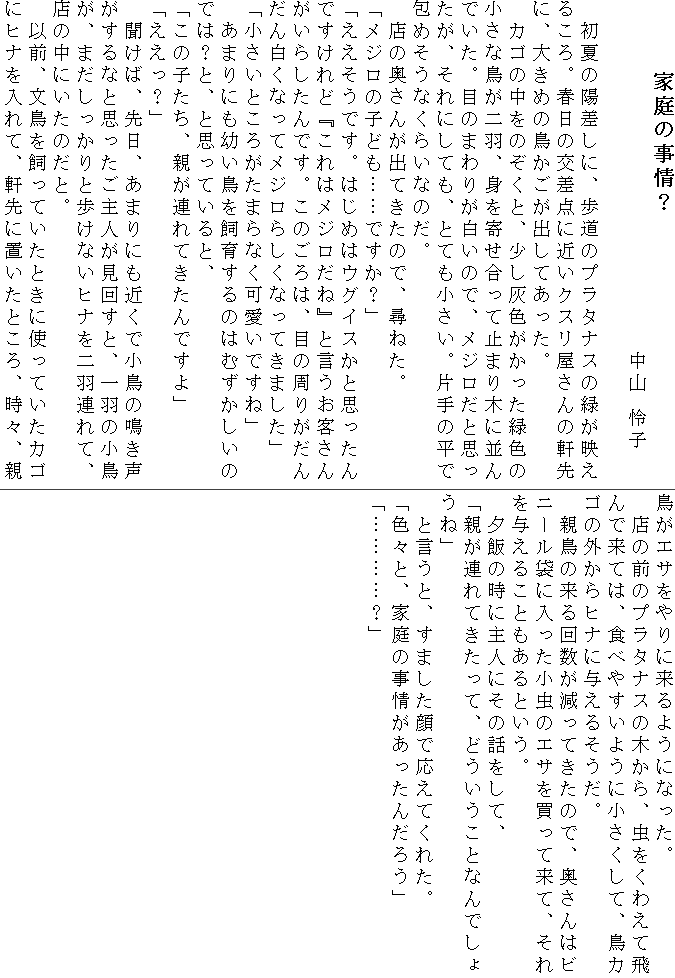 |
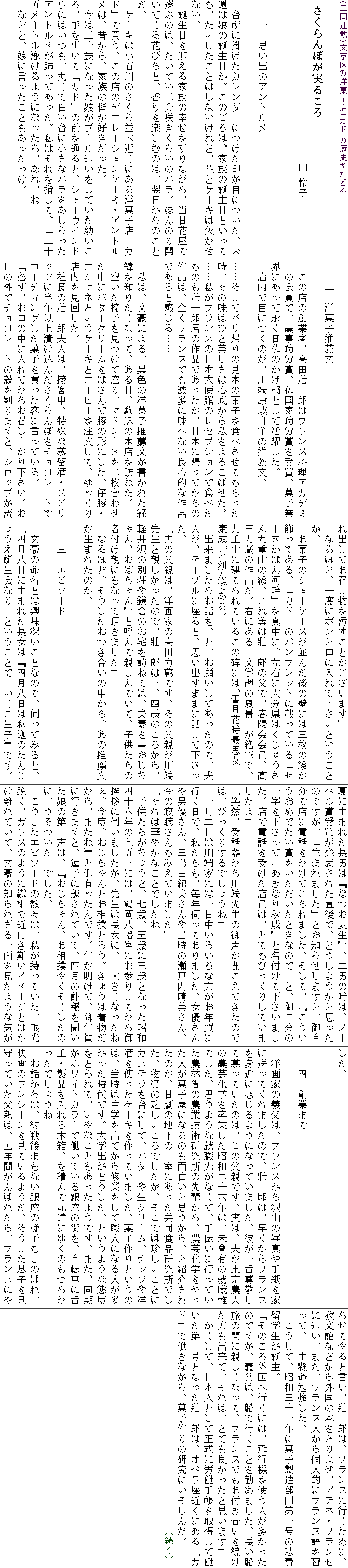 |
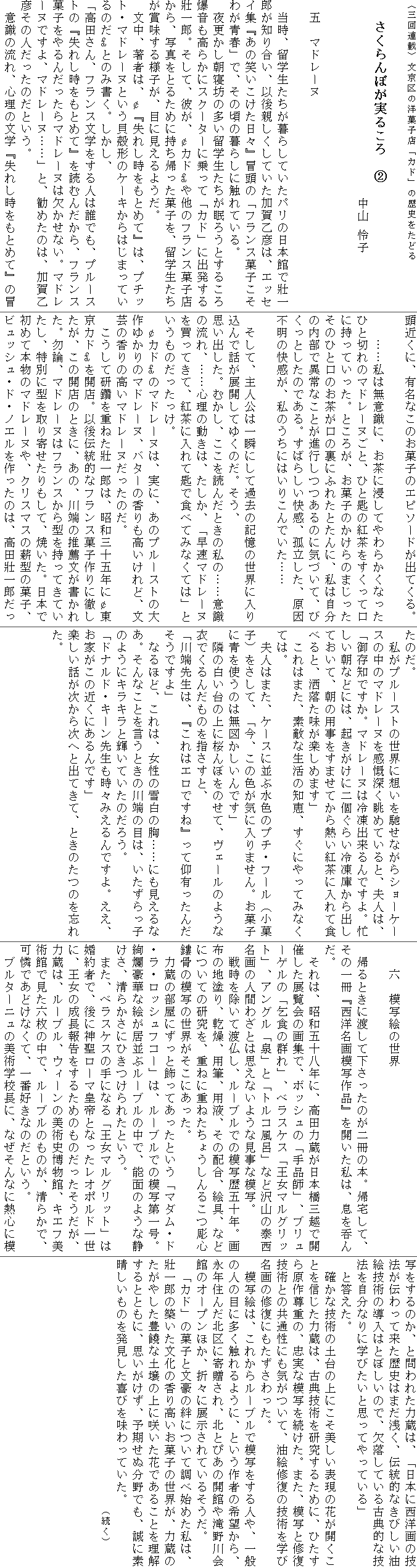 |
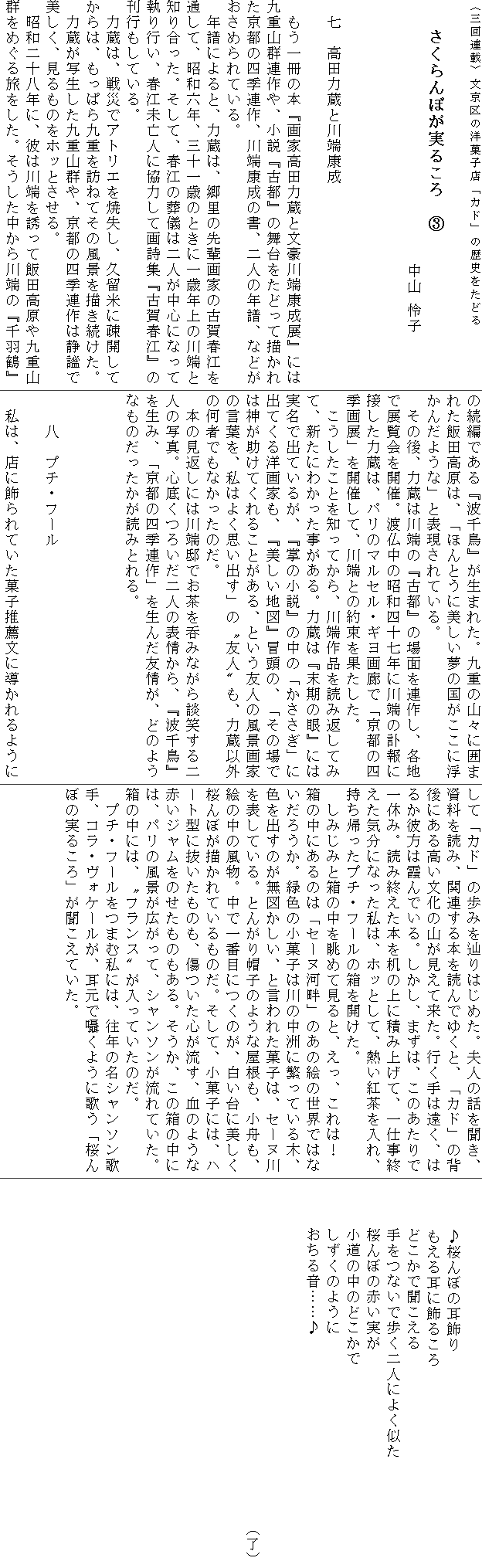 |